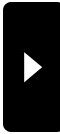2018年06月25日
平成30年度第1回レインボーツアー「奈良4寺巡礼」
日野町町民会館わたむきホール虹では会員制ですが「レインボーツアー」と言う事業があります。
わたむきホール虹では鑑賞できないお祭りや伝統行事、あるいは寺社仏閣等の歴史的施設の見学を目的に行っている事業です。
昨日(6月24日)、本年度1回目のレインボーツアーを開催。奈良4寺巡礼として、安倍文殊院・岡寺・長谷寺・室生寺に行ってまいりました。どのお寺のご本尊も素晴らしく、さすが国宝、重要文化財だと見とれてしまいました。ご本尊やその他の仏像は撮影NGですので写真としては紹介できません。残念。しかし、今回のレインボーツアーの雰囲気だけはお知らせしようと何枚か写真を公開いたします。ちなみにアジサイがキレイなのは長谷寺です。
会員制の事業と言いましたが、随時会員は募集しています。もちろん会員登録は無料ですので、ご興味のある方はわたむきホール虹までご一報ください。




わたむきホール虹では鑑賞できないお祭りや伝統行事、あるいは寺社仏閣等の歴史的施設の見学を目的に行っている事業です。
昨日(6月24日)、本年度1回目のレインボーツアーを開催。奈良4寺巡礼として、安倍文殊院・岡寺・長谷寺・室生寺に行ってまいりました。どのお寺のご本尊も素晴らしく、さすが国宝、重要文化財だと見とれてしまいました。ご本尊やその他の仏像は撮影NGですので写真としては紹介できません。残念。しかし、今回のレインボーツアーの雰囲気だけはお知らせしようと何枚か写真を公開いたします。ちなみにアジサイがキレイなのは長谷寺です。
会員制の事業と言いましたが、随時会員は募集しています。もちろん会員登録は無料ですので、ご興味のある方はわたむきホール虹までご一報ください。




2016年06月11日
【開催中】福山敬之 日本画展
みなさん、こんにちは
梅雨入りということですが、
意外にさわやかな日々が続いていますね。
今のうちに衣替えを済まして
家中の冷房器具のホコリをはらって・・・と
「やるべきことリスト」はたくさんあるのですが、
結局何かが終わっていないまま
雨が降り続く日々を迎えてしまうのが
毎年のこととなっています・・・。
さて、わたむきホール虹美術ギャラリーでは
夏の始まりにふさわしく
緑が印象的な数々の風景が描かれた
日本画の展覧会が行われています。
福山敬之 日本画展
「風景 日野」
6月9日(金)~7月3日(日)

今回作品を出展してくださったのは
東近江市在住の日本画家
福山敬之(ふくやま たかゆき)さんです。

嵯峨美術短大で日本画を学び
その後約25年にわたり画家として
自らの作品世界を追求してきた
福山さん。
2013年にはアメリカ・ミシガン州と滋賀県の
芸術交流展
「Art from the Lakes」の開催にあたり
中心的役割を担われました。
福山さんは、いつも風景画を
描いているそうです。
福山さんの画に描かれた風景はすべて
独特の静謐をたたえ、
清浄な空気に満たされている印象を受けます。

(ミシガン州のオーヴィッド村の風景を描いた作品)
「描きたいと思った風景に出会ったときの思いを、
どうすれば表現できるか日々挑戦している」
という福山さんの眼と心が
どんな風に目の前の世界をとらえているか
少しだけお話を伺うことができました。
―今回は日野の風景を
いくつか描いてくださったんですね。
・・・この景色は・・・?

(福山さん)「北畑口の方からこっち
(わたむきホール虹方面)を
見ている道なんですけど。
地平線の方に、わたむきホールがあるんですよ」
(注:画の中にホールが描いてあるという意味ではないのです。)

(日野町在住の皆さんは、あの場所か!と、ぴんとくるかもしれません)
「この日は、住んでいる東近江市の平田から
日野まで歩いてきたんです。20kmぐらい」
20kmという距離に驚きながら、
同時に納得もしてしまうのは
福山さんが描いた風景がどれも
“車だったらたぶん通り過ぎている”と
思うような、ごくさりげない場所にあるせいです。
こういった風景は、歩く速度でなければ
きちんと眼に入ってこないという気がします。

(日野町のTさんのお宅を、田んぼ越しに見た風景。
三角形のお家がさりげなくも印象的)
―日野の風景を描かれて、
何か感じられたことはありますか?
「やっぱり、僕の住んでいる平田とは
日野は違う文化圏だということを感じますよね。
絵を描きながらそういうものを探索する楽しみが
ありますね」
―どういったところが違うと思われますか。
「それがわかるところまで踏み込めて
いないですけど。
でも、風景ににじみ出ているものがある。
そこに住んでいる人のリアリティというか・・・」
“住人たちがそこに暮らすリアリティが
風景ににじみ出る”
福山さんは、非常に印象的な言葉で
その土地の“個性”や“風土”と
呼ばれるもののことを表現されました。
「日野町は・・・ほいのぼりとか日野祭とか
伝統が色濃く残っているでしょう。
一方、オバマ大統領が先日初めて広島を訪れ、
被爆者の方と言葉を交わされるなど
世界的な歴史の流れというものがあって。
だけど日野町では、
そういう世界的な流れとはまた全く別に
時間が流れ、人が生まれたり亡くなったり
しているような感じも受ける。
そういうところが、何か自分と
波長が合うような気もしますね」
自分の画はまだ道半ば、という感じです。
本当にいい画は、見た後に
早く家に帰って自分も何かしなきゃ、
という気を起こさせるものですから。
僕の画はまだそこまでいっていないかな・・・。
そう話される福山さん。
しかし、福山さんの画を
眺めているときの感覚は
かぎりなく、実際の風景を
見ているときのものに近いと感じます。
山や海をただ見るのと同じように
目に映るものに過剰な意味を求めずに
時間を過ごせる、というような。
そういった作品の存在は
今のこの時代にとって、
とても貴重なものだと思われるのです。

(蒲生地区に実在する風景を描いた作品「蒲生」)
画家の筆による、深呼吸したくなるような
いくつもの風景に囲まれ、
静かで充実した時を過ごせる展覧会です。
ぜひ、会期中にお越し下さい。
(6月14日(火)・21日(火)・28日(火)は休館日です)
梅雨入りということですが、
意外にさわやかな日々が続いていますね。
今のうちに衣替えを済まして
家中の冷房器具のホコリをはらって・・・と
「やるべきことリスト」はたくさんあるのですが、
結局何かが終わっていないまま
雨が降り続く日々を迎えてしまうのが
毎年のこととなっています・・・。
さて、わたむきホール虹美術ギャラリーでは
夏の始まりにふさわしく
緑が印象的な数々の風景が描かれた
日本画の展覧会が行われています。
福山敬之 日本画展
「風景 日野」
6月9日(金)~7月3日(日)

今回作品を出展してくださったのは
東近江市在住の日本画家
福山敬之(ふくやま たかゆき)さんです。

嵯峨美術短大で日本画を学び
その後約25年にわたり画家として
自らの作品世界を追求してきた
福山さん。
2013年にはアメリカ・ミシガン州と滋賀県の
芸術交流展
「Art from the Lakes」の開催にあたり
中心的役割を担われました。
福山さんは、いつも風景画を
描いているそうです。
福山さんの画に描かれた風景はすべて
独特の静謐をたたえ、
清浄な空気に満たされている印象を受けます。

(ミシガン州のオーヴィッド村の風景を描いた作品)
「描きたいと思った風景に出会ったときの思いを、
どうすれば表現できるか日々挑戦している」
という福山さんの眼と心が
どんな風に目の前の世界をとらえているか
少しだけお話を伺うことができました。
―今回は日野の風景を
いくつか描いてくださったんですね。
・・・この景色は・・・?

(福山さん)「北畑口の方からこっち
(わたむきホール虹方面)を
見ている道なんですけど。
地平線の方に、わたむきホールがあるんですよ」
(注:画の中にホールが描いてあるという意味ではないのです。)

(日野町在住の皆さんは、あの場所か!と、ぴんとくるかもしれません)
「この日は、住んでいる東近江市の平田から
日野まで歩いてきたんです。20kmぐらい」
20kmという距離に驚きながら、
同時に納得もしてしまうのは
福山さんが描いた風景がどれも
“車だったらたぶん通り過ぎている”と
思うような、ごくさりげない場所にあるせいです。
こういった風景は、歩く速度でなければ
きちんと眼に入ってこないという気がします。

(日野町のTさんのお宅を、田んぼ越しに見た風景。
三角形のお家がさりげなくも印象的)
―日野の風景を描かれて、
何か感じられたことはありますか?
「やっぱり、僕の住んでいる平田とは
日野は違う文化圏だということを感じますよね。
絵を描きながらそういうものを探索する楽しみが
ありますね」
―どういったところが違うと思われますか。
「それがわかるところまで踏み込めて
いないですけど。
でも、風景ににじみ出ているものがある。
そこに住んでいる人のリアリティというか・・・」
“住人たちがそこに暮らすリアリティが
風景ににじみ出る”
福山さんは、非常に印象的な言葉で
その土地の“個性”や“風土”と
呼ばれるもののことを表現されました。
「日野町は・・・ほいのぼりとか日野祭とか
伝統が色濃く残っているでしょう。
一方、オバマ大統領が先日初めて広島を訪れ、
被爆者の方と言葉を交わされるなど
世界的な歴史の流れというものがあって。
だけど日野町では、
そういう世界的な流れとはまた全く別に
時間が流れ、人が生まれたり亡くなったり
しているような感じも受ける。
そういうところが、何か自分と
波長が合うような気もしますね」
自分の画はまだ道半ば、という感じです。
本当にいい画は、見た後に
早く家に帰って自分も何かしなきゃ、
という気を起こさせるものですから。
僕の画はまだそこまでいっていないかな・・・。
そう話される福山さん。
しかし、福山さんの画を
眺めているときの感覚は
かぎりなく、実際の風景を
見ているときのものに近いと感じます。
山や海をただ見るのと同じように
目に映るものに過剰な意味を求めずに
時間を過ごせる、というような。
そういった作品の存在は
今のこの時代にとって、
とても貴重なものだと思われるのです。

(蒲生地区に実在する風景を描いた作品「蒲生」)
画家の筆による、深呼吸したくなるような
いくつもの風景に囲まれ、
静かで充実した時を過ごせる展覧会です。
ぜひ、会期中にお越し下さい。
(6月14日(火)・21日(火)・28日(火)は休館日です)
2016年05月21日
【開催中】福田貞一 切り絵&水彩スケッチ展
みなさん、こんにちは
本当にいいお天気が続きます。
青空に緑がまぶしいです。
この草や葉っぱの緑色ですが、
染色家の志村ふくみさんの本に
あらゆる草や葉っぱは緑色なのに
この世のどんな植物からも
直接、緑という色を取りだして
染めることはできない、
と書いてあり、驚いたことがあります。
緑色の葉っぱも草もなぜか
白い布を緑には染められない。
なんだか不思議だと思いませんか?
さて、さわやかな季節に
美術ギャラリーにて新しい展示が始まりました。
福田貞一
切り絵&水彩スケッチ展
~歩く旅の中で得たスケッチと
遊び心で制作した切り絵~
5月19日(木)~6月5日(日)

長浜市在住の福田貞一さんによる
30点の切り絵、そして11点の水彩スケッチ画の
展覧会です。
福田さんはこの方です。

福田さんは長年、教師として中学校で
子どもたちに美術を教え、
その職を引退された現在は、
短大で人権教育や教育実習指導などの
授業を行いつつ、
切り絵、そして旅行先でのスケッチ画を
制作されています。
切り絵とスケッチ、どちらにも
“センス”と呼びたい輝きが宿る
福田さんの作品。
その秘密について、お話を伺いました。
まずは切り絵のお話から。
福田さんの切り絵に描かれているのは
琵琶湖や県下の町並みの風景などの
“現実に存在するもの”が大半を占めます。
しかしご本人は
「(切り絵作家の)藤城清治さんの
メルヘン調の世界が好き」
なのだとか。
(福田さん)「絵本もやれたらいいなあと
思っているんですよ。
それで、最近は詩や俳句なんかを
作品に入れているんです」

(「八方尾根」と、これからそこに挑む登山者、そして俳句が絶妙なバランスで配置されたユニークな構図)
―この字体は、福田さんオリジナルの
デザインなんですか?
「そうです。元の生徒が僕の展示を見に来て
“レタリングが良かった”なんて
褒めてくれたことがありますが」
さらりと仕上げられた
楽しげで、遊び心に満ちた切り絵。
手先が器用かつ根気強い人にしか
向かない創作形態なのかとも思いますが・・・。
「いや、切り絵は簡単ですよ。
それはもう、後始末も楽だしね。
(図案さえ決まれば)あとは
テレビ見ながらでもできるでしょう」
ただし、もちろん難しい部分はあります。
「黒と白のバランスが難しい。
・・・あのね、僕は作品をつくったら
家のテレビの横に作品を置いてね、
繰り返し目に入るようにするんですよ。
そうすると、直さないといけないところに
気づくんです」

(作品の上と下に黒い色が帯状に入っています。この部分は最初白かったということですが、黒を入れるほうが作品が締まることを「テレビの横に置いて」気づかれたそう)
黒と白の配分が魅力的なものになるよう
考えられた福田さんの切り絵。
さらに、作品にはその奥行きをもっと深くする
心配りが施されています。
それは、わずかのことで
黒と白だけの世界に大きな変化を起こす
“さし色使い”の妙。


福田さんの切り絵を見ていると、
“デザイン”とは本当に素敵なものだな、
と思います。
作品にしたい対象を表すための、
重要な線やフォルムが何かを的確につかみ、
少ない要素で、対象をより印象に残るものに
表現する。
ほとんど黒と白だけの切り絵の世界が
こんなにも目を楽しませてくれるのは
“デザイン”の力が持つ、豊かさと遊び心に
ほかならないと感じます。

続いて水彩スケッチ画について。

「もともとは大学から、
管理職になる50代手前まで
ずーっと油絵をやってました。
だけど、歳をとると油絵は準備が大変なんです。
その点、水彩は準備も後かたづけも
楽なんですが、
描くのは難しいですね。
失敗しても直せないし(笑)」
スケッチ旅行をしていると
現地の人と絵をきっかけにして
話すことができるのが楽しみ、と
福田さんは言われます。

(横浜の南京町の様子。同じ図案の切り絵作品もギャラリー内にあります。さがしてみてください)
「歳をとると、気力、体力のエネルギーは
減っていきますが、
それでもたえず何かつくっていたいと
思いますね」
そう言われる福田さん。
ギャラリーに来られるお客様には
自分も何かしてみたいけど、
こんなに上手に出来ないと
言われる方も多いのです、と
お話しすると
「やったらいいと思うんです。
上手下手はないですよ。
自分を表に出すことが大事」
という言葉をくださいました。
「作品をつくる」という行為は
考えてみると、とても面白いものです。
紙を切り抜いたり、線を描いて色をつけたり
するだけで、
様々な人の目や心を喜ばせる何かを
形にすることができてしまいます。
今回、会場で福田さんの作品を
ご覧になったあとは、思いがけず
「何かをつくりたくなる気持ち」
が芽ばえるのを感じられるかもしれません。

(5月24日(火)・31日(火・)6月3日(金)は休館日です)

本当にいいお天気が続きます。
青空に緑がまぶしいです。
この草や葉っぱの緑色ですが、
染色家の志村ふくみさんの本に
あらゆる草や葉っぱは緑色なのに
この世のどんな植物からも
直接、緑という色を取りだして
染めることはできない、
と書いてあり、驚いたことがあります。
緑色の葉っぱも草もなぜか
白い布を緑には染められない。
なんだか不思議だと思いませんか?
さて、さわやかな季節に
美術ギャラリーにて新しい展示が始まりました。
福田貞一
切り絵&水彩スケッチ展
~歩く旅の中で得たスケッチと
遊び心で制作した切り絵~
5月19日(木)~6月5日(日)

長浜市在住の福田貞一さんによる
30点の切り絵、そして11点の水彩スケッチ画の
展覧会です。
福田さんはこの方です。

福田さんは長年、教師として中学校で
子どもたちに美術を教え、
その職を引退された現在は、
短大で人権教育や教育実習指導などの
授業を行いつつ、
切り絵、そして旅行先でのスケッチ画を
制作されています。
切り絵とスケッチ、どちらにも
“センス”と呼びたい輝きが宿る
福田さんの作品。
その秘密について、お話を伺いました。
まずは切り絵のお話から。
福田さんの切り絵に描かれているのは
琵琶湖や県下の町並みの風景などの
“現実に存在するもの”が大半を占めます。
しかしご本人は
「(切り絵作家の)藤城清治さんの
メルヘン調の世界が好き」
なのだとか。
(福田さん)「絵本もやれたらいいなあと
思っているんですよ。
それで、最近は詩や俳句なんかを
作品に入れているんです」

(「八方尾根」と、これからそこに挑む登山者、そして俳句が絶妙なバランスで配置されたユニークな構図)
―この字体は、福田さんオリジナルの
デザインなんですか?
「そうです。元の生徒が僕の展示を見に来て
“レタリングが良かった”なんて
褒めてくれたことがありますが」
さらりと仕上げられた
楽しげで、遊び心に満ちた切り絵。
手先が器用かつ根気強い人にしか
向かない創作形態なのかとも思いますが・・・。
「いや、切り絵は簡単ですよ。
それはもう、後始末も楽だしね。
(図案さえ決まれば)あとは
テレビ見ながらでもできるでしょう」
ただし、もちろん難しい部分はあります。
「黒と白のバランスが難しい。
・・・あのね、僕は作品をつくったら
家のテレビの横に作品を置いてね、
繰り返し目に入るようにするんですよ。
そうすると、直さないといけないところに
気づくんです」

(作品の上と下に黒い色が帯状に入っています。この部分は最初白かったということですが、黒を入れるほうが作品が締まることを「テレビの横に置いて」気づかれたそう)
黒と白の配分が魅力的なものになるよう
考えられた福田さんの切り絵。
さらに、作品にはその奥行きをもっと深くする
心配りが施されています。
それは、わずかのことで
黒と白だけの世界に大きな変化を起こす
“さし色使い”の妙。


福田さんの切り絵を見ていると、
“デザイン”とは本当に素敵なものだな、
と思います。
作品にしたい対象を表すための、
重要な線やフォルムが何かを的確につかみ、
少ない要素で、対象をより印象に残るものに
表現する。
ほとんど黒と白だけの切り絵の世界が
こんなにも目を楽しませてくれるのは
“デザイン”の力が持つ、豊かさと遊び心に
ほかならないと感じます。

続いて水彩スケッチ画について。

「もともとは大学から、
管理職になる50代手前まで
ずーっと油絵をやってました。
だけど、歳をとると油絵は準備が大変なんです。
その点、水彩は準備も後かたづけも
楽なんですが、
描くのは難しいですね。
失敗しても直せないし(笑)」
スケッチ旅行をしていると
現地の人と絵をきっかけにして
話すことができるのが楽しみ、と
福田さんは言われます。

(横浜の南京町の様子。同じ図案の切り絵作品もギャラリー内にあります。さがしてみてください)
「歳をとると、気力、体力のエネルギーは
減っていきますが、
それでもたえず何かつくっていたいと
思いますね」
そう言われる福田さん。
ギャラリーに来られるお客様には
自分も何かしてみたいけど、
こんなに上手に出来ないと
言われる方も多いのです、と
お話しすると
「やったらいいと思うんです。
上手下手はないですよ。
自分を表に出すことが大事」
という言葉をくださいました。
「作品をつくる」という行為は
考えてみると、とても面白いものです。
紙を切り抜いたり、線を描いて色をつけたり
するだけで、
様々な人の目や心を喜ばせる何かを
形にすることができてしまいます。
今回、会場で福田さんの作品を
ご覧になったあとは、思いがけず
「何かをつくりたくなる気持ち」
が芽ばえるのを感じられるかもしれません。

(5月24日(火)・31日(火・)6月3日(金)は休館日です)
2016年04月10日
【開催中】薮田和義 スケッチ画展
みなさん、こんにちは!
桜の季節もそろそろ終盤になってきましたね。
この時期になると、ほんの1~2日見ないうちに
ピンクの花びら一色の姿から
葉桜に変化している桜も増えてきます。
その有無を言わせぬ変化のスピードを
人間である私たちはただ受けいれるしか
ないんだなあ・・・と、思ったりもします。
しかし品種によってはまだまだ楽しめる桜も。
あともう少し、日本ならではの春の喜びを
満喫しましょう!
さて、美術ギャラリーで
新しい展覧会がはじまりました。
薮田和義 水彩スケッチ展
~湖国滋賀の心に響く
里山風景を求めて
晴描雨眠のスケッチ紀行~
4月7日(木)~4月24日(日)

千葉県市川市生まれ、現在大津市在住の
薮田和義さんによる、
滋賀県下の風景を描いた水彩スケッチ展です。
薮田さんのお写真はこちら。

2000年に退職されてから、
ずっと好きだった絵を描く毎日を
過ごしているという薮田さん。
滋賀県の風景を描くことにこだわって
車で県内中をめぐり、
細い道しかない場所に入るときは
その車から自転車を取り出して、
描きたい景色を探しにゆかれるそうです。
そのフットワークのように軽やかで自在な線と、
場所のもつ空気感を的確にとらえた色づかいで
描かれたスケッチ画について、
薮田さんにお話を伺いました。
(薮田さん)「僕はね、名所旧跡は描かないんです」
お話の最初に、薮田さんはまずそうおっしゃいました。
「これはね、蒲生(旧蒲生町 現東近江市)岡本の
ガリ版伝承館の裏にあるんだけど」

―ガリ版伝承館も風情のある建物ですが、“裏”ですか。
「うん、“裏”のほうがいいんだよ。
この建物はもうなくなっちゃったんだね。
こういうもの、いいんだけどね・・・。
残っていかないかなと思うんだけど」
これも同じ、蒲生岡本の景色。

「こっち側にあるこのかやぶき、
これも今はないんだよ。
この絵は2003年に描いたんだけど
この間行ったらなかったんだ」

(絵の左上にかやぶき屋根がほんの少し、頭をのぞかせています)
今回展示していただいたスケッチ画には
全て、薮田さんがその風景と出会ったいきさつと
風景から何を感じたかを
300~400字程度のエッセイ風にまとめた
キャプションが添えられています。
この蒲生岡本の絵のキャプションでは
かやぶき屋根のなくなった現在の景色は
薮田さんにとっては
“わさび抜きのにぎりずしのよう”と
書かれてあります。
ユーモアを含みながらも、
無くなってしまったものを惜しむ気持ちや、
寂しさが伝わってくる表現です。
名所旧跡というものを描かない薮田さんが
車と自転車を駆使して捜し求める場所とは
表立って紹介されることのない
無名の景色でありながら
人の心の中にさりげなくも忘れがたい
「絵」として刻まれる場所。
ところが、そんな「絵になる」場所は
近年、急激な変化を遂げているのだと
薮田さんは感じていらっしゃるのです。

「これは上仰木の棚田だね。
珍しく全部(稲で)埋まっていると思って
描いたんだよ」
―仰木の棚田も空いているところがあるのですか。
「そう。ところどころ、ちょうど
シャッター商店街みたいに。
やはり田んぼが空いてしまっていると
絵に描くのはね・・・。」

「ここはマキノの奥にある在原っていう場所。
かやぶきの家にまだ普通に人が住んでいるっていう
貴重な場所なんだね。
ただ、人は減っている。
雪が深いから、人の住んでいない家は
そのうち崩れてしまうしかない」
いわゆる「近代化」「都市化」の大きな波が
押し寄せる場所からわずかに外にあったことで
以前からの生活のかたちが残されてきた土地に、
いま、本格的な危機が訪れていることを
薮田さんはスケッチの旅で目の当たりに
されています。
そして、その危機をとりまく、
この時代独特の空気感がどんなものであるか
絵を描く人ならではのこんな言葉で表現されます。
「今は“調和”を大事にしないね」
薮田さんの心に焦点を結ぶ
“絵になる”景色とはすなわち、
“そこにあるものが互いに調和している”
様子を感じられる眺めのこと。
その調和は何によって支えられていると
薮田さんは考えているのでしょうか。
「外国の人に訊くと、
昔の日本の農村風景のことを
“こんなに美しいものはない”と言うんです。
自然と人間が共存していることが美しいと。
それが破られたのは・・・戦後の復興で
生きるのに精一杯だったことも
あるのかもしれないけど・・・。
僕の子どもの頃なんかは、地域住民の
密着度が高かったね。
昔は晴れた日に畳を干して、
竹でたたいてほこりを払うんだけど
それは近所中みんなで決めて同じ日に
やったんだよ」

「あと、子どもの頃は僕らは
“家の中にいたらだめ。外で遊びなさい”
と言われていたね。
だから、道が遊び場だった。
そうやっていたから、自然と
自分の住んでいるところに愛着を
持っていたというかね。
もちろん、日本の昔の村の親密さには
村八分みたいなものも生んでしまう
ネガティブな側面もあったわけだけど」
「自然との共存」は、今では私たちにとって
とても難しい課題となってしまいました。
しかし、そう遠くない過去には
その「共存」の重みを背負いながら
当たり前に日常が営まれていたのです。
手間や労力を必要とする暮らしを
底から支えていたのは
薮田さんの言われる、幼い頃から育まれた
“自分の住んでいるところへの愛着”であり、
周りの景色を日々感じることで生まれる
“自分たちは全体の中の一部である”という
語らずとも共有できた世界観だったのかも
しれません。
現代の40歳代以下の世代では
土地の材料を使わなくても建てられる
工業化住宅が建ちならび、
人の住む家や店舗やビルは
持ち主の事情や必要性、あるいは
好みに沿って外観が作られているが、
周囲の自然や、街並みとのバランスからは
ばらばらに孤立している感じがするのが
子どもの頃から見てきた景色・・・という人が
大半を占めるのではないでしょうか。
それは一概に否定されるべきものではなく
やはり皆が幸福な暮らしを築くため努力して
作り上げてきた景色には違いないのですが、
それでも薮田さんの言われる
「調和」という言葉には、
様々なことを考えさせる重みがあります。

日本は変な国ですよ、一方では休耕田が多く
一方では食料自給率がこんなに低い。
でもね、やはり子どもの頃から考える
というような方向にしていかないとね、
そう言われたあと、薮田さんは続けて
「自分たちのいるところを住みよい場所にして
周りに住む人と仲良くして、
愛着をもつということ、
これが大事なことなんだと思う」
と添えられました。
“あなたの育ってきた場所の絵を描いて”と
誰かに頼まれることがあったとしたら
自分はどんな絵を描くのだろう?
会場に展示された薮田さんの作品を見ながら
時折考えてしまいます。
今はもうこの通りではない景色。
もうじきなくなるかもしれない景色。
知らない場所なのに、
どこか知っている気がする景色・・・。
薮田さんが描いた様々な実在の「景色」に
ぜひ会場で出会っていただき、
自由に思いを巡らせてみてください。

(今回の展示のために、日野町の風景も数点スケッチしてくださいました。これは仁本木地区のとある場所とのこと)
(4月12日(火)・19日(火)は休館日です)

桜の季節もそろそろ終盤になってきましたね。
この時期になると、ほんの1~2日見ないうちに
ピンクの花びら一色の姿から
葉桜に変化している桜も増えてきます。
その有無を言わせぬ変化のスピードを
人間である私たちはただ受けいれるしか
ないんだなあ・・・と、思ったりもします。
しかし品種によってはまだまだ楽しめる桜も。
あともう少し、日本ならではの春の喜びを
満喫しましょう!
さて、美術ギャラリーで
新しい展覧会がはじまりました。
薮田和義 水彩スケッチ展
~湖国滋賀の心に響く
里山風景を求めて
晴描雨眠のスケッチ紀行~
4月7日(木)~4月24日(日)

千葉県市川市生まれ、現在大津市在住の
薮田和義さんによる、
滋賀県下の風景を描いた水彩スケッチ展です。
薮田さんのお写真はこちら。

2000年に退職されてから、
ずっと好きだった絵を描く毎日を
過ごしているという薮田さん。
滋賀県の風景を描くことにこだわって
車で県内中をめぐり、
細い道しかない場所に入るときは
その車から自転車を取り出して、
描きたい景色を探しにゆかれるそうです。
そのフットワークのように軽やかで自在な線と、
場所のもつ空気感を的確にとらえた色づかいで
描かれたスケッチ画について、
薮田さんにお話を伺いました。
(薮田さん)「僕はね、名所旧跡は描かないんです」
お話の最初に、薮田さんはまずそうおっしゃいました。
「これはね、蒲生(旧蒲生町 現東近江市)岡本の
ガリ版伝承館の裏にあるんだけど」

―ガリ版伝承館も風情のある建物ですが、“裏”ですか。
「うん、“裏”のほうがいいんだよ。
この建物はもうなくなっちゃったんだね。
こういうもの、いいんだけどね・・・。
残っていかないかなと思うんだけど」
これも同じ、蒲生岡本の景色。

「こっち側にあるこのかやぶき、
これも今はないんだよ。
この絵は2003年に描いたんだけど
この間行ったらなかったんだ」

(絵の左上にかやぶき屋根がほんの少し、頭をのぞかせています)
今回展示していただいたスケッチ画には
全て、薮田さんがその風景と出会ったいきさつと
風景から何を感じたかを
300~400字程度のエッセイ風にまとめた
キャプションが添えられています。
この蒲生岡本の絵のキャプションでは
かやぶき屋根のなくなった現在の景色は
薮田さんにとっては
“わさび抜きのにぎりずしのよう”と
書かれてあります。
ユーモアを含みながらも、
無くなってしまったものを惜しむ気持ちや、
寂しさが伝わってくる表現です。
名所旧跡というものを描かない薮田さんが
車と自転車を駆使して捜し求める場所とは
表立って紹介されることのない
無名の景色でありながら
人の心の中にさりげなくも忘れがたい
「絵」として刻まれる場所。
ところが、そんな「絵になる」場所は
近年、急激な変化を遂げているのだと
薮田さんは感じていらっしゃるのです。

「これは上仰木の棚田だね。
珍しく全部(稲で)埋まっていると思って
描いたんだよ」
―仰木の棚田も空いているところがあるのですか。
「そう。ところどころ、ちょうど
シャッター商店街みたいに。
やはり田んぼが空いてしまっていると
絵に描くのはね・・・。」

「ここはマキノの奥にある在原っていう場所。
かやぶきの家にまだ普通に人が住んでいるっていう
貴重な場所なんだね。
ただ、人は減っている。
雪が深いから、人の住んでいない家は
そのうち崩れてしまうしかない」
いわゆる「近代化」「都市化」の大きな波が
押し寄せる場所からわずかに外にあったことで
以前からの生活のかたちが残されてきた土地に、
いま、本格的な危機が訪れていることを
薮田さんはスケッチの旅で目の当たりに
されています。
そして、その危機をとりまく、
この時代独特の空気感がどんなものであるか
絵を描く人ならではのこんな言葉で表現されます。
「今は“調和”を大事にしないね」
薮田さんの心に焦点を結ぶ
“絵になる”景色とはすなわち、
“そこにあるものが互いに調和している”
様子を感じられる眺めのこと。
その調和は何によって支えられていると
薮田さんは考えているのでしょうか。
「外国の人に訊くと、
昔の日本の農村風景のことを
“こんなに美しいものはない”と言うんです。
自然と人間が共存していることが美しいと。
それが破られたのは・・・戦後の復興で
生きるのに精一杯だったことも
あるのかもしれないけど・・・。
僕の子どもの頃なんかは、地域住民の
密着度が高かったね。
昔は晴れた日に畳を干して、
竹でたたいてほこりを払うんだけど
それは近所中みんなで決めて同じ日に
やったんだよ」

「あと、子どもの頃は僕らは
“家の中にいたらだめ。外で遊びなさい”
と言われていたね。
だから、道が遊び場だった。
そうやっていたから、自然と
自分の住んでいるところに愛着を
持っていたというかね。
もちろん、日本の昔の村の親密さには
村八分みたいなものも生んでしまう
ネガティブな側面もあったわけだけど」
「自然との共存」は、今では私たちにとって
とても難しい課題となってしまいました。
しかし、そう遠くない過去には
その「共存」の重みを背負いながら
当たり前に日常が営まれていたのです。
手間や労力を必要とする暮らしを
底から支えていたのは
薮田さんの言われる、幼い頃から育まれた
“自分の住んでいるところへの愛着”であり、
周りの景色を日々感じることで生まれる
“自分たちは全体の中の一部である”という
語らずとも共有できた世界観だったのかも
しれません。
現代の40歳代以下の世代では
土地の材料を使わなくても建てられる
工業化住宅が建ちならび、
人の住む家や店舗やビルは
持ち主の事情や必要性、あるいは
好みに沿って外観が作られているが、
周囲の自然や、街並みとのバランスからは
ばらばらに孤立している感じがするのが
子どもの頃から見てきた景色・・・という人が
大半を占めるのではないでしょうか。
それは一概に否定されるべきものではなく
やはり皆が幸福な暮らしを築くため努力して
作り上げてきた景色には違いないのですが、
それでも薮田さんの言われる
「調和」という言葉には、
様々なことを考えさせる重みがあります。

日本は変な国ですよ、一方では休耕田が多く
一方では食料自給率がこんなに低い。
でもね、やはり子どもの頃から考える
というような方向にしていかないとね、
そう言われたあと、薮田さんは続けて
「自分たちのいるところを住みよい場所にして
周りに住む人と仲良くして、
愛着をもつということ、
これが大事なことなんだと思う」
と添えられました。
“あなたの育ってきた場所の絵を描いて”と
誰かに頼まれることがあったとしたら
自分はどんな絵を描くのだろう?
会場に展示された薮田さんの作品を見ながら
時折考えてしまいます。
今はもうこの通りではない景色。
もうじきなくなるかもしれない景色。
知らない場所なのに、
どこか知っている気がする景色・・・。
薮田さんが描いた様々な実在の「景色」に
ぜひ会場で出会っていただき、
自由に思いを巡らせてみてください。

(今回の展示のために、日野町の風景も数点スケッチしてくださいました。これは仁本木地区のとある場所とのこと)
(4月12日(火)・19日(火)は休館日です)
2016年03月19日
【開催中】近藤やよい 絵画展
みなさん、こんにちは。
冬のコートはもうしまっていいのか、
いや、思いきって片付けてしまい、
多少の寒の戻りは気合で乗りきるか…。
その決断を今日にも迫られているような
この頃です。
もう春が来ましたね。
わたむきホール虹の美術ギャラリーでは
この季節にふさわしい、
華やかな絵画展がスタートしました。
近藤やよい 絵画展
~色彩でありのままの感動を
描くことへの追求~
3月17日(木)~4月3日(日)

湖南市に拠点を置き、
絵画教室の講師として活動されている
近藤やよいさんの絵画展です。
近藤さんのお写真はこちらです。

今回は、当美術ギャラリーの
展示としては大変数の多い、
36点もの作品が
贅沢に壁面を彩っています。

まず最初に近藤さんの作品を見て驚くのは、
その技術の高さ。

写真ではありません。
これは近藤さんの筆による油絵です。

こちらはパステルで描きあげた作品。
パステルというひとつの画材のみで
人形の髪、肌、ドレスの生地、背景の
それぞれの質感を
見事に描き分けておられます。
何を聞いても
必ず朗らかな笑い声とともに
答えてくださる近藤さん。
作品が配置されたばかりの
ギャラリーを巡りながら
お話を伺いました。
絵を描くとき、
「なるだけ素直に描くことを心がけている」
と仰る近藤さんの画風は写実的で明快。
油絵でも、細部に見入ってしまうほど
細かく描きこまれている作品が多く、
気づくとひとつの絵を長い時間
眺めてしまっています。
(近藤さん)「もともと肖像画がメインなんです。
人物は得意ですね。
といっても注文を受けて描くので、
手元に残っているのは、
自分の家族を描いた作品ばかりです」

(娘さんを描いた作品。人物を描くときは“柔らかい雰囲気になるよう心がける”そうです。)
-美しいですね…。
そして、じっと見ていると
3Dのように浮きあがってくる感じが(笑)
「人の肖像の仕事をしていて、
夜中にふとその絵を見るとね、
思わずこう(絵を伏せたく)なることも(笑)
でも人の形をしたものが魅力的なんです」
会場には小型犬や猫など
愛らしい動物を描いた絵も数点
展示されていますが、
心がけておられるのは
“絵の動物と見る人の目が
合わないようにすること”。

「目は合わさないようにしますよね。
見る人のことを考えてというか…。
でも、画家としてはもっとリアルで
ぎょっとするぐらいのものを
描きたいと思う気持ちがありますよ。
もう、しびれるぐらいのものを」
でも、描いていると、
見る人のことを考えてバランスをとる気持ちが
働くのだと近藤さんは言われます。
現実にかぎりなく近いものを作る作業とは、
受け手に対する独特の配慮を
どこかで必要とするものなのでしょうか。
近藤さんの筆がキャンバスに再現する世界。
風景画も圧巻です。
「これは水彩(ガッシュ)で、
日本庭園を描きました」

「半夏生の花が白くてきれいで
これを手前に持ってきて、
後ろに庭園があってね。
でも、すみずみまで描きすぎて…。
描きこみすぎず、周りをぼかすとか、
そういうやり方もあるので、
これはちょっとやりすぎたかなって(笑)」

(半夏生の花が一本一本、茎の節の部分や葉の質感まで描かれています。)
-いや、非常に魅力的な絵だと思います。
写実的な風景画で、
何も変ったものが描かれていないのに
なぜかずっと見ていても飽きません。
アメリカの、ワイエスという画家の絵を
思い出しました。
「ワイエス、ああ、不思議な感じの
とても素敵な絵ですね…。
“ずっと見ていても飽きない”
と言ってもらえるのは一番嬉しいですよ」

こちらはヨーロッパの街並。
近藤さんの描かれるヨーロッパの街は
子どものころに憧れた
絵本やアニメの中のヨーロッパを
彷彿とさせます。
-子どものころ、絵本やアニメに描かれた
こういう街並みを見て
人の手で描かれたものだということが
信じられませんでした。
「そうですね、ジブリのアニメの絵なんて
本当にすごいですよね。背景の風景画とか・・・。
この絵は、でも、鉛筆の下描きなしで
描いているんですよ。絵が汚れちゃうから。
自分の絵の生徒さんにもそうしてもらっています。
下描きなしでみんな描いてますよ(笑)」

(下描きなし、だそうです。)
近藤さんは、どんなに細かい筆づかいの
絵を前にしても
「簡単ですよ」「難しくない」
と言われます。
絵を描くのが苦手なホールスタッフが
「人の顔って難しいですよね」と言うと、
近藤さんは
「顔なんか丸と四角で描けますよ」
と、にこにこしながら仰いました。
いや、私達にはとてもそうは見えません・・・
と思いながらも、
近藤さんにそう言っていただくと、
少しだけ、絵を描くことと自分との距離が
縮まるような気がしました。

近藤さんの作品を見ていると、
子どものころ、自分も周りの友達も
みんな絵を描くのが好きだったことを
思い出します。
人や花や犬や、遠い外国の風景を、
そこにあるかのように紙の上に現せたら、
ちょっとした魔法を使えるような感じが
するのではないか、と。
大人になると、その魔法は「技術」と
呼ばれるようになります。
近藤さんの絵は、誰もがかつて憧れた
あの魔法を感じられるものとして
人を魅了するのかもしれません。
展覧会は4月3日(日)まで。
皆様ぜひご来場ください。

(右側にあるのは、ドイツに実際にあったガス塔。「すごく素敵なんだけど、撤去されてなくなるということだったので、じゃあ絵に描いておかなくちゃ、と」)
(3月22日(火)・23日(水)・29日(火)は
休館日です)
冬のコートはもうしまっていいのか、
いや、思いきって片付けてしまい、
多少の寒の戻りは気合で乗りきるか…。
その決断を今日にも迫られているような
この頃です。
もう春が来ましたね。
わたむきホール虹の美術ギャラリーでは
この季節にふさわしい、
華やかな絵画展がスタートしました。
近藤やよい 絵画展
~色彩でありのままの感動を
描くことへの追求~
3月17日(木)~4月3日(日)

湖南市に拠点を置き、
絵画教室の講師として活動されている
近藤やよいさんの絵画展です。
近藤さんのお写真はこちらです。

今回は、当美術ギャラリーの
展示としては大変数の多い、
36点もの作品が
贅沢に壁面を彩っています。

まず最初に近藤さんの作品を見て驚くのは、
その技術の高さ。

写真ではありません。
これは近藤さんの筆による油絵です。

こちらはパステルで描きあげた作品。
パステルというひとつの画材のみで
人形の髪、肌、ドレスの生地、背景の
それぞれの質感を
見事に描き分けておられます。
何を聞いても
必ず朗らかな笑い声とともに
答えてくださる近藤さん。
作品が配置されたばかりの
ギャラリーを巡りながら
お話を伺いました。
絵を描くとき、
「なるだけ素直に描くことを心がけている」
と仰る近藤さんの画風は写実的で明快。
油絵でも、細部に見入ってしまうほど
細かく描きこまれている作品が多く、
気づくとひとつの絵を長い時間
眺めてしまっています。
(近藤さん)「もともと肖像画がメインなんです。
人物は得意ですね。
といっても注文を受けて描くので、
手元に残っているのは、
自分の家族を描いた作品ばかりです」

(娘さんを描いた作品。人物を描くときは“柔らかい雰囲気になるよう心がける”そうです。)
-美しいですね…。
そして、じっと見ていると
3Dのように浮きあがってくる感じが(笑)
「人の肖像の仕事をしていて、
夜中にふとその絵を見るとね、
思わずこう(絵を伏せたく)なることも(笑)
でも人の形をしたものが魅力的なんです」
会場には小型犬や猫など
愛らしい動物を描いた絵も数点
展示されていますが、
心がけておられるのは
“絵の動物と見る人の目が
合わないようにすること”。

「目は合わさないようにしますよね。
見る人のことを考えてというか…。
でも、画家としてはもっとリアルで
ぎょっとするぐらいのものを
描きたいと思う気持ちがありますよ。
もう、しびれるぐらいのものを」
でも、描いていると、
見る人のことを考えてバランスをとる気持ちが
働くのだと近藤さんは言われます。
現実にかぎりなく近いものを作る作業とは、
受け手に対する独特の配慮を
どこかで必要とするものなのでしょうか。
近藤さんの筆がキャンバスに再現する世界。
風景画も圧巻です。
「これは水彩(ガッシュ)で、
日本庭園を描きました」

「半夏生の花が白くてきれいで
これを手前に持ってきて、
後ろに庭園があってね。
でも、すみずみまで描きすぎて…。
描きこみすぎず、周りをぼかすとか、
そういうやり方もあるので、
これはちょっとやりすぎたかなって(笑)」

(半夏生の花が一本一本、茎の節の部分や葉の質感まで描かれています。)
-いや、非常に魅力的な絵だと思います。
写実的な風景画で、
何も変ったものが描かれていないのに
なぜかずっと見ていても飽きません。
アメリカの、ワイエスという画家の絵を
思い出しました。
「ワイエス、ああ、不思議な感じの
とても素敵な絵ですね…。
“ずっと見ていても飽きない”
と言ってもらえるのは一番嬉しいですよ」

こちらはヨーロッパの街並。
近藤さんの描かれるヨーロッパの街は
子どものころに憧れた
絵本やアニメの中のヨーロッパを
彷彿とさせます。
-子どものころ、絵本やアニメに描かれた
こういう街並みを見て
人の手で描かれたものだということが
信じられませんでした。
「そうですね、ジブリのアニメの絵なんて
本当にすごいですよね。背景の風景画とか・・・。
この絵は、でも、鉛筆の下描きなしで
描いているんですよ。絵が汚れちゃうから。
自分の絵の生徒さんにもそうしてもらっています。
下描きなしでみんな描いてますよ(笑)」

(下描きなし、だそうです。)
近藤さんは、どんなに細かい筆づかいの
絵を前にしても
「簡単ですよ」「難しくない」
と言われます。
絵を描くのが苦手なホールスタッフが
「人の顔って難しいですよね」と言うと、
近藤さんは
「顔なんか丸と四角で描けますよ」
と、にこにこしながら仰いました。
いや、私達にはとてもそうは見えません・・・
と思いながらも、
近藤さんにそう言っていただくと、
少しだけ、絵を描くことと自分との距離が
縮まるような気がしました。

近藤さんの作品を見ていると、
子どものころ、自分も周りの友達も
みんな絵を描くのが好きだったことを
思い出します。
人や花や犬や、遠い外国の風景を、
そこにあるかのように紙の上に現せたら、
ちょっとした魔法を使えるような感じが
するのではないか、と。
大人になると、その魔法は「技術」と
呼ばれるようになります。
近藤さんの絵は、誰もがかつて憧れた
あの魔法を感じられるものとして
人を魅了するのかもしれません。
展覧会は4月3日(日)まで。
皆様ぜひご来場ください。

(右側にあるのは、ドイツに実際にあったガス塔。「すごく素敵なんだけど、撤去されてなくなるということだったので、じゃあ絵に描いておかなくちゃ、と」)
(3月22日(火)・23日(水)・29日(火)は
休館日です)