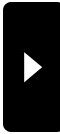2015年01月18日
【開催中】ミゲル・リマ 絵画展
みなさん、こんにちは! 毎日寒いですね~。
毎日寒いですね~。
朝起きると外が銀世界ということもしばしば。
今年の冬は暖冬という予報だったんじゃ・・・?
そしてインフルエンザが本格的に流行中とのこと。
みなさん温かくて美味しいものをたっぷり食べて
ウイルスを撃退しましょうね!
さて、わたむきホール虹の美術ギャラリーは今
鮮やかなアンデスの色彩に彩られています。
南米ボリビア出身で、先住民族「アイマラ族」の
血を引くアーティスト、そして教育家でもある
ミゲル・リマさんの絵画展が開催中なのです。
ミゲル・リマ絵画展
~チチカカ湖の色彩~
1月16日(金)~2月1日(日)

リマさんは2013年に初めて日本の土を踏み
2014年にあらためて来日、
現在、日野町で暮らされています。

日野町ではすっかり有名人のリマさん。
日本語は勉強中とのことですが、穏やかな人柄と、
奥様の浦田広美さんの通訳で自然に地域に溶け込み
様々なイベントや催しに引っ張りだこの日々を
送っていらっしゃいます。
そんなリマさんが昨年から描き始めたのが
自らのルーツ、アイマラ族の暮らしや神話を描いた
色鮮やかな色鉛筆画。
神秘的で愛らしい、不思議な魅力を持つリマさんの絵は
今、静かに様々な人の心をとらえています。
また今回は絵の他に、アイマラ文化を伝えるいくつかの
ものを同時に出展していただきました。
今回の展示について、リマさんと浦田さんに伺ったお話
をお楽しみ下さい!
会場に入ると、
最初にどうしても目についてしまうものが…。
動物の頭のよう。かなりのインパクトです。

(浦田さん)「アンデスの神話の動物のお面です。
アンデスの神話を伝えるため、日本で劇をした時に
作ったものです。
風船を膨らませ、新聞紙やキッチンペーパーを上に
貼って、乾いたら風船を取り除きます。
スペイン語ではパペルマシェ(Papelmashe)といいます」

(神話のタイトルは「キツネと娘」…昔あるところに娘がいた。娘は鳥の王様コンドルに求婚されたが、「他にもっといい人がいるかもしれない」と断る。様々な求婚者を断り続けた娘はついに自分を幸せにしてくれそうなキツネと結婚するが、キツネは嘘つきで、だまされて大変に苦労の多い人生を送った…というお話)
(浦田さん)「またこれは、チチカカ湖の神話を紹介した
いということで、ミゲルがひらがなで字を書きました」

(神話はチチカカ湖の名前の由来にまつわるもの。「チチカカ」とはそういう意味だったのかとびっくりする内容です)
様々な神話が遍在する南米の大地。
そこに暮らす人々の世界には、神話と同様に
豊かな「色」が溢れているようです。
―やはり、違う国に育ってきた方の色使いですね。
日本人は鮮やかな色をたくさん組み合わせると
いうことがないので…。
どうしてもどこかに中間色が入ってしまいます。
(リマさん)「ああ、そうですね。日本人の作家の絵を見る
と、とても感覚が繊細だということを感じます」
(浦田さん)「向こうの人は、(周りの目を気にするよりも)
“自分がこの色を好きだから”という理由で色を選ん
で組み合わせるんですね。
ボリビアでは人々がよく織物をやるんですが、
とにかく色を使うのが楽しいようです。
特に最近は化学染料が使えるようになり、
糸が簡単に染められるのでより楽しいみたいです」

(展示物である南米の楽器の下に敷かれているのもボリビアの織物です。鮮やかな水色、モスグリーンにピンク…。日本人には大胆な色の配列ですが、派手でトゥーマッチな印象は受けないのが不思議。)
さて、話題はいよいよ絵に移っていきます。
リマさんの絵は、古くから民族に伝承される図案・絵柄と
リマさんが考えたオリジナルの絵のミックスだそうです。
下のキャプションは絵の中の神話の場面や、アイマラの
人々の生活や儀式の場面を説明しており、
これも伝承されている話を
リマさんの言葉で語りなおしています。
(浦田さん)「たとえば絵の中にいるコンドルは
ナスカの地上絵でも見られる古い図案です。
星(十字架のように見えるもの)も古い図案ですね。
同時に、絵にいろいろな遊び心もこめていて、
よく見ると絵の中にいろいろな動物が隠れているんです」

(髪の毛?の先が鳥のくちばしのよう。他にもたくさんの絵にいろんな動物が隠れています。探してみてください!)
(浦田さん)「あらゆる場所に動物が遍在するというのは、アイマラの人独特の世界観かなと私は思っているのですが」
(リマさん)「自分の描く山には精霊が宿っています。」

(山にも動物。わかりますか?単に動物が暮らすだけではなく精霊も宿っているという意味で、パズルのピースのように動物を描きこまれているのでしょうか)
ここまでずっとお二人のお話を伺ってきて、
ひとつの疑問が浮かびました。
自然と暮らし何千年もかけて培ってきた美しい世界観と
独特の生活様式を持つアンデスの人々。
しかし美しくてもそれはあくまで
「あたりまえの日常」のはずです。
地球半周分も離れた地の外国人=私達日本人に
「自分たちの文化」を伝えようとされる理由は
いったい何なのでしょうか?
(浦田さん)「あたりまえ?うーん…。」
―“あたりまえ”ではないのですか?
「ここに描かれている絵は確かにアイマラの原風景です。
しかしミゲルはここで育ったわけではないんです。
彼はもちろんアイマラ族ですが、彼のお父さんも、おじいさんも、町に出て生活をしていました。ミゲルは町で育ったんですね。
そして大きくなってから、自分のルーツを知りたくて
アイマラ族の住む場所に通ったんです」

「もちろん子どもの頃から楽器を演奏するなど
お家にアイマラとしての習慣はあったので、
彼にはアイマラ族のアイデンティティがあるんです。
でもアイマラ族のいろいろな人の話を聞いたり、
アイマラの音楽を勉強したりしたのは
日本にアイマラ文化を紹介するのがきっかけでした。
彼はずっと音楽をやっていましたが、
前は外国の音楽に興味を持っていて、
自分のルーツとなる音楽をやりだしたのは
最近のことなんです。」
―リマさんは30代後半でいらっしゃいますね。
生まれ育った背景は全く違いますが、
同世代として、その感覚がよくわかる気がします。
自分たちの世代から、日本でも昔から受け継がれて
きたものが、ぷつんと途切れてしまっている感じが
あるのです。
(浦田さん)「そうですね。同じだと思います。
今回はアイマラに伝わる楽器も展示していますが、
この楽器を使った音楽も、若い世代に受け継がれる
ことが少なくなり、演奏できるのは高齢の人たち
ばかりになっていますので、
世代的に危機感を感じていると思います」

日本で問題になっていることが、遠いアンデスの地でも
同様に問題であることに驚くとともに、
それぞれの世代で感じることは、国境を越えてどこか
通じる部分があるのかもしれないと思いました。
最後に、リマさんより来場される皆様へ向けて
メッセージをいただきました。
「絵を通してアイマラの文化を知ってほしいです。
また、描いている風景を見てほしいと思います」
厳しい高地で、何千年もかけて織物を織るように
作られてきた暮らしの形。
そこには、目に見えない神々や音楽も、目に見える
ものと変わることなく等しく織り込まれています。
人が自然と生きることでしか生まれることのない
豊かさの形を、ぜひ会場でご覧になってください。

(1月20日(火)・1月27日(火)は休館日です)
 毎日寒いですね~。
毎日寒いですね~。朝起きると外が銀世界ということもしばしば。
今年の冬は暖冬という予報だったんじゃ・・・?
そしてインフルエンザが本格的に流行中とのこと。
みなさん温かくて美味しいものをたっぷり食べて
ウイルスを撃退しましょうね!
さて、わたむきホール虹の美術ギャラリーは今
鮮やかなアンデスの色彩に彩られています。
南米ボリビア出身で、先住民族「アイマラ族」の
血を引くアーティスト、そして教育家でもある
ミゲル・リマさんの絵画展が開催中なのです。
ミゲル・リマ絵画展
~チチカカ湖の色彩~
1月16日(金)~2月1日(日)

リマさんは2013年に初めて日本の土を踏み
2014年にあらためて来日、
現在、日野町で暮らされています。

日野町ではすっかり有名人のリマさん。
日本語は勉強中とのことですが、穏やかな人柄と、
奥様の浦田広美さんの通訳で自然に地域に溶け込み
様々なイベントや催しに引っ張りだこの日々を
送っていらっしゃいます。
そんなリマさんが昨年から描き始めたのが
自らのルーツ、アイマラ族の暮らしや神話を描いた
色鮮やかな色鉛筆画。
神秘的で愛らしい、不思議な魅力を持つリマさんの絵は
今、静かに様々な人の心をとらえています。
また今回は絵の他に、アイマラ文化を伝えるいくつかの
ものを同時に出展していただきました。
今回の展示について、リマさんと浦田さんに伺ったお話
をお楽しみ下さい!
会場に入ると、
最初にどうしても目についてしまうものが…。
動物の頭のよう。かなりのインパクトです。

(浦田さん)「アンデスの神話の動物のお面です。
アンデスの神話を伝えるため、日本で劇をした時に
作ったものです。
風船を膨らませ、新聞紙やキッチンペーパーを上に
貼って、乾いたら風船を取り除きます。
スペイン語ではパペルマシェ(Papelmashe)といいます」

(神話のタイトルは「キツネと娘」…昔あるところに娘がいた。娘は鳥の王様コンドルに求婚されたが、「他にもっといい人がいるかもしれない」と断る。様々な求婚者を断り続けた娘はついに自分を幸せにしてくれそうなキツネと結婚するが、キツネは嘘つきで、だまされて大変に苦労の多い人生を送った…というお話)
(浦田さん)「またこれは、チチカカ湖の神話を紹介した
いということで、ミゲルがひらがなで字を書きました」

(神話はチチカカ湖の名前の由来にまつわるもの。「チチカカ」とはそういう意味だったのかとびっくりする内容です)
様々な神話が遍在する南米の大地。
そこに暮らす人々の世界には、神話と同様に
豊かな「色」が溢れているようです。
―やはり、違う国に育ってきた方の色使いですね。
日本人は鮮やかな色をたくさん組み合わせると
いうことがないので…。
どうしてもどこかに中間色が入ってしまいます。
(リマさん)「ああ、そうですね。日本人の作家の絵を見る
と、とても感覚が繊細だということを感じます」
(浦田さん)「向こうの人は、(周りの目を気にするよりも)
“自分がこの色を好きだから”という理由で色を選ん
で組み合わせるんですね。
ボリビアでは人々がよく織物をやるんですが、
とにかく色を使うのが楽しいようです。
特に最近は化学染料が使えるようになり、
糸が簡単に染められるのでより楽しいみたいです」

(展示物である南米の楽器の下に敷かれているのもボリビアの織物です。鮮やかな水色、モスグリーンにピンク…。日本人には大胆な色の配列ですが、派手でトゥーマッチな印象は受けないのが不思議。)
さて、話題はいよいよ絵に移っていきます。
リマさんの絵は、古くから民族に伝承される図案・絵柄と
リマさんが考えたオリジナルの絵のミックスだそうです。
下のキャプションは絵の中の神話の場面や、アイマラの
人々の生活や儀式の場面を説明しており、
これも伝承されている話を
リマさんの言葉で語りなおしています。
(浦田さん)「たとえば絵の中にいるコンドルは
ナスカの地上絵でも見られる古い図案です。
星(十字架のように見えるもの)も古い図案ですね。
同時に、絵にいろいろな遊び心もこめていて、
よく見ると絵の中にいろいろな動物が隠れているんです」

(髪の毛?の先が鳥のくちばしのよう。他にもたくさんの絵にいろんな動物が隠れています。探してみてください!)
(浦田さん)「あらゆる場所に動物が遍在するというのは、アイマラの人独特の世界観かなと私は思っているのですが」
(リマさん)「自分の描く山には精霊が宿っています。」

(山にも動物。わかりますか?単に動物が暮らすだけではなく精霊も宿っているという意味で、パズルのピースのように動物を描きこまれているのでしょうか)
ここまでずっとお二人のお話を伺ってきて、
ひとつの疑問が浮かびました。
自然と暮らし何千年もかけて培ってきた美しい世界観と
独特の生活様式を持つアンデスの人々。
しかし美しくてもそれはあくまで
「あたりまえの日常」のはずです。
地球半周分も離れた地の外国人=私達日本人に
「自分たちの文化」を伝えようとされる理由は
いったい何なのでしょうか?
(浦田さん)「あたりまえ?うーん…。」
―“あたりまえ”ではないのですか?
「ここに描かれている絵は確かにアイマラの原風景です。
しかしミゲルはここで育ったわけではないんです。
彼はもちろんアイマラ族ですが、彼のお父さんも、おじいさんも、町に出て生活をしていました。ミゲルは町で育ったんですね。
そして大きくなってから、自分のルーツを知りたくて
アイマラ族の住む場所に通ったんです」

「もちろん子どもの頃から楽器を演奏するなど
お家にアイマラとしての習慣はあったので、
彼にはアイマラ族のアイデンティティがあるんです。
でもアイマラ族のいろいろな人の話を聞いたり、
アイマラの音楽を勉強したりしたのは
日本にアイマラ文化を紹介するのがきっかけでした。
彼はずっと音楽をやっていましたが、
前は外国の音楽に興味を持っていて、
自分のルーツとなる音楽をやりだしたのは
最近のことなんです。」
―リマさんは30代後半でいらっしゃいますね。
生まれ育った背景は全く違いますが、
同世代として、その感覚がよくわかる気がします。
自分たちの世代から、日本でも昔から受け継がれて
きたものが、ぷつんと途切れてしまっている感じが
あるのです。
(浦田さん)「そうですね。同じだと思います。
今回はアイマラに伝わる楽器も展示していますが、
この楽器を使った音楽も、若い世代に受け継がれる
ことが少なくなり、演奏できるのは高齢の人たち
ばかりになっていますので、
世代的に危機感を感じていると思います」

日本で問題になっていることが、遠いアンデスの地でも
同様に問題であることに驚くとともに、
それぞれの世代で感じることは、国境を越えてどこか
通じる部分があるのかもしれないと思いました。
最後に、リマさんより来場される皆様へ向けて
メッセージをいただきました。
「絵を通してアイマラの文化を知ってほしいです。
また、描いている風景を見てほしいと思います」
厳しい高地で、何千年もかけて織物を織るように
作られてきた暮らしの形。
そこには、目に見えない神々や音楽も、目に見える
ものと変わることなく等しく織り込まれています。
人が自然と生きることでしか生まれることのない
豊かさの形を、ぜひ会場でご覧になってください。

(1月20日(火)・1月27日(火)は休館日です)
Posted by わたむきホール虹 at 11:35│Comments(0)
│美術ギャラリー