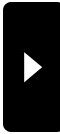2015年08月30日
【開催中】梶本隆三 点描画展
みなさん、こんにちは
いつの間にかもう9月なのですね。
秋が切ないと感じるのは、
ある日ふっと気温と湿度が下がり
虫の声の種類が変わったのを知ることで
時間というものが確実に過ぎていることを
実感させられるからなのでしょうか。
とはいえ、もう少ししたら
食べるものがおいしく
かつ外へのお出かけにぴったりな季節が
巡ってきます。
そのお出かけの前にぜひ
ご覧になっていただきたい展覧会が
美術ギャラリーではじまりました。
梶本 隆三 点描画展
近江から雅な京に憧れ
「軽薄淡小」の世界で誘います。
8月27日(木)
~9月13日(日)

現在守山市を拠点に、
美しい水彩の点描で作品を制作し
多くの方の支持を得ておられる画家
梶本隆三(かじもと たかぞう)さんの
作品展です。
梶本さんのお写真はこちら。

今回会場に並べられた作品を見渡すと
まずはその「小ささ」に惹きつけられます。
すべての絵が、1号から2号程度の大きさに
きっちりと収まって描かれており、
本当にポケットに入れて持ち歩くことが
出来てしまいそうです。
そして、水彩と“市販の水性ペン”を
駆使して描かれる
淡い色づかいの繊細な点描。
絵が小さいということは、
すなわち点のひとつひとつも、
とても小さいのです。
梶本さん「そうなんですよ。
まさに今回の展示のタイトルにある
「軽薄淡小」という言葉なんですけど・・・」
軽くて、薄くて、
淡くて、小さい。
繊細に作られた織物や、
和菓子にあてはまるようなこの形容が、
梶本さんの絵にはぴったりです。

―なぜ、点描で絵を描こうと思われたのですか?
「水彩は15分から20分くらいで
描けてしまうので、
物足りないというか・・・。
もう少しじっくりと描いてみたかったんです。
点描は、点の数で遠近を出すんですね。
あと、ものの大きさも表現できる」

―今回は、滋賀と京都の風景の絵を
展示いただいているということですが
梶本さんのご出身は・・・?
「京都です。実家は二条城の西側にあるんですよ」
京都出身の梶本さんの筆がとらえた
私達のホーム、滋賀の様々な風景。
まずはそこから
お話を聞かせていただくことにします。

「琵琶湖大橋から見た景色ですね。
ピエリ守山、もしくは道の駅の方から
描いたんですよ。
ここ、普通は止まって見られないでしょう?」
―そうですね。車に乗っていますから。
「向こうの方に浮御堂があって、
この先端のところにあるのは木製の灯台ですね。
“出島灯台”っていうんですよね」

(“なかなか止まって見られない”景色。浮御堂と出島灯台が大変かわいらしいです)
かわってこちらは、
その“琵琶湖大橋”が主役の作品。

「琵琶湖大橋の50周年記念の様子です。
この風景、いいでしょう。気球も出て。
なかなかね、後ろに風船があるのに
気づいてもらえないんですけどね」

(色とりどりの無数の風船が、点描で描かれています。手前には気球。気球の下の水面には“えり漁”の網)

(そして橋に敬意を表すように、一斉に水面をすべる船。特別な1日です)
「僕はね、鳥瞰図が好きなんです。
鳥の目線で上から見たような。
絵を描くとき、近くに建物があったら
上がらせてもらうんですよ。
グーグルアースの、
上からの視点で見るやつなんかも
好きですね」
鳥瞰図。鳥の目線。
ここまで作品を見せていただくと
なるほどと思います。
滑空する鳥の目線では
地上のものの多くが
「点」に見えるのでしょうね。
さて、今度は舞台を京都に移します。
この地で生まれ育った梶本さんは
どんな京都の絵を描かれるのでしょうか。

「京都市美術館をね、川の方から見たんです」
―建物の横側ですか。
外から行く私達は普段、
正面からしか見ることがないですね。
「そうですよね。
この時期は川沿いの桜が綺麗なので。
あと、人がこの辺にいる様子も
いいですよね」

(美術館で絵を見ることばかりが頭にあって、建物の横にこんな素敵な光景が広がっていたりすることに気づいていませんでした)

「これは南座なんですけど、
京阪の地下鉄の出口からの
アングルなんです」
―ああー、地下鉄の階段を登ってきた感じ
すごくわかります。
「“都の賑い”って南座の夏の催しで、
夏の南座は冬に比べればお客さんが
少なくなるから、
宮川町と祇園甲部の芸妓さんが
舞台に立つんですよ」

(全ての作品には、日本語のタイトルの下に英語のキャプションがついています。「外国の方に見ていただくことも多く、ひとつひとつ絵の説明をしていたのですが、こうして書いてしまえばわかりやすいのかなと思って」)

(夏の風物詩、鴨川沿いの“等間隔座り”が点描で描きこまれています。京都の夏の夕暮れの、風や湿度までを感じられる作品です)
以前は写真をやっていたという
梶本さん。
“好きな場所を見ていると
構図が見えてくる”と言われます。
そして、
「滋賀でも京都でもできるだけ、
見たらどこかわかるような
“現実の固有名詞を持つところ”を描くように
心がけているんです」
と仰います。
梶本さんの絵にある景色は
私達のよく知る場所でありながら
小さな画面の中に、美しく細やかな
点描で描かれることによって、
現実のその場所よりも淡くて軽い、
“心の中におさめやすい”場所へと
変貌を遂げるようです。
“心の中におさまる”という表現を
別の言葉で言い換えれば
「愛着を持つ」「好きになる」
ということになるのかもしれません。

梶本さんが、今のような形で
制作活動をされるようになるまでには
こんな変遷があったのだそうです。
「少年時代から絵が好きだったんですけれども、
社会人になる前に、
友達が美術コースを選んだんですね。
自分は機械工学を学んで、
IT関係の会社に就職しました」
「定年前に大病をし、生きながらえて、
何かやり残したことはあるかと考え、
絵があるな、と思ったんです。
描くからには楽しく描きたい。
見る人の心が和むような形で、と」
最後に、今回の展示を
見に来てくださる皆様へ
メッセージをいただきました。
「近江の方は、大阪よりもむしろ
京都に憧れを持っておられると
聞きました。
今回の展示ではそういう魅力も
出せたらというのと、
近江の風景と京都の風景を
並べて展示する面白さも
感じていただけたらと思います」

(日野の景色も描いてくださいました)
“京都の方は、梶本さんのお描きに
なった滋賀の風景を見て、どう仰いますか?”
と質問したところ、
「いや、『面白い』『一回行ってみよう』って
言われますよ」
と言われたあと、
「この絵はそういう
“滋賀再発見”みたいなことにも
つながるのかもしれないですね。
実は僕は守山市役所の臨時職員を
やっていまして、
地域の魅力をFacebookで
発信しているんですよ。」
梶本さんの目線がとらえた
守山、滋賀の魅力にご興味のある方は
ぜひ守山市役所のFacebookを
覗いてみてくださいね!
↓↓↓
https://ja-jp.facebook.com/moriyamaprf
そしてもちろん、わたむきホール虹での
展覧会にて梶本さんの絵を通し、
「滋賀と京都」という、私達にもっとも
親しい土地の中に
新しい“私の好きな場所”を
見つけていただければと思います。
(9月1日(火)9日(火)は休館日です)

いつの間にかもう9月なのですね。
秋が切ないと感じるのは、
ある日ふっと気温と湿度が下がり
虫の声の種類が変わったのを知ることで
時間というものが確実に過ぎていることを
実感させられるからなのでしょうか。
とはいえ、もう少ししたら
食べるものがおいしく

かつ外へのお出かけにぴったりな季節が
巡ってきます。
そのお出かけの前にぜひ
ご覧になっていただきたい展覧会が
美術ギャラリーではじまりました。
梶本 隆三 点描画展
近江から雅な京に憧れ
「軽薄淡小」の世界で誘います。
8月27日(木)
~9月13日(日)

現在守山市を拠点に、
美しい水彩の点描で作品を制作し
多くの方の支持を得ておられる画家
梶本隆三(かじもと たかぞう)さんの
作品展です。
梶本さんのお写真はこちら。

今回会場に並べられた作品を見渡すと
まずはその「小ささ」に惹きつけられます。
すべての絵が、1号から2号程度の大きさに
きっちりと収まって描かれており、
本当にポケットに入れて持ち歩くことが
出来てしまいそうです。
そして、水彩と“市販の水性ペン”を
駆使して描かれる
淡い色づかいの繊細な点描。
絵が小さいということは、
すなわち点のひとつひとつも、
とても小さいのです。
梶本さん「そうなんですよ。
まさに今回の展示のタイトルにある
「軽薄淡小」という言葉なんですけど・・・」
軽くて、薄くて、
淡くて、小さい。
繊細に作られた織物や、
和菓子にあてはまるようなこの形容が、
梶本さんの絵にはぴったりです。

―なぜ、点描で絵を描こうと思われたのですか?
「水彩は15分から20分くらいで
描けてしまうので、
物足りないというか・・・。
もう少しじっくりと描いてみたかったんです。
点描は、点の数で遠近を出すんですね。
あと、ものの大きさも表現できる」

―今回は、滋賀と京都の風景の絵を
展示いただいているということですが
梶本さんのご出身は・・・?
「京都です。実家は二条城の西側にあるんですよ」
京都出身の梶本さんの筆がとらえた
私達のホーム、滋賀の様々な風景。
まずはそこから
お話を聞かせていただくことにします。

「琵琶湖大橋から見た景色ですね。
ピエリ守山、もしくは道の駅の方から
描いたんですよ。
ここ、普通は止まって見られないでしょう?」
―そうですね。車に乗っていますから。
「向こうの方に浮御堂があって、
この先端のところにあるのは木製の灯台ですね。
“出島灯台”っていうんですよね」

(“なかなか止まって見られない”景色。浮御堂と出島灯台が大変かわいらしいです)
かわってこちらは、
その“琵琶湖大橋”が主役の作品。

「琵琶湖大橋の50周年記念の様子です。
この風景、いいでしょう。気球も出て。
なかなかね、後ろに風船があるのに
気づいてもらえないんですけどね」

(色とりどりの無数の風船が、点描で描かれています。手前には気球。気球の下の水面には“えり漁”の網)

(そして橋に敬意を表すように、一斉に水面をすべる船。特別な1日です)
「僕はね、鳥瞰図が好きなんです。
鳥の目線で上から見たような。
絵を描くとき、近くに建物があったら
上がらせてもらうんですよ。
グーグルアースの、
上からの視点で見るやつなんかも
好きですね」
鳥瞰図。鳥の目線。
ここまで作品を見せていただくと
なるほどと思います。
滑空する鳥の目線では
地上のものの多くが
「点」に見えるのでしょうね。
さて、今度は舞台を京都に移します。
この地で生まれ育った梶本さんは
どんな京都の絵を描かれるのでしょうか。

「京都市美術館をね、川の方から見たんです」
―建物の横側ですか。
外から行く私達は普段、
正面からしか見ることがないですね。
「そうですよね。
この時期は川沿いの桜が綺麗なので。
あと、人がこの辺にいる様子も
いいですよね」

(美術館で絵を見ることばかりが頭にあって、建物の横にこんな素敵な光景が広がっていたりすることに気づいていませんでした)

「これは南座なんですけど、
京阪の地下鉄の出口からの
アングルなんです」
―ああー、地下鉄の階段を登ってきた感じ
すごくわかります。
「“都の賑い”って南座の夏の催しで、
夏の南座は冬に比べればお客さんが
少なくなるから、
宮川町と祇園甲部の芸妓さんが
舞台に立つんですよ」

(全ての作品には、日本語のタイトルの下に英語のキャプションがついています。「外国の方に見ていただくことも多く、ひとつひとつ絵の説明をしていたのですが、こうして書いてしまえばわかりやすいのかなと思って」)

(夏の風物詩、鴨川沿いの“等間隔座り”が点描で描きこまれています。京都の夏の夕暮れの、風や湿度までを感じられる作品です)
以前は写真をやっていたという
梶本さん。
“好きな場所を見ていると
構図が見えてくる”と言われます。
そして、
「滋賀でも京都でもできるだけ、
見たらどこかわかるような
“現実の固有名詞を持つところ”を描くように
心がけているんです」
と仰います。
梶本さんの絵にある景色は
私達のよく知る場所でありながら
小さな画面の中に、美しく細やかな
点描で描かれることによって、
現実のその場所よりも淡くて軽い、
“心の中におさめやすい”場所へと
変貌を遂げるようです。
“心の中におさまる”という表現を
別の言葉で言い換えれば
「愛着を持つ」「好きになる」
ということになるのかもしれません。

梶本さんが、今のような形で
制作活動をされるようになるまでには
こんな変遷があったのだそうです。
「少年時代から絵が好きだったんですけれども、
社会人になる前に、
友達が美術コースを選んだんですね。
自分は機械工学を学んで、
IT関係の会社に就職しました」
「定年前に大病をし、生きながらえて、
何かやり残したことはあるかと考え、
絵があるな、と思ったんです。
描くからには楽しく描きたい。
見る人の心が和むような形で、と」
最後に、今回の展示を
見に来てくださる皆様へ
メッセージをいただきました。
「近江の方は、大阪よりもむしろ
京都に憧れを持っておられると
聞きました。
今回の展示ではそういう魅力も
出せたらというのと、
近江の風景と京都の風景を
並べて展示する面白さも
感じていただけたらと思います」

(日野の景色も描いてくださいました)
“京都の方は、梶本さんのお描きに
なった滋賀の風景を見て、どう仰いますか?”
と質問したところ、
「いや、『面白い』『一回行ってみよう』って
言われますよ」
と言われたあと、
「この絵はそういう
“滋賀再発見”みたいなことにも
つながるのかもしれないですね。
実は僕は守山市役所の臨時職員を
やっていまして、
地域の魅力をFacebookで
発信しているんですよ。」
梶本さんの目線がとらえた
守山、滋賀の魅力にご興味のある方は
ぜひ守山市役所のFacebookを
覗いてみてくださいね!
↓↓↓
https://ja-jp.facebook.com/moriyamaprf
そしてもちろん、わたむきホール虹での
展覧会にて梶本さんの絵を通し、
「滋賀と京都」という、私達にもっとも
親しい土地の中に
新しい“私の好きな場所”を
見つけていただければと思います。
(9月1日(火)9日(火)は休館日です)
Posted by わたむきホール虹 at 18:20│Comments(0)
│美術ギャラリー