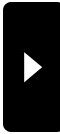2015年04月12日
【開催中】松村 勝 写真絵画展
みなさん、こんにちは
今年の桜は存分に楽しまれたでしょうか?
近年目にする光景ですが、
大きな街の、人の集まる場所で桜が咲くと
私達日本人と同様に、かなりの数の外国の方が
スマートフォンで撮影をされたりしています。
前に、日本に住む外国人の知人が
「春になると桜が綺麗だから、日本は最高だ」
と言っていました。
毎年、春先のこの季節、
私達は最高の場所で暮らしているのですね
さて、そんな綺麗な桜の一瞬の美を閉じ込めて
好きなときに眺めるための道具、
それが写真です。
現在、わたむき美術ギャラリーでは、
写真が“残されるもの”になるために
ある努力をされた写真家の方の展覧会を
開催しています。
松村勝 写真絵画展
~写真の美 後世に
湖国の四季~
4月9日(木)~4月29日(水・祝)

“写真を後世に残す”ことを目的として
「写真絵画」という独自のジャンルを
開拓された栗東市在住の写真家、
松村勝さんの作品展です。
また、今回は
「地元日野の方と何かコラボレーションしたい」
という松村さんの希望により、
日野町にお住まいの山本良秀さんが育てられている
貴重な石楠花の鉢植えが、
会場の随所を彩っています。

(左が松村さん、右が山本さんです)
まずはじめに、松村さんが生み出した
「写真絵画」とは何かをご説明します。
写真のデータを、特殊な顔料プリンタで
油絵のキャンバス地に印刷します。
印刷された写真は、そのままではニュアンスに欠け
印刷の粗い部分も存在します。
そこに絵筆を使い、手彩色で精密な補正を加え
立体感、色調の美しさ、輪郭の明晰さを
表現していきます。
この技術は松村さん独自のもの。
また、徳島県にある大塚美術館の陶板画
(世界のあらゆる名画を原寸大で陶板画にしている)
の作成には、松村さんの技術が用いられています。

(一見普通の写真のようですが・・・)

(フラッシュを正面からたくと、キャンバス地の凹凸がわかります)
「写真絵画」の仕上がりは、
キャンバス地に印刷されたとは
思えないほどの透明感と鮮やかさに満ちたもの。
しかし、どうして松村さんは
普通に写真をプリントするのではなく
このような方法をとられるのでしょうか。
(松村さん)「昔、カメラマンになった時に
言われたんですね。
『写真というのは、劣化するから
芸術品として美術館に置いてもらえません。
写真家になっても、自分の作品を
後世に残すことはできないのですよ』と。
そこで、劣化しない印刷物はないか考えたんです」
“「写真はコマーシャルでしかない」
と言われたんです”
と松村さんは言われます。
“今そのとき”“生のもの”を次々にとらえるのが、
写真に求められることであり、
まして「もの」として後世に残せないのなら
芸術品にはならない、と。
「どこの国の美術館でもだめです。
今、写真を収蔵している美術館は、
個人が建てた記念館などではないでしょうか」

正直なところ、このお話には驚きました。
書店や図書館の美術書のコーナーに行けば、
“芸術”として撮影され、また扱われているに違いない
素晴らしい写真集がたくさんあります。
それなのに、美術館に写真は収蔵されないとは。
また、写真家の方は現像もご自身でされるので、
現像の仕上げかた自体もその方の技術や
芸術的な表現だと思っていました…と、
松村さんにお伝えすると、
松村さんは、戦後の写真がたどってきた歴史を
説明してくださいました。
「昔はネガがあって、現像液を使ってそれを
印画紙に焼きつけていたわけです。
それは写真家がしていました。
今その方法は、コストが高くついてしまいます。
私は昭和38年に、18歳でカメラマンになりましたが
最初はガラスの感板写真、次に白黒フィルム、
その次がネガフィルム、ポジカラー、
そして最新がデジタルと、
65年の間に、像を写真として記録する方法は
5代も交代しているんです。
ほぼ10年に1度、変わっている計算です」
デジタル全盛の現在、
私達は自宅で簡単にできるはずの
写真のプリント作業の手間さえ
惜しむようになってしまいました。
「次はどうなっていくのか…とにかく
“もの”としての写真には将来がない。
そう思ったとき、
キャンバスにしたら、なくならないのではと
考えました。
キャンバス地なら、絵画のように修復ができます。
実際どうなるかはわかりませんが
100年後も残そうと思えば残っている可能性がある。」

この「写真絵画」の技術は
手彩色の部分に非常な精密さと根気を要するそうです。
薄い色を何層にも何層にも重ねて彩色することで
肉眼で捉える光の反射を自然なものにし、
写真のもつ、つややかな表面を保ちつつも、
被写体が立体的に見える効果を生み出します。
まさにヨーロッパの古い絵画の修復のような作業。
そんな大変な工程をへてまで、
“100年後も残るものにしたい”
との思いをかけられる写真には
いったい何が写されているのでしょうか。
「後世に残すモチーフとしては
自然環境をね、これは永遠ではないものですから。
自分の住んでいる滋賀県の四季の風景を
最大限残そうと考えたんです。
そう決めたからには、
まずいい作品を撮らなければなりません」
“残すための写真”にふさわしい
その一瞬がやってくるのを求めて
写真家としての松村さんもまた、あらゆる努力を
撮影に注ぎ込まれます。
私達にはなじみ深く思われる風景の中に
最上の光と構図を求め、必要な情報収集をし、
高所からのアングルが必要であれば
脚立にも乗り続け、
気が遠くなるほどに時間をかけて
ベストの写真を撮影されているそうです。

(「この紫陽花の風景、ここもすでに変わってしまっているんですよ。この写真の通りの景色はもう存在しないんです」と、松村さんの奥様が教えてくださいました)

(「たとえばこのコハクチョウの写真、普通はこんな位置から撮れないんですよ。近づけない。どうやって撮ったと思いますか?“コハクチョウを守る会” の会長になったんです(笑)」と、松村さん。)
“写真を後世に残すこと”に
大きなエネルギーを費やしてこられた
松村さん。
お話をお伺いしながら、いったい何が
松村さんを動かして
ここまでのお仕事をさせるのか…と
考えていました。
「“写真絵画”の技術開発には10年かかり、
身の回りのことが、やっと10年前ぐらいから
落ち着いてきました。
私は高いレベルの教育を受けていません。
もしそういうものがあれば、
他に人生の選択肢もあったかもしれないから、
きっと写真に対してここまでしていない。
自分のやることはこれと決めているからです。
“こんなこと”に自分の人生をかけられる人間は
他にいないと思いますから。」
“こんなことに人生をかけられる人間は
他にいないと思う”
と、仰る言葉が心に残りました。
「もし若い人が、何かでこういうこと
(「写真を残すこと」)が必要になったとき、
誰か、前にやった人がいて、方法が残っていると
非常にやりやすいと思うんです。
僕はいつまでも生きるわけじゃありませんから
(若い人のための)足跡をつけているというか」
今回賛助出品として展示してくださった
山本良秀さんの鉢植えを眺めながら
松村さんは仰いました。
「石楠花は咲くのに10年かかるそうですね。
僕と同じですね」

ヨーロッパには、
古いものを残していく文化があるといいます。
人々は何百年も前の建物や絵画を修復する
技術を学び、若い世代に受け継いでいます。
もちろん日本にもそういった修復の技術は
ありますが、
“後世に受け継いでいく精神”の面で
ヨーロッパの方がゆるぎないものを
持っているように思われます。
その精神とは、一言で言うと
「これを未来に手渡すのは自分だ」
という自覚を、一人ひとりが持っている
ということに、尽きるのではないでしょうか。

美しい風景の写真を眺めながら、
自分自身にとっての
「後世に残したいもの」は何なのかに
思いを巡らせたくなる展覧会です。
石楠花も美しく咲いていますので、
ぜひ一度、ご来場ください。
(4月14日(火)・21日(火)・28日(火)は休館日です)

今年の桜は存分に楽しまれたでしょうか?
近年目にする光景ですが、
大きな街の、人の集まる場所で桜が咲くと
私達日本人と同様に、かなりの数の外国の方が
スマートフォンで撮影をされたりしています。
前に、日本に住む外国人の知人が
「春になると桜が綺麗だから、日本は最高だ」
と言っていました。
毎年、春先のこの季節、
私達は最高の場所で暮らしているのですね

さて、そんな綺麗な桜の一瞬の美を閉じ込めて
好きなときに眺めるための道具、
それが写真です。
現在、わたむき美術ギャラリーでは、
写真が“残されるもの”になるために
ある努力をされた写真家の方の展覧会を
開催しています。
松村勝 写真絵画展
~写真の美 後世に
湖国の四季~
4月9日(木)~4月29日(水・祝)
“写真を後世に残す”ことを目的として
「写真絵画」という独自のジャンルを
開拓された栗東市在住の写真家、
松村勝さんの作品展です。
また、今回は
「地元日野の方と何かコラボレーションしたい」
という松村さんの希望により、
日野町にお住まいの山本良秀さんが育てられている
貴重な石楠花の鉢植えが、
会場の随所を彩っています。

(左が松村さん、右が山本さんです)
まずはじめに、松村さんが生み出した
「写真絵画」とは何かをご説明します。
写真のデータを、特殊な顔料プリンタで
油絵のキャンバス地に印刷します。
印刷された写真は、そのままではニュアンスに欠け
印刷の粗い部分も存在します。
そこに絵筆を使い、手彩色で精密な補正を加え
立体感、色調の美しさ、輪郭の明晰さを
表現していきます。
この技術は松村さん独自のもの。
また、徳島県にある大塚美術館の陶板画
(世界のあらゆる名画を原寸大で陶板画にしている)
の作成には、松村さんの技術が用いられています。

(一見普通の写真のようですが・・・)

(フラッシュを正面からたくと、キャンバス地の凹凸がわかります)
「写真絵画」の仕上がりは、
キャンバス地に印刷されたとは
思えないほどの透明感と鮮やかさに満ちたもの。
しかし、どうして松村さんは
普通に写真をプリントするのではなく
このような方法をとられるのでしょうか。
(松村さん)「昔、カメラマンになった時に
言われたんですね。
『写真というのは、劣化するから
芸術品として美術館に置いてもらえません。
写真家になっても、自分の作品を
後世に残すことはできないのですよ』と。
そこで、劣化しない印刷物はないか考えたんです」
“「写真はコマーシャルでしかない」
と言われたんです”
と松村さんは言われます。
“今そのとき”“生のもの”を次々にとらえるのが、
写真に求められることであり、
まして「もの」として後世に残せないのなら
芸術品にはならない、と。
「どこの国の美術館でもだめです。
今、写真を収蔵している美術館は、
個人が建てた記念館などではないでしょうか」

正直なところ、このお話には驚きました。
書店や図書館の美術書のコーナーに行けば、
“芸術”として撮影され、また扱われているに違いない
素晴らしい写真集がたくさんあります。
それなのに、美術館に写真は収蔵されないとは。
また、写真家の方は現像もご自身でされるので、
現像の仕上げかた自体もその方の技術や
芸術的な表現だと思っていました…と、
松村さんにお伝えすると、
松村さんは、戦後の写真がたどってきた歴史を
説明してくださいました。
「昔はネガがあって、現像液を使ってそれを
印画紙に焼きつけていたわけです。
それは写真家がしていました。
今その方法は、コストが高くついてしまいます。
私は昭和38年に、18歳でカメラマンになりましたが
最初はガラスの感板写真、次に白黒フィルム、
その次がネガフィルム、ポジカラー、
そして最新がデジタルと、
65年の間に、像を写真として記録する方法は
5代も交代しているんです。
ほぼ10年に1度、変わっている計算です」
デジタル全盛の現在、
私達は自宅で簡単にできるはずの
写真のプリント作業の手間さえ
惜しむようになってしまいました。
「次はどうなっていくのか…とにかく
“もの”としての写真には将来がない。
そう思ったとき、
キャンバスにしたら、なくならないのではと
考えました。
キャンバス地なら、絵画のように修復ができます。
実際どうなるかはわかりませんが
100年後も残そうと思えば残っている可能性がある。」

この「写真絵画」の技術は
手彩色の部分に非常な精密さと根気を要するそうです。
薄い色を何層にも何層にも重ねて彩色することで
肉眼で捉える光の反射を自然なものにし、
写真のもつ、つややかな表面を保ちつつも、
被写体が立体的に見える効果を生み出します。
まさにヨーロッパの古い絵画の修復のような作業。
そんな大変な工程をへてまで、
“100年後も残るものにしたい”
との思いをかけられる写真には
いったい何が写されているのでしょうか。
「後世に残すモチーフとしては
自然環境をね、これは永遠ではないものですから。
自分の住んでいる滋賀県の四季の風景を
最大限残そうと考えたんです。
そう決めたからには、
まずいい作品を撮らなければなりません」
“残すための写真”にふさわしい
その一瞬がやってくるのを求めて
写真家としての松村さんもまた、あらゆる努力を
撮影に注ぎ込まれます。
私達にはなじみ深く思われる風景の中に
最上の光と構図を求め、必要な情報収集をし、
高所からのアングルが必要であれば
脚立にも乗り続け、
気が遠くなるほどに時間をかけて
ベストの写真を撮影されているそうです。

(「この紫陽花の風景、ここもすでに変わってしまっているんですよ。この写真の通りの景色はもう存在しないんです」と、松村さんの奥様が教えてくださいました)

(「たとえばこのコハクチョウの写真、普通はこんな位置から撮れないんですよ。近づけない。どうやって撮ったと思いますか?“コハクチョウを守る会” の会長になったんです(笑)」と、松村さん。)
“写真を後世に残すこと”に
大きなエネルギーを費やしてこられた
松村さん。
お話をお伺いしながら、いったい何が
松村さんを動かして
ここまでのお仕事をさせるのか…と
考えていました。
「“写真絵画”の技術開発には10年かかり、
身の回りのことが、やっと10年前ぐらいから
落ち着いてきました。
私は高いレベルの教育を受けていません。
もしそういうものがあれば、
他に人生の選択肢もあったかもしれないから、
きっと写真に対してここまでしていない。
自分のやることはこれと決めているからです。
“こんなこと”に自分の人生をかけられる人間は
他にいないと思いますから。」
“こんなことに人生をかけられる人間は
他にいないと思う”
と、仰る言葉が心に残りました。
「もし若い人が、何かでこういうこと
(「写真を残すこと」)が必要になったとき、
誰か、前にやった人がいて、方法が残っていると
非常にやりやすいと思うんです。
僕はいつまでも生きるわけじゃありませんから
(若い人のための)足跡をつけているというか」
今回賛助出品として展示してくださった
山本良秀さんの鉢植えを眺めながら
松村さんは仰いました。
「石楠花は咲くのに10年かかるそうですね。
僕と同じですね」

ヨーロッパには、
古いものを残していく文化があるといいます。
人々は何百年も前の建物や絵画を修復する
技術を学び、若い世代に受け継いでいます。
もちろん日本にもそういった修復の技術は
ありますが、
“後世に受け継いでいく精神”の面で
ヨーロッパの方がゆるぎないものを
持っているように思われます。
その精神とは、一言で言うと
「これを未来に手渡すのは自分だ」
という自覚を、一人ひとりが持っている
ということに、尽きるのではないでしょうか。

美しい風景の写真を眺めながら、
自分自身にとっての
「後世に残したいもの」は何なのかに
思いを巡らせたくなる展覧会です。
石楠花も美しく咲いていますので、
ぜひ一度、ご来場ください。
(4月14日(火)・21日(火)・28日(火)は休館日です)
2015年03月21日
Facebookはじめました!
お知らせです。
この春、
わたむきホール虹の
Facebookページを
開設いたしました !
!
右側のサイドバー、
「お気に入り」から入っていただけます
ホームの写真は、
「わたむきホール虹」を象徴するこの1枚。

いえ、皆様が
「・・・やっと?」
「なんで今のタイミング?」
とお思いになっていらっしゃることは
きちんと了解しております
非常にマイペースなタイミングの開設で
申し訳ございません。
今後は、最新のタイムラインはFacebookで、
読みごたえたっぷりの長文記事は滋賀咲くブログで、
どんどん情報発信をしていきますので
よろしくお願いします!
この春、
わたむきホール虹の
Facebookページを
開設いたしました
 !
!右側のサイドバー、
「お気に入り」から入っていただけます

ホームの写真は、
「わたむきホール虹」を象徴するこの1枚。

いえ、皆様が
「・・・やっと?」
「なんで今のタイミング?」
とお思いになっていらっしゃることは
きちんと了解しております

非常にマイペースなタイミングの開設で
申し訳ございません。
今後は、最新のタイムラインはFacebookで、
読みごたえたっぷりの長文記事は滋賀咲くブログで、
どんどん情報発信をしていきますので
よろしくお願いします!
2015年03月21日
【開催中】ぱふ ワイヤークラフト展
みなさん、こんにちは!
春ですね 。気温が上がるのにきっちり比例して、
。気温が上がるのにきっちり比例して、
外を行く人々の服装がカラフルになるのが楽しいです。
「寒の戻り」というものもありますが、
多少戻ってもそのうち必ず暖かい日がやってくる。
そう思えるだけでなんだか心強いですよね。
そんな気持ちのいい春の日に、
ぜひわたむきホール虹まで足を伸ばして
ご覧になっていただきたい展覧会が
現在、美術ギャラリーにて開催中です。
ぱふ ワイヤークラフト展
~湖国の風景・異国の風景~
ワイヤーで風景を描きました~
3月19日(木)~4月5日(日)

アイアンワイヤー(鉄ワイヤー)の特性と質感をいかし、
ワイヤーの線で印象的な風景や植物などを描いた作品を
制作する作家、「ぱふ」さんの展覧会です。
そして今回は賛助出品として、
2002年にこの美術ギャラリーに出展いただいた
澤井泉源(さわいせんげん)さん制作の
“古材で作った家具”も同時にご覧いただけます。
「ぱふ」さんと澤井さんのお写真はこちら

(右が「ぱふ」さん、左が澤井さん。澤井さん制作のテーブルセットで談笑中)
まずは「ぱふ」さんに、
大人の女性の心を間違いなく一瞬でつかんでしまう
素敵なワイヤークラフト作品についてお話を伺いました。
ちなみに、「ぱふ」さんは作家活動の際のお名前を
「ぱふ」で統一していらっしゃるので、
記事中でも「ぱふ」さんとお呼びいたします。
また、「ぱふ」さんはこのわたむきブログと同じ
滋賀咲くブログに近況を綴られています。
ギャラリーに来られる予定も掲載されていますので
こちらもぜひのぞいてください!
Paf's WIRE★CRAFT
http://paf.shiga-saku.net/
―本当に可愛い作品ですね…。
「ぱふ」さんの作家活動としては、
“ワイヤーで風景を描いた作品を制作されている”
で、よろしいんでしょうか。―
「ぱふ」さん「はい、ワイヤーで風景を作っています。
今回は日野町での展示ということで、
『日野の風景』を作ってみたんです」
―あっ、綿向(わたむき)山ですね。-

「そうなんです。
それと、ここが“わたむきホール虹”なので
虹を入れました」
ワイヤーの線だけで日野町のシンボル“綿向山”、
そして“虹”まで描けてしまうことと、
何気ないようでいて細部まで美しく仕上げられた
作品のたたずまいに見入ってしまうばかりです。
でも、どうして「ワイヤーで風景」を?
「最初は盆栽用のアルミワイヤーで
カゴなどを作っていたんですね。
それが、あるとき鉄の細いワイヤーに出会ったことで
風景の額を作るようになったんです」
鉄のワイヤーを触っているうちに「ぱふ」さんはふと、
“あ、これで木を作ってみたいな”と
思われたのだそうです。
ワイヤーで何かを作られる方の中には
溶接技術を使う方もいらっしゃるそうですが、
「ぱふ」さんは「ペンチ1本で作りたいなと思って」。

―でも面白いですね。「線」で何かを表現したいと
思うとき、例えばドローイング(線描)を選ばれる
方もいらっしゃいますし…-
「あっ、私はもう『ワイヤーありき』なので。
ワイヤーがあって、何かを作ってみたいと感じるんです。
私は絵心はないんですけど、
ワイヤーを使うと、自分の思ったものが描ける。
ワイヤーで絵を描くように描いてみたくて」
今回「ぱふ」さんは、「季節の額」と題し、
12ヶ月をそれぞれの季節の植物などで表現した
小さな額のシリーズを出展してくださっています。
「植物の葉っぱや花の質感も、
ワイヤーで描くことによって、
思ったものが出せる気がするんですね」

「ぱふ」さんのお話には
「ワイヤーありき」「ワイヤーで描くことによって」
と、何度も“ワイヤーという素材”のことが
登場します。
土、木、布、ガラス…世の中には様々な
“素材”がありますが、
ある1つの素材と、作家の方の出会いとは
本当に不思議なものです。
“その素材でないと、思う作品が作れない”
というのは
創作という行為が秘める、ひとつの神秘だと思います。
―(仕上がりを決め、目的に沿って作るというよりは)
ワイヤーをなんとなく触っているうちに、
いろいろアイデアが出てくるという感じですか?-
「そうです。あの、やってみてください(笑)
本当に楽しいですから」

(これは、もともとカゴにしようと作りはじめ、途中で「雪の結晶」になった作品だそうです)
ところで、すでに見てきた作品の中に
ところどころ登場し、ワイヤーの造形物を
支えている“木の枠”。
これはもちろん…。
「木枠は、澤井泉源さんの作品です。
ある展覧会をきっかけに古木との出会いがあり
そのときから澤井さんとのつながりも生まれました」
「ぱふ」さんにとっては自在な素材であるワイヤーも
それだけしか使わない表現にはやはり限界があります。
古木はアイアンワイヤーの持つ質感にすっと馴染み、
同時に「ぱふ」さんの作品世界を
豊かに広げてくれるものだったそうです。
「このへんのオブジェ作品の木は、澤井さんが
『もう薪にくべるけど、欲しかったら取りに来い』って
言ってくださったのを急いで取りにいったもので(笑)」


「古材を見て場面が浮かんできたりもするんですね。
“物語のある風景”だと私は思っているんですけど」
―見る人がそれぞれに思う“物語”を
重ねやすい作品だと感じます―
「そうですね、色とかがないから
見た人が自由に思いを重ねてもらえるのかも
しれません」
古材の話が出てきたところで、
ぜひ澤井さんにもお話を…、と仰る「ぱふ」さん。
なごやかにインタビューの交代が行われます。
澤井さん「あんまり難しいこと聞かんといてや」
―お聞きしません(笑)
…普段の制作としては、ここにあるもののように、
古材で家具などを作られているのでしょうか―

「まあ、そうやな。
“人が使っていた外にあるもの”の古材。
中にあるものじゃなくて。
(外に置いてあって使い込まれたものの)
汚い感じが好きなんです」
澤井さんのお家はもともと、茶道で使用する道具を
作られていたそうで、
その道具の中に、舟板の古材をほぼそのまま使用した
“舟板結界”というものがあり、
昔から、「古い舟板」が身近なものだったそうです。
「外にあるものって、雨やらいろいろなものに
さらされるから、いい材料で作られてるんやね」
また、銅管や銅板などの古い金属も収集され、
作品の中で使われています。

(ペン立てへと生まれ変わった銅管。こんな机の上で仕事ができたら…)
「屋根の古い樋(とい)とかな、銅板や。
材料探しが一番大変。
外にさらされているもの…畑の端の板とか
(土を止めるために立ててある板のこと、でしょうか)
田んぼのところの川に渡してある板とか…」
―そういったものを見かけたら、
もしいらないのなら、譲ってほしいと
直接交渉される…―
「そうそう。だから大変」
今回、澤井さんはたくさんの「いすと机」を
ギャラリーに置いてくださいました。
「いすは座ってもらわなわからへんから、
ぜひ、いろんな人に座ってほしい。
人に座ってもらったり、さわってもらったりしたら
ものに艶も出てくるし」
古材のいすや机の木目に触れているうちに
自分が知る、「木で作られたもの」のことが
いくつも頭に浮かんできました。
明治の西洋建築だった小学校の校舎や
7月5日にわたむきホール虹で開催する
「オーケストラ・ムジカ・チェレステ演奏会」で
ソリストの鈴木舞さんが使用される
“17世紀のヴァイオリン”のこと…。
思いついたままにお話ししたことに
澤井さんは興味深く耳を傾けてくださり、
こんなふうに仰いました。
「ものは、使われなあかんからね」

それぞれに違う素材を使って、
形も用途も異なる作品を制作されている
「ぱふ」さんと澤井泉源さん。
しかしお2人の世界は、
それとは気付かないさりげなさで、
とてもよく似た響きを奏でているようです。
ワイヤーと古材、どちらもそのままでは
“用をなさなければかえりみられない”
ものかもしれませんが、
素材の美しさと可能性を見抜いた作家の手で
何かに作り変えられたとき、
「とても大切なもの」へ価値が大きく転換します。
人が手で何かをつくること、
そうして作られた何かを大切にすること、
暮らしを良くするのはまさにその2つなのだと、
あらためて感じる展覧会です。
どうぞ、会場にてゆっくりとお過ごしください。

(会場にはワイヤーとペンチが置かれています。澤井さんのテーブルセットに腰掛けて、ワイヤーでいろいろな形を作ってみてください!)
(3月22日(日)・24日(火)・31日(火) 4月3日(金)は休館日です)
春ですね
 。気温が上がるのにきっちり比例して、
。気温が上がるのにきっちり比例して、外を行く人々の服装がカラフルになるのが楽しいです。
「寒の戻り」というものもありますが、
多少戻ってもそのうち必ず暖かい日がやってくる。
そう思えるだけでなんだか心強いですよね。
そんな気持ちのいい春の日に、
ぜひわたむきホール虹まで足を伸ばして
ご覧になっていただきたい展覧会が
現在、美術ギャラリーにて開催中です。
ぱふ ワイヤークラフト展
~湖国の風景・異国の風景~
ワイヤーで風景を描きました~
3月19日(木)~4月5日(日)
アイアンワイヤー(鉄ワイヤー)の特性と質感をいかし、
ワイヤーの線で印象的な風景や植物などを描いた作品を
制作する作家、「ぱふ」さんの展覧会です。
そして今回は賛助出品として、
2002年にこの美術ギャラリーに出展いただいた
澤井泉源(さわいせんげん)さん制作の
“古材で作った家具”も同時にご覧いただけます。
「ぱふ」さんと澤井さんのお写真はこちら

(右が「ぱふ」さん、左が澤井さん。澤井さん制作のテーブルセットで談笑中)
まずは「ぱふ」さんに、
大人の女性の心を間違いなく一瞬でつかんでしまう
素敵なワイヤークラフト作品についてお話を伺いました。
ちなみに、「ぱふ」さんは作家活動の際のお名前を
「ぱふ」で統一していらっしゃるので、
記事中でも「ぱふ」さんとお呼びいたします。
また、「ぱふ」さんはこのわたむきブログと同じ
滋賀咲くブログに近況を綴られています。
ギャラリーに来られる予定も掲載されていますので
こちらもぜひのぞいてください!

Paf's WIRE★CRAFT
http://paf.shiga-saku.net/
―本当に可愛い作品ですね…。
「ぱふ」さんの作家活動としては、
“ワイヤーで風景を描いた作品を制作されている”
で、よろしいんでしょうか。―
「ぱふ」さん「はい、ワイヤーで風景を作っています。
今回は日野町での展示ということで、
『日野の風景』を作ってみたんです」
―あっ、綿向(わたむき)山ですね。-

「そうなんです。
それと、ここが“わたむきホール虹”なので
虹を入れました」
ワイヤーの線だけで日野町のシンボル“綿向山”、
そして“虹”まで描けてしまうことと、
何気ないようでいて細部まで美しく仕上げられた
作品のたたずまいに見入ってしまうばかりです。
でも、どうして「ワイヤーで風景」を?
「最初は盆栽用のアルミワイヤーで
カゴなどを作っていたんですね。
それが、あるとき鉄の細いワイヤーに出会ったことで
風景の額を作るようになったんです」
鉄のワイヤーを触っているうちに「ぱふ」さんはふと、
“あ、これで木を作ってみたいな”と
思われたのだそうです。
ワイヤーで何かを作られる方の中には
溶接技術を使う方もいらっしゃるそうですが、
「ぱふ」さんは「ペンチ1本で作りたいなと思って」。

―でも面白いですね。「線」で何かを表現したいと
思うとき、例えばドローイング(線描)を選ばれる
方もいらっしゃいますし…-
「あっ、私はもう『ワイヤーありき』なので。
ワイヤーがあって、何かを作ってみたいと感じるんです。
私は絵心はないんですけど、
ワイヤーを使うと、自分の思ったものが描ける。
ワイヤーで絵を描くように描いてみたくて」
今回「ぱふ」さんは、「季節の額」と題し、
12ヶ月をそれぞれの季節の植物などで表現した
小さな額のシリーズを出展してくださっています。
「植物の葉っぱや花の質感も、
ワイヤーで描くことによって、
思ったものが出せる気がするんですね」

「ぱふ」さんのお話には
「ワイヤーありき」「ワイヤーで描くことによって」
と、何度も“ワイヤーという素材”のことが
登場します。
土、木、布、ガラス…世の中には様々な
“素材”がありますが、
ある1つの素材と、作家の方の出会いとは
本当に不思議なものです。
“その素材でないと、思う作品が作れない”
というのは
創作という行為が秘める、ひとつの神秘だと思います。
―(仕上がりを決め、目的に沿って作るというよりは)
ワイヤーをなんとなく触っているうちに、
いろいろアイデアが出てくるという感じですか?-
「そうです。あの、やってみてください(笑)
本当に楽しいですから」

(これは、もともとカゴにしようと作りはじめ、途中で「雪の結晶」になった作品だそうです)
ところで、すでに見てきた作品の中に
ところどころ登場し、ワイヤーの造形物を
支えている“木の枠”。
これはもちろん…。
「木枠は、澤井泉源さんの作品です。
ある展覧会をきっかけに古木との出会いがあり
そのときから澤井さんとのつながりも生まれました」
「ぱふ」さんにとっては自在な素材であるワイヤーも
それだけしか使わない表現にはやはり限界があります。
古木はアイアンワイヤーの持つ質感にすっと馴染み、
同時に「ぱふ」さんの作品世界を
豊かに広げてくれるものだったそうです。
「このへんのオブジェ作品の木は、澤井さんが
『もう薪にくべるけど、欲しかったら取りに来い』って
言ってくださったのを急いで取りにいったもので(笑)」


「古材を見て場面が浮かんできたりもするんですね。
“物語のある風景”だと私は思っているんですけど」
―見る人がそれぞれに思う“物語”を
重ねやすい作品だと感じます―
「そうですね、色とかがないから
見た人が自由に思いを重ねてもらえるのかも
しれません」
古材の話が出てきたところで、
ぜひ澤井さんにもお話を…、と仰る「ぱふ」さん。
なごやかにインタビューの交代が行われます。
澤井さん「あんまり難しいこと聞かんといてや」
―お聞きしません(笑)
…普段の制作としては、ここにあるもののように、
古材で家具などを作られているのでしょうか―

「まあ、そうやな。
“人が使っていた外にあるもの”の古材。
中にあるものじゃなくて。
(外に置いてあって使い込まれたものの)
汚い感じが好きなんです」
澤井さんのお家はもともと、茶道で使用する道具を
作られていたそうで、
その道具の中に、舟板の古材をほぼそのまま使用した
“舟板結界”というものがあり、
昔から、「古い舟板」が身近なものだったそうです。
「外にあるものって、雨やらいろいろなものに
さらされるから、いい材料で作られてるんやね」
また、銅管や銅板などの古い金属も収集され、
作品の中で使われています。

(ペン立てへと生まれ変わった銅管。こんな机の上で仕事ができたら…)
「屋根の古い樋(とい)とかな、銅板や。
材料探しが一番大変。
外にさらされているもの…畑の端の板とか
(土を止めるために立ててある板のこと、でしょうか)
田んぼのところの川に渡してある板とか…」
―そういったものを見かけたら、
もしいらないのなら、譲ってほしいと
直接交渉される…―
「そうそう。だから大変」
今回、澤井さんはたくさんの「いすと机」を
ギャラリーに置いてくださいました。
「いすは座ってもらわなわからへんから、
ぜひ、いろんな人に座ってほしい。
人に座ってもらったり、さわってもらったりしたら
ものに艶も出てくるし」
古材のいすや机の木目に触れているうちに
自分が知る、「木で作られたもの」のことが
いくつも頭に浮かんできました。
明治の西洋建築だった小学校の校舎や
7月5日にわたむきホール虹で開催する
「オーケストラ・ムジカ・チェレステ演奏会」で
ソリストの鈴木舞さんが使用される
“17世紀のヴァイオリン”のこと…。
思いついたままにお話ししたことに
澤井さんは興味深く耳を傾けてくださり、
こんなふうに仰いました。
「ものは、使われなあかんからね」

それぞれに違う素材を使って、
形も用途も異なる作品を制作されている
「ぱふ」さんと澤井泉源さん。
しかしお2人の世界は、
それとは気付かないさりげなさで、
とてもよく似た響きを奏でているようです。
ワイヤーと古材、どちらもそのままでは
“用をなさなければかえりみられない”
ものかもしれませんが、
素材の美しさと可能性を見抜いた作家の手で
何かに作り変えられたとき、
「とても大切なもの」へ価値が大きく転換します。
人が手で何かをつくること、
そうして作られた何かを大切にすること、
暮らしを良くするのはまさにその2つなのだと、
あらためて感じる展覧会です。
どうぞ、会場にてゆっくりとお過ごしください。

(会場にはワイヤーとペンチが置かれています。澤井さんのテーブルセットに腰掛けて、ワイヤーでいろいろな形を作ってみてください!)
(3月22日(日)・24日(火)・31日(火) 4月3日(金)は休館日です)
2015年02月28日
【開催中】一居 孝明 洋画展
みなさん、こんにちは!
ここ数回分のブログの書き出しですが、
表現の違いはあれど大体みんなどこか
「寒くて憂鬱 」という意味の文章に
」という意味の文章に
なっていたことに気づき、反省しております。
冒頭からこの元気のなさ、失礼致しました。
でももう春!陽ざしの暖かな日が2日も続けば
ついこの間までの寒さのことを忘れてしまいます。
時間の流れと変化に瞬間ごとに対応していく
人の心と体は本当に不思議です。
さて、今回もわたむき美術ギャラリーの話題。
まさに「時間の流れ」についてのタイトルがついた
絵画展が開催中です。
一居 孝明 洋画展
~過去・現在・未来を
多視点から見つめて~
2月26日(木)~3月15日(日)

長浜市在住の画家
一居孝明(いちいたかあき)さんによる絵画展です。
一居さんのお写真はこちら。

一居さんは、あの佐藤忠良さんや舟越保武さん、
丹下健三さんも所属していたという、
「新制作協会」の会員であり、
数々の受賞歴をお持ちです。
金属の板やパイプを大きな画面全体に配し
細部まで緻密に描きこまれる作風にも圧倒され、
今回お会いする前は、何をお聞きしようか
正直なところ、多少緊張気味で考えていました。
しかしその緊張は、一居さんがお話をされる際の
深く落ち着いたお声を聞くうちに気が付けばなくなり、
ただ絵を間に置いて、ちょっとした宝探しのように
自分の心の中に埋もれたものを探す時間となりました。
それでは、そのお話の中身をご覧下さい。

―画の中のメタリックなものの印象が強いのですが、
このモチーフはずっと描かれているのですか?
「そうですね…これはここ15、6年ほどずっと
モチーフにしています。
それ以前は違うものも描いていたんですよ」
―そうなんですか! ちなみにどんなものを…。
「わりと抽象的な世界を描いていました。
抽象画ですね」
現在描かれているこのモチーフの形を
はっきりと意識されたのは、
阪神大震災が起こった時期だったそうです。
「それ以前もこんな感じのものは
やってたんですけどね。
『ゴミ』を、描いていたんです。
それこそゴミの集積場とか、車のスクラップとかを。
阪神大震災が起きる前にもオウムの事件があったり
世の中の空気が澱んでいた。
ゴミを黄金色に塗ったのは、
そんな感じを皮肉るというかね。
阪神大震災が起こって、
モチーフとしてより意識するようになりました」

阪神大震災が起こる前後の
日本全体が閉塞感に満ちていたような空気のことは
今でも鮮明に思い出せる気がします。
「今も、不安な時期ですよね。
今回のタイトルは
『過去・現在・未来を多視点から見つめて』
としていますが、
時代のそんな不安を見つめたとき、
自分のこういう表現ははまるのではないかと
思ったりして」
今のこの時代を表すイメージとして、
画面全体を無言で埋める黄金色の廃材。
しかし、一居さんの作品の前に実際に立ったとき
画から問題を鋭く突きつけられているようだったり
画が観る者を選んでいるような感じがすることはなく
むしろ、画の世界に誘い込まれているような
何か「親しい」感じをおぼえます。
これは、実際に会場で画を前にされた時に
はじめて実感していただける感覚かもしれません。
たとえば…。
―作品をみていくと、時々画面の中に
マスキングテープや荷札があったりするのですが…。


「こういうものを画の中に入れることで、
自分が関わっている瞬間の位置づけを
作品に入れ込めるというか…。
トリッキーさ、ある種の嘘の世界、
画面の中にそんなたくらみも入れたいと
思っているんです」
面白い話があってね、
と一居さんはお話を続けられます。
「僕が入っている新制作協会の
メインの展覧会が東京であったんですが、
そこに観にこられた方が、僕の絵をじっと見てね。
しばらくすると周りを確認して、誰も見てないと思われたのか
このテープを、そっとはがそうとしてくれるんですよ(笑)
それを僕は後ろから見てて『やった!』と思ってる(笑)」

(さて、お気づきになった方、そうでない方、両方いらっしゃるかもしれません。このテープも荷札も、画の上に後から貼り付けたものではなく、一居さんの筆による「絵」なんです!
驚くほど高い技術で画に仕掛けられた、なんともチャーミングないたずら。)
最初は遠くから全体を眺めて圧倒され、
しかし画家の仕掛けた“いたずら”によって
近寄り難いように見えた画と急に距離が縮まってしまう。
そしてあらためて近くで一居さんの画を見てみると
金属の廃材の中に、「時間の意味」を喚起させる
様々なものが散りばめられているのが見つかるのです。


今回のインタビューには、展覧会を企画したスタッフも同席していました。
(スタッフ)「この画を最初に見たときは、
“過去に置いてきた大切なもの”が
描いてあるのかな、というイメージだったんですよ。
でも、お話を伺っているとそれだけじゃなくて…」
一居さんは、「時間を作品に描きこむこと」について
こんな風に仰っています。
「たとえば今こうしてしゃべったことも、
もう既に、どんどん過去になっていきますね。
そして頭の中には、今これからしゃべろうとする
未来のことがあって…。
そういう瞬間的な過去・現在・未来と、
長いスパンでの過去・現在・未来を両方、
作品の中に入れてみたいんです」

(画の上部のタイプライターと、下部にあるMacのキーボードが、過去と現代をそれぞれ語っています。
「息子が小さいときに遊んでいたファミコンを、描いたこともあるんですよ」)
一居さんとギャラリーを巡りながらお話をして、
私達スタッフがたぶん最も多く画の前で発した言葉は
「なつかしい」でした。
画の中に配された「時間」を語る様々なものたちが
自分の中にとめどなく積もり続ける「時間」のことを、
いつの間にか思いださせてくれたようです。
“「画に描かれた、この場所はどこですか?」と
質問されることはないですか”とお聞きしてみました。
「どこっていうのは…ないですね。
自分の夢の中、国籍も不明な場所。
どこっていう固有名詞がない場所です」

(一居さんの画のところどころに登場するスズメは、一居さんご自身を表しているのだそうです。いろいろな方向を向いているのは未来を見たり、過去を見たりしているということ。この画の世界には他の鳥でなく、なぜかスズメがぴったり!と思います)
今後もしばらくこういう感じの作品を作っていくと思うが、
タイプライター等の具体的なものを描きこむなど
説明的な要素はなくなっていくかもしれないと
予測しています…と、仰る一居さん。
最後に、会場にいらっしゃる方へ
メッセージをいただきました。
「難しい目で見ずに、
気楽に素直に見てほしいなと思いますね。
この画はこんな画だとか、こんな事を描いているとか
枠を設けて見るのではなくて、
素直な気持ちで見てもらえるといいなと思います」

私達は毎日たくさんのことを見聞きし、
新しい一日を迎える度にそれを忘れていきます。
時間をとどめておくことは不可能ですが
そのくりかえしをどこか、
寂しく思う気持ちがあるようにも感じます。
“画の世界にも流行があります。
でも流行に流されないように、
独自の表現を貫くことが一番大事。”
そう仰る一居さんの画には、
現実の表面を忙しく流れていく時間ではなく
自分自身の内側に存在する時間の風景に
観る者を立ち返らせてくれる力があるようです。
冬から春へ。季節が移る時期にぜひご覧ください。

(古いカメラが描かれています。「父親の形見です」とのこと。)
(3月3日(火) 3月6日(金) 3月10日(火)は
休館日です)
ここ数回分のブログの書き出しですが、
表現の違いはあれど大体みんなどこか
「寒くて憂鬱
 」という意味の文章に
」という意味の文章になっていたことに気づき、反省しております。

冒頭からこの元気のなさ、失礼致しました。
でももう春!陽ざしの暖かな日が2日も続けば
ついこの間までの寒さのことを忘れてしまいます。
時間の流れと変化に瞬間ごとに対応していく
人の心と体は本当に不思議です。
さて、今回もわたむき美術ギャラリーの話題。
まさに「時間の流れ」についてのタイトルがついた
絵画展が開催中です。
一居 孝明 洋画展
~過去・現在・未来を
多視点から見つめて~
2月26日(木)~3月15日(日)

長浜市在住の画家
一居孝明(いちいたかあき)さんによる絵画展です。
一居さんのお写真はこちら。

一居さんは、あの佐藤忠良さんや舟越保武さん、
丹下健三さんも所属していたという、
「新制作協会」の会員であり、
数々の受賞歴をお持ちです。
金属の板やパイプを大きな画面全体に配し
細部まで緻密に描きこまれる作風にも圧倒され、
今回お会いする前は、何をお聞きしようか
正直なところ、多少緊張気味で考えていました。
しかしその緊張は、一居さんがお話をされる際の
深く落ち着いたお声を聞くうちに気が付けばなくなり、
ただ絵を間に置いて、ちょっとした宝探しのように
自分の心の中に埋もれたものを探す時間となりました。
それでは、そのお話の中身をご覧下さい。

―画の中のメタリックなものの印象が強いのですが、
このモチーフはずっと描かれているのですか?
「そうですね…これはここ15、6年ほどずっと
モチーフにしています。
それ以前は違うものも描いていたんですよ」
―そうなんですか! ちなみにどんなものを…。
「わりと抽象的な世界を描いていました。
抽象画ですね」
現在描かれているこのモチーフの形を
はっきりと意識されたのは、
阪神大震災が起こった時期だったそうです。
「それ以前もこんな感じのものは
やってたんですけどね。
『ゴミ』を、描いていたんです。
それこそゴミの集積場とか、車のスクラップとかを。
阪神大震災が起きる前にもオウムの事件があったり
世の中の空気が澱んでいた。
ゴミを黄金色に塗ったのは、
そんな感じを皮肉るというかね。
阪神大震災が起こって、
モチーフとしてより意識するようになりました」

阪神大震災が起こる前後の
日本全体が閉塞感に満ちていたような空気のことは
今でも鮮明に思い出せる気がします。
「今も、不安な時期ですよね。
今回のタイトルは
『過去・現在・未来を多視点から見つめて』
としていますが、
時代のそんな不安を見つめたとき、
自分のこういう表現ははまるのではないかと
思ったりして」
今のこの時代を表すイメージとして、
画面全体を無言で埋める黄金色の廃材。
しかし、一居さんの作品の前に実際に立ったとき
画から問題を鋭く突きつけられているようだったり
画が観る者を選んでいるような感じがすることはなく
むしろ、画の世界に誘い込まれているような
何か「親しい」感じをおぼえます。
これは、実際に会場で画を前にされた時に
はじめて実感していただける感覚かもしれません。
たとえば…。
―作品をみていくと、時々画面の中に
マスキングテープや荷札があったりするのですが…。


「こういうものを画の中に入れることで、
自分が関わっている瞬間の位置づけを
作品に入れ込めるというか…。
トリッキーさ、ある種の嘘の世界、
画面の中にそんなたくらみも入れたいと
思っているんです」
面白い話があってね、
と一居さんはお話を続けられます。
「僕が入っている新制作協会の
メインの展覧会が東京であったんですが、
そこに観にこられた方が、僕の絵をじっと見てね。
しばらくすると周りを確認して、誰も見てないと思われたのか
このテープを、そっとはがそうとしてくれるんですよ(笑)
それを僕は後ろから見てて『やった!』と思ってる(笑)」

(さて、お気づきになった方、そうでない方、両方いらっしゃるかもしれません。このテープも荷札も、画の上に後から貼り付けたものではなく、一居さんの筆による「絵」なんです!
驚くほど高い技術で画に仕掛けられた、なんともチャーミングないたずら。)
最初は遠くから全体を眺めて圧倒され、
しかし画家の仕掛けた“いたずら”によって
近寄り難いように見えた画と急に距離が縮まってしまう。
そしてあらためて近くで一居さんの画を見てみると
金属の廃材の中に、「時間の意味」を喚起させる
様々なものが散りばめられているのが見つかるのです。


今回のインタビューには、展覧会を企画したスタッフも同席していました。
(スタッフ)「この画を最初に見たときは、
“過去に置いてきた大切なもの”が
描いてあるのかな、というイメージだったんですよ。
でも、お話を伺っているとそれだけじゃなくて…」
一居さんは、「時間を作品に描きこむこと」について
こんな風に仰っています。
「たとえば今こうしてしゃべったことも、
もう既に、どんどん過去になっていきますね。
そして頭の中には、今これからしゃべろうとする
未来のことがあって…。
そういう瞬間的な過去・現在・未来と、
長いスパンでの過去・現在・未来を両方、
作品の中に入れてみたいんです」

(画の上部のタイプライターと、下部にあるMacのキーボードが、過去と現代をそれぞれ語っています。
「息子が小さいときに遊んでいたファミコンを、描いたこともあるんですよ」)
一居さんとギャラリーを巡りながらお話をして、
私達スタッフがたぶん最も多く画の前で発した言葉は
「なつかしい」でした。
画の中に配された「時間」を語る様々なものたちが
自分の中にとめどなく積もり続ける「時間」のことを、
いつの間にか思いださせてくれたようです。
“「画に描かれた、この場所はどこですか?」と
質問されることはないですか”とお聞きしてみました。
「どこっていうのは…ないですね。
自分の夢の中、国籍も不明な場所。
どこっていう固有名詞がない場所です」

(一居さんの画のところどころに登場するスズメは、一居さんご自身を表しているのだそうです。いろいろな方向を向いているのは未来を見たり、過去を見たりしているということ。この画の世界には他の鳥でなく、なぜかスズメがぴったり!と思います)
今後もしばらくこういう感じの作品を作っていくと思うが、
タイプライター等の具体的なものを描きこむなど
説明的な要素はなくなっていくかもしれないと
予測しています…と、仰る一居さん。
最後に、会場にいらっしゃる方へ
メッセージをいただきました。
「難しい目で見ずに、
気楽に素直に見てほしいなと思いますね。
この画はこんな画だとか、こんな事を描いているとか
枠を設けて見るのではなくて、
素直な気持ちで見てもらえるといいなと思います」

私達は毎日たくさんのことを見聞きし、
新しい一日を迎える度にそれを忘れていきます。
時間をとどめておくことは不可能ですが
そのくりかえしをどこか、
寂しく思う気持ちがあるようにも感じます。
“画の世界にも流行があります。
でも流行に流されないように、
独自の表現を貫くことが一番大事。”
そう仰る一居さんの画には、
現実の表面を忙しく流れていく時間ではなく
自分自身の内側に存在する時間の風景に
観る者を立ち返らせてくれる力があるようです。
冬から春へ。季節が移る時期にぜひご覧ください。

(古いカメラが描かれています。「父親の形見です」とのこと。)
(3月3日(火) 3月6日(金) 3月10日(火)は
休館日です)
2015年02月11日
【開催中】仁志出敬子 コンピューター・グラフィック展
みなさん、こんにちは!
いつの間にか節分が終わり、
“二十四節気”でいえば
「立春」を迎えているはずの今日この頃。
なのに…寒い!寒いです
春はすぐそこ、地面のすぐ下まで来ているのに。
冬の少しだけ寂しい気分と、
春を待ち望むわくわくした気持ちが
入り混じる今の季節の空気感に
とてもよく似合う展覧会をご紹介します。
仁志出敬子
コンピューター・グラフィック展
~心の中の生き物たち~
2月5日(木)~2月22日(日)

動物たち(時々擬人化されていたりします)や、
現実にあるもののようで
どこか非現実的な物たちを、
優しい色使いとユニークな画面構成で描く
仁志出敬子さんの展覧会です。
仁志出敬子さんはこの方です。

まず、「コンピューター・グラフィック」というと、
もしかすると緻密で、メカニックで、先鋭的な作風を
イメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが
仁志出さんの作品は「コンピューター」を
意識させることのない、温かで優しい印象です。
「そうですね、わざと手描きっぽくしている
ところはあります。
パソコンでなめらかな線を描くというのは、
相当熟練していないとできない技術ですね」
コンピューターを習い始めたのは、今から18年前という
仁志出さん。
デザインやテキスタイルのお仕事をされていた関係も
かねて習得された技術ですが、
「コンピューター」を使って作品制作をするということに
特別な意識はなく、
ただ制作に必要な道具として捉えておられるようです。
「パソコンは機械の一種ですよね。
いびつなものを修正できたりもしますが、
パソコンだからといってきちっと線が描けるわけでは
ないので…。
作品をご覧になった方に『切って貼ったんか?』と
訊かれることもあるんですけど(笑)
私自身はこういう描き方が好きなので」
そして、実際に作品を見ていただくと
否応なく惹きつけられるのが、
そこに描かれた、可愛くて、シュールで
不思議な世界です。

「よく『この絵には何か物語があるの?』って
訊かれたりするんですけど、
物語があって、それに絵をつけているんじゃないんです。
最初に視覚的なイメージがあって、絵を描きます。
ストーリーは後からついたりすることもありますが」
“こういうものを描こう”と、頭で考えて決めるより
心に浮かんだ視覚的なイメージを着想にされるという
仁志出さん。
たとえば、こちらの「心の中の生き物」というタイトルが
ついた一連の作品は、
浮かんだイメージをクロッキー帳に描きためておき、
何年か経って掘り起こしたものが描かれています。

物語から生まれる絵ではない。
でも、
「この絵は何かの物語を表わしているんじゃないか…」
そう推測したい方の気持もわかる気がする
というぐらい、
仁志出さんの作品は本当に、
見れば見るほどユニークで興味がつきません。
描かれている動物や人物が、ファンタジックでありながら
互いに絶妙な距離感を保っていることで生まれる
飄々としたユーモアのセンス。
現実からすれば突飛な光景が描かれているのに
絵の中の生き物たちは「いたって平常心」であることが
昔読んだ
“不思議の国のアリス”の世界を思い出させます。

―(笑)面白いです。なぜ動物たちはこのような形に…。
「“メビウスの輪”って、立体的に面白いと思って。
あと、“クラインの壷”ってありますよね。
そういう感じを作品に取り入れたくて。
輪の中に描いたのは、まあ
“うさぎとねこが永遠に追いかけっこをしている”
というか…(笑)」

―これは、左下の人物が“狼男”に
変身している最中かなと思ったのですが。
「いえ、イメージでは
“ピーターパンが影を身に着けている”
みたいな感じだったんですけど…」
―影ですか。そのただならぬ様子に
周りの動物たちも反応していますね。

―木になっている人物もインパクトがありますが、
周りに描かれてあるものも不思議です。
室内は夜のようなのに、窓の外は昼に見えたり。
あと、右側の大きなものさしとか、
左の壁から出ている足とか。
「そうですね…ものさしはあの、やはり背が伸びるということで…(笑)足は、ここにピンクのものが欲しかったんですけど、こう、足があったほうがいいかな…?と(笑)」
―(笑)
派手な見た目で注意をひく形ではなく
画面の細部に目をこらすほど、
じわじわとおかしさがこみあげてくるユーモアを
そなえた仁志出さんの作品たち。
「おかしいですよね。描いているときは別に
笑いを取ろうと思って描いていないんですけど…。
でも、自分でも笑えてきます(笑)」
コンピューターを使用し、独自の世界を描く
仁志出さんの作品群は、
わかりやすい形で「ジャンル分け」ができる
特徴をもたないため
これまで、様々な形に受け取られてきたそうです。

「『イラストレーターですか?』と訊かれることも
あるんですけれど、
“イラストレーター”の定義がわからなくて。
辞書で引くと、
“絵本の挿絵を描く人”“商業的な絵を描く人”
というような意味があったのですが、
この作品は、売るための絵ではないので…」
また、絵の中に登場する動物や人物やものの
大きさが現実とは異なっていたり、
いわゆる「遠近法」に沿っているといえない形で
あることについて、仁志出さんは、
「みんな対等に描いていて、絵の中のどれを強調
したくてというのが、あまりないんです」
と言われます。
あくまで私個人の感想ですが、
その感覚は、仁志出さんがデザインや
テキスタイルの制作を手がけられてきたことに
関係があるのかもと思いました。

最後に、来場される方にメッセージをいただきました。
「具体的で、でも写実的ではないという世界ですので
現実の固定観念にとらわれないで見てほしいと思います。
展示のタイトルにもある“心の中の生き物”として」
インタビュー中の仁志出さんの言葉に
反するようですが
私が仁志出さんの作品を見て連想したものは
「昔の児童書の挿絵作家の作品」でした。
デザイン性に優れながら、温かさとユーモアをそなえ、
決して「物語の説明」にならない豊かな挿絵の世界。
その絵は、読み手の想像力を縛るものではなく、
絵があることで物語は謎を深め、奥行きを増します。
観る側が心を開いてじっと見つめた分だけ、
中にある豊かな世界を教えてくれる、
そんな仁志出さんの作品世界をぜひ会場で
心ゆくまで時間をかけて
ご覧になっていただきたいです。

(仁志出さんの旦那様は2013年にこのギャラリーに出展していただいた仁志出孝春さんです。「ご主人様は作品を見て何と言われますか?」との質問に「こんな発想がいったいどこから来るのか不思議だ、って言います」)
(2月12日(木)・2月17日(火)は休館日です)
いつの間にか節分が終わり、
“二十四節気”でいえば
「立春」を迎えているはずの今日この頃。
なのに…寒い!寒いです

春はすぐそこ、地面のすぐ下まで来ているのに。
冬の少しだけ寂しい気分と、
春を待ち望むわくわくした気持ちが
入り混じる今の季節の空気感に
とてもよく似合う展覧会をご紹介します。
仁志出敬子
コンピューター・グラフィック展
~心の中の生き物たち~
2月5日(木)~2月22日(日)

動物たち(時々擬人化されていたりします)や、
現実にあるもののようで
どこか非現実的な物たちを、
優しい色使いとユニークな画面構成で描く
仁志出敬子さんの展覧会です。
仁志出敬子さんはこの方です。

まず、「コンピューター・グラフィック」というと、
もしかすると緻密で、メカニックで、先鋭的な作風を
イメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが
仁志出さんの作品は「コンピューター」を
意識させることのない、温かで優しい印象です。
「そうですね、わざと手描きっぽくしている
ところはあります。
パソコンでなめらかな線を描くというのは、
相当熟練していないとできない技術ですね」
コンピューターを習い始めたのは、今から18年前という
仁志出さん。
デザインやテキスタイルのお仕事をされていた関係も
かねて習得された技術ですが、
「コンピューター」を使って作品制作をするということに
特別な意識はなく、
ただ制作に必要な道具として捉えておられるようです。
「パソコンは機械の一種ですよね。
いびつなものを修正できたりもしますが、
パソコンだからといってきちっと線が描けるわけでは
ないので…。
作品をご覧になった方に『切って貼ったんか?』と
訊かれることもあるんですけど(笑)
私自身はこういう描き方が好きなので」
そして、実際に作品を見ていただくと
否応なく惹きつけられるのが、
そこに描かれた、可愛くて、シュールで
不思議な世界です。

「よく『この絵には何か物語があるの?』って
訊かれたりするんですけど、
物語があって、それに絵をつけているんじゃないんです。
最初に視覚的なイメージがあって、絵を描きます。
ストーリーは後からついたりすることもありますが」
“こういうものを描こう”と、頭で考えて決めるより
心に浮かんだ視覚的なイメージを着想にされるという
仁志出さん。
たとえば、こちらの「心の中の生き物」というタイトルが
ついた一連の作品は、
浮かんだイメージをクロッキー帳に描きためておき、
何年か経って掘り起こしたものが描かれています。

物語から生まれる絵ではない。
でも、
「この絵は何かの物語を表わしているんじゃないか…」
そう推測したい方の気持もわかる気がする
というぐらい、
仁志出さんの作品は本当に、
見れば見るほどユニークで興味がつきません。
描かれている動物や人物が、ファンタジックでありながら
互いに絶妙な距離感を保っていることで生まれる
飄々としたユーモアのセンス。
現実からすれば突飛な光景が描かれているのに
絵の中の生き物たちは「いたって平常心」であることが
昔読んだ
“不思議の国のアリス”の世界を思い出させます。

―(笑)面白いです。なぜ動物たちはこのような形に…。
「“メビウスの輪”って、立体的に面白いと思って。
あと、“クラインの壷”ってありますよね。
そういう感じを作品に取り入れたくて。
輪の中に描いたのは、まあ
“うさぎとねこが永遠に追いかけっこをしている”
というか…(笑)」

―これは、左下の人物が“狼男”に
変身している最中かなと思ったのですが。
「いえ、イメージでは
“ピーターパンが影を身に着けている”
みたいな感じだったんですけど…」
―影ですか。そのただならぬ様子に
周りの動物たちも反応していますね。

―木になっている人物もインパクトがありますが、
周りに描かれてあるものも不思議です。
室内は夜のようなのに、窓の外は昼に見えたり。
あと、右側の大きなものさしとか、
左の壁から出ている足とか。
「そうですね…ものさしはあの、やはり背が伸びるということで…(笑)足は、ここにピンクのものが欲しかったんですけど、こう、足があったほうがいいかな…?と(笑)」
―(笑)
派手な見た目で注意をひく形ではなく
画面の細部に目をこらすほど、
じわじわとおかしさがこみあげてくるユーモアを
そなえた仁志出さんの作品たち。
「おかしいですよね。描いているときは別に
笑いを取ろうと思って描いていないんですけど…。
でも、自分でも笑えてきます(笑)」
コンピューターを使用し、独自の世界を描く
仁志出さんの作品群は、
わかりやすい形で「ジャンル分け」ができる
特徴をもたないため
これまで、様々な形に受け取られてきたそうです。

「『イラストレーターですか?』と訊かれることも
あるんですけれど、
“イラストレーター”の定義がわからなくて。
辞書で引くと、
“絵本の挿絵を描く人”“商業的な絵を描く人”
というような意味があったのですが、
この作品は、売るための絵ではないので…」
また、絵の中に登場する動物や人物やものの
大きさが現実とは異なっていたり、
いわゆる「遠近法」に沿っているといえない形で
あることについて、仁志出さんは、
「みんな対等に描いていて、絵の中のどれを強調
したくてというのが、あまりないんです」
と言われます。
あくまで私個人の感想ですが、
その感覚は、仁志出さんがデザインや
テキスタイルの制作を手がけられてきたことに
関係があるのかもと思いました。

最後に、来場される方にメッセージをいただきました。
「具体的で、でも写実的ではないという世界ですので
現実の固定観念にとらわれないで見てほしいと思います。
展示のタイトルにもある“心の中の生き物”として」
インタビュー中の仁志出さんの言葉に
反するようですが
私が仁志出さんの作品を見て連想したものは
「昔の児童書の挿絵作家の作品」でした。
デザイン性に優れながら、温かさとユーモアをそなえ、
決して「物語の説明」にならない豊かな挿絵の世界。
その絵は、読み手の想像力を縛るものではなく、
絵があることで物語は謎を深め、奥行きを増します。
観る側が心を開いてじっと見つめた分だけ、
中にある豊かな世界を教えてくれる、
そんな仁志出さんの作品世界をぜひ会場で
心ゆくまで時間をかけて
ご覧になっていただきたいです。

(仁志出さんの旦那様は2013年にこのギャラリーに出展していただいた仁志出孝春さんです。「ご主人様は作品を見て何と言われますか?」との質問に「こんな発想がいったいどこから来るのか不思議だ、って言います」)
(2月12日(木)・2月17日(火)は休館日です)