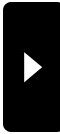› わたむきホール虹ブログ › 美術ギャラリー
› わたむきホール虹ブログ › 美術ギャラリー2015年02月28日
【開催中】一居 孝明 洋画展
みなさん、こんにちは!
ここ数回分のブログの書き出しですが、
表現の違いはあれど大体みんなどこか
「寒くて憂鬱 」という意味の文章に
」という意味の文章に
なっていたことに気づき、反省しております。
冒頭からこの元気のなさ、失礼致しました。
でももう春!陽ざしの暖かな日が2日も続けば
ついこの間までの寒さのことを忘れてしまいます。
時間の流れと変化に瞬間ごとに対応していく
人の心と体は本当に不思議です。
さて、今回もわたむき美術ギャラリーの話題。
まさに「時間の流れ」についてのタイトルがついた
絵画展が開催中です。
一居 孝明 洋画展
~過去・現在・未来を
多視点から見つめて~
2月26日(木)~3月15日(日)

長浜市在住の画家
一居孝明(いちいたかあき)さんによる絵画展です。
一居さんのお写真はこちら。

一居さんは、あの佐藤忠良さんや舟越保武さん、
丹下健三さんも所属していたという、
「新制作協会」の会員であり、
数々の受賞歴をお持ちです。
金属の板やパイプを大きな画面全体に配し
細部まで緻密に描きこまれる作風にも圧倒され、
今回お会いする前は、何をお聞きしようか
正直なところ、多少緊張気味で考えていました。
しかしその緊張は、一居さんがお話をされる際の
深く落ち着いたお声を聞くうちに気が付けばなくなり、
ただ絵を間に置いて、ちょっとした宝探しのように
自分の心の中に埋もれたものを探す時間となりました。
それでは、そのお話の中身をご覧下さい。

―画の中のメタリックなものの印象が強いのですが、
このモチーフはずっと描かれているのですか?
「そうですね…これはここ15、6年ほどずっと
モチーフにしています。
それ以前は違うものも描いていたんですよ」
―そうなんですか! ちなみにどんなものを…。
「わりと抽象的な世界を描いていました。
抽象画ですね」
現在描かれているこのモチーフの形を
はっきりと意識されたのは、
阪神大震災が起こった時期だったそうです。
「それ以前もこんな感じのものは
やってたんですけどね。
『ゴミ』を、描いていたんです。
それこそゴミの集積場とか、車のスクラップとかを。
阪神大震災が起きる前にもオウムの事件があったり
世の中の空気が澱んでいた。
ゴミを黄金色に塗ったのは、
そんな感じを皮肉るというかね。
阪神大震災が起こって、
モチーフとしてより意識するようになりました」

阪神大震災が起こる前後の
日本全体が閉塞感に満ちていたような空気のことは
今でも鮮明に思い出せる気がします。
「今も、不安な時期ですよね。
今回のタイトルは
『過去・現在・未来を多視点から見つめて』
としていますが、
時代のそんな不安を見つめたとき、
自分のこういう表現ははまるのではないかと
思ったりして」
今のこの時代を表すイメージとして、
画面全体を無言で埋める黄金色の廃材。
しかし、一居さんの作品の前に実際に立ったとき
画から問題を鋭く突きつけられているようだったり
画が観る者を選んでいるような感じがすることはなく
むしろ、画の世界に誘い込まれているような
何か「親しい」感じをおぼえます。
これは、実際に会場で画を前にされた時に
はじめて実感していただける感覚かもしれません。
たとえば…。
―作品をみていくと、時々画面の中に
マスキングテープや荷札があったりするのですが…。


「こういうものを画の中に入れることで、
自分が関わっている瞬間の位置づけを
作品に入れ込めるというか…。
トリッキーさ、ある種の嘘の世界、
画面の中にそんなたくらみも入れたいと
思っているんです」
面白い話があってね、
と一居さんはお話を続けられます。
「僕が入っている新制作協会の
メインの展覧会が東京であったんですが、
そこに観にこられた方が、僕の絵をじっと見てね。
しばらくすると周りを確認して、誰も見てないと思われたのか
このテープを、そっとはがそうとしてくれるんですよ(笑)
それを僕は後ろから見てて『やった!』と思ってる(笑)」

(さて、お気づきになった方、そうでない方、両方いらっしゃるかもしれません。このテープも荷札も、画の上に後から貼り付けたものではなく、一居さんの筆による「絵」なんです!
驚くほど高い技術で画に仕掛けられた、なんともチャーミングないたずら。)
最初は遠くから全体を眺めて圧倒され、
しかし画家の仕掛けた“いたずら”によって
近寄り難いように見えた画と急に距離が縮まってしまう。
そしてあらためて近くで一居さんの画を見てみると
金属の廃材の中に、「時間の意味」を喚起させる
様々なものが散りばめられているのが見つかるのです。


今回のインタビューには、展覧会を企画したスタッフも同席していました。
(スタッフ)「この画を最初に見たときは、
“過去に置いてきた大切なもの”が
描いてあるのかな、というイメージだったんですよ。
でも、お話を伺っているとそれだけじゃなくて…」
一居さんは、「時間を作品に描きこむこと」について
こんな風に仰っています。
「たとえば今こうしてしゃべったことも、
もう既に、どんどん過去になっていきますね。
そして頭の中には、今これからしゃべろうとする
未来のことがあって…。
そういう瞬間的な過去・現在・未来と、
長いスパンでの過去・現在・未来を両方、
作品の中に入れてみたいんです」

(画の上部のタイプライターと、下部にあるMacのキーボードが、過去と現代をそれぞれ語っています。
「息子が小さいときに遊んでいたファミコンを、描いたこともあるんですよ」)
一居さんとギャラリーを巡りながらお話をして、
私達スタッフがたぶん最も多く画の前で発した言葉は
「なつかしい」でした。
画の中に配された「時間」を語る様々なものたちが
自分の中にとめどなく積もり続ける「時間」のことを、
いつの間にか思いださせてくれたようです。
“「画に描かれた、この場所はどこですか?」と
質問されることはないですか”とお聞きしてみました。
「どこっていうのは…ないですね。
自分の夢の中、国籍も不明な場所。
どこっていう固有名詞がない場所です」

(一居さんの画のところどころに登場するスズメは、一居さんご自身を表しているのだそうです。いろいろな方向を向いているのは未来を見たり、過去を見たりしているということ。この画の世界には他の鳥でなく、なぜかスズメがぴったり!と思います)
今後もしばらくこういう感じの作品を作っていくと思うが、
タイプライター等の具体的なものを描きこむなど
説明的な要素はなくなっていくかもしれないと
予測しています…と、仰る一居さん。
最後に、会場にいらっしゃる方へ
メッセージをいただきました。
「難しい目で見ずに、
気楽に素直に見てほしいなと思いますね。
この画はこんな画だとか、こんな事を描いているとか
枠を設けて見るのではなくて、
素直な気持ちで見てもらえるといいなと思います」

私達は毎日たくさんのことを見聞きし、
新しい一日を迎える度にそれを忘れていきます。
時間をとどめておくことは不可能ですが
そのくりかえしをどこか、
寂しく思う気持ちがあるようにも感じます。
“画の世界にも流行があります。
でも流行に流されないように、
独自の表現を貫くことが一番大事。”
そう仰る一居さんの画には、
現実の表面を忙しく流れていく時間ではなく
自分自身の内側に存在する時間の風景に
観る者を立ち返らせてくれる力があるようです。
冬から春へ。季節が移る時期にぜひご覧ください。

(古いカメラが描かれています。「父親の形見です」とのこと。)
(3月3日(火) 3月6日(金) 3月10日(火)は
休館日です)
ここ数回分のブログの書き出しですが、
表現の違いはあれど大体みんなどこか
「寒くて憂鬱
 」という意味の文章に
」という意味の文章になっていたことに気づき、反省しております。

冒頭からこの元気のなさ、失礼致しました。
でももう春!陽ざしの暖かな日が2日も続けば
ついこの間までの寒さのことを忘れてしまいます。
時間の流れと変化に瞬間ごとに対応していく
人の心と体は本当に不思議です。
さて、今回もわたむき美術ギャラリーの話題。
まさに「時間の流れ」についてのタイトルがついた
絵画展が開催中です。
一居 孝明 洋画展
~過去・現在・未来を
多視点から見つめて~
2月26日(木)~3月15日(日)

長浜市在住の画家
一居孝明(いちいたかあき)さんによる絵画展です。
一居さんのお写真はこちら。

一居さんは、あの佐藤忠良さんや舟越保武さん、
丹下健三さんも所属していたという、
「新制作協会」の会員であり、
数々の受賞歴をお持ちです。
金属の板やパイプを大きな画面全体に配し
細部まで緻密に描きこまれる作風にも圧倒され、
今回お会いする前は、何をお聞きしようか
正直なところ、多少緊張気味で考えていました。
しかしその緊張は、一居さんがお話をされる際の
深く落ち着いたお声を聞くうちに気が付けばなくなり、
ただ絵を間に置いて、ちょっとした宝探しのように
自分の心の中に埋もれたものを探す時間となりました。
それでは、そのお話の中身をご覧下さい。

―画の中のメタリックなものの印象が強いのですが、
このモチーフはずっと描かれているのですか?
「そうですね…これはここ15、6年ほどずっと
モチーフにしています。
それ以前は違うものも描いていたんですよ」
―そうなんですか! ちなみにどんなものを…。
「わりと抽象的な世界を描いていました。
抽象画ですね」
現在描かれているこのモチーフの形を
はっきりと意識されたのは、
阪神大震災が起こった時期だったそうです。
「それ以前もこんな感じのものは
やってたんですけどね。
『ゴミ』を、描いていたんです。
それこそゴミの集積場とか、車のスクラップとかを。
阪神大震災が起きる前にもオウムの事件があったり
世の中の空気が澱んでいた。
ゴミを黄金色に塗ったのは、
そんな感じを皮肉るというかね。
阪神大震災が起こって、
モチーフとしてより意識するようになりました」

阪神大震災が起こる前後の
日本全体が閉塞感に満ちていたような空気のことは
今でも鮮明に思い出せる気がします。
「今も、不安な時期ですよね。
今回のタイトルは
『過去・現在・未来を多視点から見つめて』
としていますが、
時代のそんな不安を見つめたとき、
自分のこういう表現ははまるのではないかと
思ったりして」
今のこの時代を表すイメージとして、
画面全体を無言で埋める黄金色の廃材。
しかし、一居さんの作品の前に実際に立ったとき
画から問題を鋭く突きつけられているようだったり
画が観る者を選んでいるような感じがすることはなく
むしろ、画の世界に誘い込まれているような
何か「親しい」感じをおぼえます。
これは、実際に会場で画を前にされた時に
はじめて実感していただける感覚かもしれません。
たとえば…。
―作品をみていくと、時々画面の中に
マスキングテープや荷札があったりするのですが…。


「こういうものを画の中に入れることで、
自分が関わっている瞬間の位置づけを
作品に入れ込めるというか…。
トリッキーさ、ある種の嘘の世界、
画面の中にそんなたくらみも入れたいと
思っているんです」
面白い話があってね、
と一居さんはお話を続けられます。
「僕が入っている新制作協会の
メインの展覧会が東京であったんですが、
そこに観にこられた方が、僕の絵をじっと見てね。
しばらくすると周りを確認して、誰も見てないと思われたのか
このテープを、そっとはがそうとしてくれるんですよ(笑)
それを僕は後ろから見てて『やった!』と思ってる(笑)」

(さて、お気づきになった方、そうでない方、両方いらっしゃるかもしれません。このテープも荷札も、画の上に後から貼り付けたものではなく、一居さんの筆による「絵」なんです!
驚くほど高い技術で画に仕掛けられた、なんともチャーミングないたずら。)
最初は遠くから全体を眺めて圧倒され、
しかし画家の仕掛けた“いたずら”によって
近寄り難いように見えた画と急に距離が縮まってしまう。
そしてあらためて近くで一居さんの画を見てみると
金属の廃材の中に、「時間の意味」を喚起させる
様々なものが散りばめられているのが見つかるのです。


今回のインタビューには、展覧会を企画したスタッフも同席していました。
(スタッフ)「この画を最初に見たときは、
“過去に置いてきた大切なもの”が
描いてあるのかな、というイメージだったんですよ。
でも、お話を伺っているとそれだけじゃなくて…」
一居さんは、「時間を作品に描きこむこと」について
こんな風に仰っています。
「たとえば今こうしてしゃべったことも、
もう既に、どんどん過去になっていきますね。
そして頭の中には、今これからしゃべろうとする
未来のことがあって…。
そういう瞬間的な過去・現在・未来と、
長いスパンでの過去・現在・未来を両方、
作品の中に入れてみたいんです」

(画の上部のタイプライターと、下部にあるMacのキーボードが、過去と現代をそれぞれ語っています。
「息子が小さいときに遊んでいたファミコンを、描いたこともあるんですよ」)
一居さんとギャラリーを巡りながらお話をして、
私達スタッフがたぶん最も多く画の前で発した言葉は
「なつかしい」でした。
画の中に配された「時間」を語る様々なものたちが
自分の中にとめどなく積もり続ける「時間」のことを、
いつの間にか思いださせてくれたようです。
“「画に描かれた、この場所はどこですか?」と
質問されることはないですか”とお聞きしてみました。
「どこっていうのは…ないですね。
自分の夢の中、国籍も不明な場所。
どこっていう固有名詞がない場所です」

(一居さんの画のところどころに登場するスズメは、一居さんご自身を表しているのだそうです。いろいろな方向を向いているのは未来を見たり、過去を見たりしているということ。この画の世界には他の鳥でなく、なぜかスズメがぴったり!と思います)
今後もしばらくこういう感じの作品を作っていくと思うが、
タイプライター等の具体的なものを描きこむなど
説明的な要素はなくなっていくかもしれないと
予測しています…と、仰る一居さん。
最後に、会場にいらっしゃる方へ
メッセージをいただきました。
「難しい目で見ずに、
気楽に素直に見てほしいなと思いますね。
この画はこんな画だとか、こんな事を描いているとか
枠を設けて見るのではなくて、
素直な気持ちで見てもらえるといいなと思います」

私達は毎日たくさんのことを見聞きし、
新しい一日を迎える度にそれを忘れていきます。
時間をとどめておくことは不可能ですが
そのくりかえしをどこか、
寂しく思う気持ちがあるようにも感じます。
“画の世界にも流行があります。
でも流行に流されないように、
独自の表現を貫くことが一番大事。”
そう仰る一居さんの画には、
現実の表面を忙しく流れていく時間ではなく
自分自身の内側に存在する時間の風景に
観る者を立ち返らせてくれる力があるようです。
冬から春へ。季節が移る時期にぜひご覧ください。

(古いカメラが描かれています。「父親の形見です」とのこと。)
(3月3日(火) 3月6日(金) 3月10日(火)は
休館日です)
2015年02月11日
【開催中】仁志出敬子 コンピューター・グラフィック展
みなさん、こんにちは!
いつの間にか節分が終わり、
“二十四節気”でいえば
「立春」を迎えているはずの今日この頃。
なのに…寒い!寒いです
春はすぐそこ、地面のすぐ下まで来ているのに。
冬の少しだけ寂しい気分と、
春を待ち望むわくわくした気持ちが
入り混じる今の季節の空気感に
とてもよく似合う展覧会をご紹介します。
仁志出敬子
コンピューター・グラフィック展
~心の中の生き物たち~
2月5日(木)~2月22日(日)

動物たち(時々擬人化されていたりします)や、
現実にあるもののようで
どこか非現実的な物たちを、
優しい色使いとユニークな画面構成で描く
仁志出敬子さんの展覧会です。
仁志出敬子さんはこの方です。

まず、「コンピューター・グラフィック」というと、
もしかすると緻密で、メカニックで、先鋭的な作風を
イメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが
仁志出さんの作品は「コンピューター」を
意識させることのない、温かで優しい印象です。
「そうですね、わざと手描きっぽくしている
ところはあります。
パソコンでなめらかな線を描くというのは、
相当熟練していないとできない技術ですね」
コンピューターを習い始めたのは、今から18年前という
仁志出さん。
デザインやテキスタイルのお仕事をされていた関係も
かねて習得された技術ですが、
「コンピューター」を使って作品制作をするということに
特別な意識はなく、
ただ制作に必要な道具として捉えておられるようです。
「パソコンは機械の一種ですよね。
いびつなものを修正できたりもしますが、
パソコンだからといってきちっと線が描けるわけでは
ないので…。
作品をご覧になった方に『切って貼ったんか?』と
訊かれることもあるんですけど(笑)
私自身はこういう描き方が好きなので」
そして、実際に作品を見ていただくと
否応なく惹きつけられるのが、
そこに描かれた、可愛くて、シュールで
不思議な世界です。

「よく『この絵には何か物語があるの?』って
訊かれたりするんですけど、
物語があって、それに絵をつけているんじゃないんです。
最初に視覚的なイメージがあって、絵を描きます。
ストーリーは後からついたりすることもありますが」
“こういうものを描こう”と、頭で考えて決めるより
心に浮かんだ視覚的なイメージを着想にされるという
仁志出さん。
たとえば、こちらの「心の中の生き物」というタイトルが
ついた一連の作品は、
浮かんだイメージをクロッキー帳に描きためておき、
何年か経って掘り起こしたものが描かれています。

物語から生まれる絵ではない。
でも、
「この絵は何かの物語を表わしているんじゃないか…」
そう推測したい方の気持もわかる気がする
というぐらい、
仁志出さんの作品は本当に、
見れば見るほどユニークで興味がつきません。
描かれている動物や人物が、ファンタジックでありながら
互いに絶妙な距離感を保っていることで生まれる
飄々としたユーモアのセンス。
現実からすれば突飛な光景が描かれているのに
絵の中の生き物たちは「いたって平常心」であることが
昔読んだ
“不思議の国のアリス”の世界を思い出させます。

―(笑)面白いです。なぜ動物たちはこのような形に…。
「“メビウスの輪”って、立体的に面白いと思って。
あと、“クラインの壷”ってありますよね。
そういう感じを作品に取り入れたくて。
輪の中に描いたのは、まあ
“うさぎとねこが永遠に追いかけっこをしている”
というか…(笑)」

―これは、左下の人物が“狼男”に
変身している最中かなと思ったのですが。
「いえ、イメージでは
“ピーターパンが影を身に着けている”
みたいな感じだったんですけど…」
―影ですか。そのただならぬ様子に
周りの動物たちも反応していますね。

―木になっている人物もインパクトがありますが、
周りに描かれてあるものも不思議です。
室内は夜のようなのに、窓の外は昼に見えたり。
あと、右側の大きなものさしとか、
左の壁から出ている足とか。
「そうですね…ものさしはあの、やはり背が伸びるということで…(笑)足は、ここにピンクのものが欲しかったんですけど、こう、足があったほうがいいかな…?と(笑)」
―(笑)
派手な見た目で注意をひく形ではなく
画面の細部に目をこらすほど、
じわじわとおかしさがこみあげてくるユーモアを
そなえた仁志出さんの作品たち。
「おかしいですよね。描いているときは別に
笑いを取ろうと思って描いていないんですけど…。
でも、自分でも笑えてきます(笑)」
コンピューターを使用し、独自の世界を描く
仁志出さんの作品群は、
わかりやすい形で「ジャンル分け」ができる
特徴をもたないため
これまで、様々な形に受け取られてきたそうです。

「『イラストレーターですか?』と訊かれることも
あるんですけれど、
“イラストレーター”の定義がわからなくて。
辞書で引くと、
“絵本の挿絵を描く人”“商業的な絵を描く人”
というような意味があったのですが、
この作品は、売るための絵ではないので…」
また、絵の中に登場する動物や人物やものの
大きさが現実とは異なっていたり、
いわゆる「遠近法」に沿っているといえない形で
あることについて、仁志出さんは、
「みんな対等に描いていて、絵の中のどれを強調
したくてというのが、あまりないんです」
と言われます。
あくまで私個人の感想ですが、
その感覚は、仁志出さんがデザインや
テキスタイルの制作を手がけられてきたことに
関係があるのかもと思いました。

最後に、来場される方にメッセージをいただきました。
「具体的で、でも写実的ではないという世界ですので
現実の固定観念にとらわれないで見てほしいと思います。
展示のタイトルにもある“心の中の生き物”として」
インタビュー中の仁志出さんの言葉に
反するようですが
私が仁志出さんの作品を見て連想したものは
「昔の児童書の挿絵作家の作品」でした。
デザイン性に優れながら、温かさとユーモアをそなえ、
決して「物語の説明」にならない豊かな挿絵の世界。
その絵は、読み手の想像力を縛るものではなく、
絵があることで物語は謎を深め、奥行きを増します。
観る側が心を開いてじっと見つめた分だけ、
中にある豊かな世界を教えてくれる、
そんな仁志出さんの作品世界をぜひ会場で
心ゆくまで時間をかけて
ご覧になっていただきたいです。

(仁志出さんの旦那様は2013年にこのギャラリーに出展していただいた仁志出孝春さんです。「ご主人様は作品を見て何と言われますか?」との質問に「こんな発想がいったいどこから来るのか不思議だ、って言います」)
(2月12日(木)・2月17日(火)は休館日です)
いつの間にか節分が終わり、
“二十四節気”でいえば
「立春」を迎えているはずの今日この頃。
なのに…寒い!寒いです

春はすぐそこ、地面のすぐ下まで来ているのに。
冬の少しだけ寂しい気分と、
春を待ち望むわくわくした気持ちが
入り混じる今の季節の空気感に
とてもよく似合う展覧会をご紹介します。
仁志出敬子
コンピューター・グラフィック展
~心の中の生き物たち~
2月5日(木)~2月22日(日)

動物たち(時々擬人化されていたりします)や、
現実にあるもののようで
どこか非現実的な物たちを、
優しい色使いとユニークな画面構成で描く
仁志出敬子さんの展覧会です。
仁志出敬子さんはこの方です。

まず、「コンピューター・グラフィック」というと、
もしかすると緻密で、メカニックで、先鋭的な作風を
イメージされる方もいらっしゃるかもしれませんが
仁志出さんの作品は「コンピューター」を
意識させることのない、温かで優しい印象です。
「そうですね、わざと手描きっぽくしている
ところはあります。
パソコンでなめらかな線を描くというのは、
相当熟練していないとできない技術ですね」
コンピューターを習い始めたのは、今から18年前という
仁志出さん。
デザインやテキスタイルのお仕事をされていた関係も
かねて習得された技術ですが、
「コンピューター」を使って作品制作をするということに
特別な意識はなく、
ただ制作に必要な道具として捉えておられるようです。
「パソコンは機械の一種ですよね。
いびつなものを修正できたりもしますが、
パソコンだからといってきちっと線が描けるわけでは
ないので…。
作品をご覧になった方に『切って貼ったんか?』と
訊かれることもあるんですけど(笑)
私自身はこういう描き方が好きなので」
そして、実際に作品を見ていただくと
否応なく惹きつけられるのが、
そこに描かれた、可愛くて、シュールで
不思議な世界です。

「よく『この絵には何か物語があるの?』って
訊かれたりするんですけど、
物語があって、それに絵をつけているんじゃないんです。
最初に視覚的なイメージがあって、絵を描きます。
ストーリーは後からついたりすることもありますが」
“こういうものを描こう”と、頭で考えて決めるより
心に浮かんだ視覚的なイメージを着想にされるという
仁志出さん。
たとえば、こちらの「心の中の生き物」というタイトルが
ついた一連の作品は、
浮かんだイメージをクロッキー帳に描きためておき、
何年か経って掘り起こしたものが描かれています。

物語から生まれる絵ではない。
でも、
「この絵は何かの物語を表わしているんじゃないか…」
そう推測したい方の気持もわかる気がする
というぐらい、
仁志出さんの作品は本当に、
見れば見るほどユニークで興味がつきません。
描かれている動物や人物が、ファンタジックでありながら
互いに絶妙な距離感を保っていることで生まれる
飄々としたユーモアのセンス。
現実からすれば突飛な光景が描かれているのに
絵の中の生き物たちは「いたって平常心」であることが
昔読んだ
“不思議の国のアリス”の世界を思い出させます。

―(笑)面白いです。なぜ動物たちはこのような形に…。
「“メビウスの輪”って、立体的に面白いと思って。
あと、“クラインの壷”ってありますよね。
そういう感じを作品に取り入れたくて。
輪の中に描いたのは、まあ
“うさぎとねこが永遠に追いかけっこをしている”
というか…(笑)」

―これは、左下の人物が“狼男”に
変身している最中かなと思ったのですが。
「いえ、イメージでは
“ピーターパンが影を身に着けている”
みたいな感じだったんですけど…」
―影ですか。そのただならぬ様子に
周りの動物たちも反応していますね。

―木になっている人物もインパクトがありますが、
周りに描かれてあるものも不思議です。
室内は夜のようなのに、窓の外は昼に見えたり。
あと、右側の大きなものさしとか、
左の壁から出ている足とか。
「そうですね…ものさしはあの、やはり背が伸びるということで…(笑)足は、ここにピンクのものが欲しかったんですけど、こう、足があったほうがいいかな…?と(笑)」
―(笑)
派手な見た目で注意をひく形ではなく
画面の細部に目をこらすほど、
じわじわとおかしさがこみあげてくるユーモアを
そなえた仁志出さんの作品たち。
「おかしいですよね。描いているときは別に
笑いを取ろうと思って描いていないんですけど…。
でも、自分でも笑えてきます(笑)」
コンピューターを使用し、独自の世界を描く
仁志出さんの作品群は、
わかりやすい形で「ジャンル分け」ができる
特徴をもたないため
これまで、様々な形に受け取られてきたそうです。

「『イラストレーターですか?』と訊かれることも
あるんですけれど、
“イラストレーター”の定義がわからなくて。
辞書で引くと、
“絵本の挿絵を描く人”“商業的な絵を描く人”
というような意味があったのですが、
この作品は、売るための絵ではないので…」
また、絵の中に登場する動物や人物やものの
大きさが現実とは異なっていたり、
いわゆる「遠近法」に沿っているといえない形で
あることについて、仁志出さんは、
「みんな対等に描いていて、絵の中のどれを強調
したくてというのが、あまりないんです」
と言われます。
あくまで私個人の感想ですが、
その感覚は、仁志出さんがデザインや
テキスタイルの制作を手がけられてきたことに
関係があるのかもと思いました。

最後に、来場される方にメッセージをいただきました。
「具体的で、でも写実的ではないという世界ですので
現実の固定観念にとらわれないで見てほしいと思います。
展示のタイトルにもある“心の中の生き物”として」
インタビュー中の仁志出さんの言葉に
反するようですが
私が仁志出さんの作品を見て連想したものは
「昔の児童書の挿絵作家の作品」でした。
デザイン性に優れながら、温かさとユーモアをそなえ、
決して「物語の説明」にならない豊かな挿絵の世界。
その絵は、読み手の想像力を縛るものではなく、
絵があることで物語は謎を深め、奥行きを増します。
観る側が心を開いてじっと見つめた分だけ、
中にある豊かな世界を教えてくれる、
そんな仁志出さんの作品世界をぜひ会場で
心ゆくまで時間をかけて
ご覧になっていただきたいです。

(仁志出さんの旦那様は2013年にこのギャラリーに出展していただいた仁志出孝春さんです。「ご主人様は作品を見て何と言われますか?」との質問に「こんな発想がいったいどこから来るのか不思議だ、って言います」)
(2月12日(木)・2月17日(火)は休館日です)
2015年01月18日
【開催中】ミゲル・リマ 絵画展
みなさん、こんにちは! 毎日寒いですね~。
毎日寒いですね~。
朝起きると外が銀世界ということもしばしば。
今年の冬は暖冬という予報だったんじゃ・・・?
そしてインフルエンザが本格的に流行中とのこと。
みなさん温かくて美味しいものをたっぷり食べて
ウイルスを撃退しましょうね!
さて、わたむきホール虹の美術ギャラリーは今
鮮やかなアンデスの色彩に彩られています。
南米ボリビア出身で、先住民族「アイマラ族」の
血を引くアーティスト、そして教育家でもある
ミゲル・リマさんの絵画展が開催中なのです。
ミゲル・リマ絵画展
~チチカカ湖の色彩~
1月16日(金)~2月1日(日)

リマさんは2013年に初めて日本の土を踏み
2014年にあらためて来日、
現在、日野町で暮らされています。

日野町ではすっかり有名人のリマさん。
日本語は勉強中とのことですが、穏やかな人柄と、
奥様の浦田広美さんの通訳で自然に地域に溶け込み
様々なイベントや催しに引っ張りだこの日々を
送っていらっしゃいます。
そんなリマさんが昨年から描き始めたのが
自らのルーツ、アイマラ族の暮らしや神話を描いた
色鮮やかな色鉛筆画。
神秘的で愛らしい、不思議な魅力を持つリマさんの絵は
今、静かに様々な人の心をとらえています。
また今回は絵の他に、アイマラ文化を伝えるいくつかの
ものを同時に出展していただきました。
今回の展示について、リマさんと浦田さんに伺ったお話
をお楽しみ下さい!
会場に入ると、
最初にどうしても目についてしまうものが…。
動物の頭のよう。かなりのインパクトです。

(浦田さん)「アンデスの神話の動物のお面です。
アンデスの神話を伝えるため、日本で劇をした時に
作ったものです。
風船を膨らませ、新聞紙やキッチンペーパーを上に
貼って、乾いたら風船を取り除きます。
スペイン語ではパペルマシェ(Papelmashe)といいます」

(神話のタイトルは「キツネと娘」…昔あるところに娘がいた。娘は鳥の王様コンドルに求婚されたが、「他にもっといい人がいるかもしれない」と断る。様々な求婚者を断り続けた娘はついに自分を幸せにしてくれそうなキツネと結婚するが、キツネは嘘つきで、だまされて大変に苦労の多い人生を送った…というお話)
(浦田さん)「またこれは、チチカカ湖の神話を紹介した
いということで、ミゲルがひらがなで字を書きました」

(神話はチチカカ湖の名前の由来にまつわるもの。「チチカカ」とはそういう意味だったのかとびっくりする内容です)
様々な神話が遍在する南米の大地。
そこに暮らす人々の世界には、神話と同様に
豊かな「色」が溢れているようです。
―やはり、違う国に育ってきた方の色使いですね。
日本人は鮮やかな色をたくさん組み合わせると
いうことがないので…。
どうしてもどこかに中間色が入ってしまいます。
(リマさん)「ああ、そうですね。日本人の作家の絵を見る
と、とても感覚が繊細だということを感じます」
(浦田さん)「向こうの人は、(周りの目を気にするよりも)
“自分がこの色を好きだから”という理由で色を選ん
で組み合わせるんですね。
ボリビアでは人々がよく織物をやるんですが、
とにかく色を使うのが楽しいようです。
特に最近は化学染料が使えるようになり、
糸が簡単に染められるのでより楽しいみたいです」

(展示物である南米の楽器の下に敷かれているのもボリビアの織物です。鮮やかな水色、モスグリーンにピンク…。日本人には大胆な色の配列ですが、派手でトゥーマッチな印象は受けないのが不思議。)
さて、話題はいよいよ絵に移っていきます。
リマさんの絵は、古くから民族に伝承される図案・絵柄と
リマさんが考えたオリジナルの絵のミックスだそうです。
下のキャプションは絵の中の神話の場面や、アイマラの
人々の生活や儀式の場面を説明しており、
これも伝承されている話を
リマさんの言葉で語りなおしています。
(浦田さん)「たとえば絵の中にいるコンドルは
ナスカの地上絵でも見られる古い図案です。
星(十字架のように見えるもの)も古い図案ですね。
同時に、絵にいろいろな遊び心もこめていて、
よく見ると絵の中にいろいろな動物が隠れているんです」

(髪の毛?の先が鳥のくちばしのよう。他にもたくさんの絵にいろんな動物が隠れています。探してみてください!)
(浦田さん)「あらゆる場所に動物が遍在するというのは、アイマラの人独特の世界観かなと私は思っているのですが」
(リマさん)「自分の描く山には精霊が宿っています。」

(山にも動物。わかりますか?単に動物が暮らすだけではなく精霊も宿っているという意味で、パズルのピースのように動物を描きこまれているのでしょうか)
ここまでずっとお二人のお話を伺ってきて、
ひとつの疑問が浮かびました。
自然と暮らし何千年もかけて培ってきた美しい世界観と
独特の生活様式を持つアンデスの人々。
しかし美しくてもそれはあくまで
「あたりまえの日常」のはずです。
地球半周分も離れた地の外国人=私達日本人に
「自分たちの文化」を伝えようとされる理由は
いったい何なのでしょうか?
(浦田さん)「あたりまえ?うーん…。」
―“あたりまえ”ではないのですか?
「ここに描かれている絵は確かにアイマラの原風景です。
しかしミゲルはここで育ったわけではないんです。
彼はもちろんアイマラ族ですが、彼のお父さんも、おじいさんも、町に出て生活をしていました。ミゲルは町で育ったんですね。
そして大きくなってから、自分のルーツを知りたくて
アイマラ族の住む場所に通ったんです」

「もちろん子どもの頃から楽器を演奏するなど
お家にアイマラとしての習慣はあったので、
彼にはアイマラ族のアイデンティティがあるんです。
でもアイマラ族のいろいろな人の話を聞いたり、
アイマラの音楽を勉強したりしたのは
日本にアイマラ文化を紹介するのがきっかけでした。
彼はずっと音楽をやっていましたが、
前は外国の音楽に興味を持っていて、
自分のルーツとなる音楽をやりだしたのは
最近のことなんです。」
―リマさんは30代後半でいらっしゃいますね。
生まれ育った背景は全く違いますが、
同世代として、その感覚がよくわかる気がします。
自分たちの世代から、日本でも昔から受け継がれて
きたものが、ぷつんと途切れてしまっている感じが
あるのです。
(浦田さん)「そうですね。同じだと思います。
今回はアイマラに伝わる楽器も展示していますが、
この楽器を使った音楽も、若い世代に受け継がれる
ことが少なくなり、演奏できるのは高齢の人たち
ばかりになっていますので、
世代的に危機感を感じていると思います」

日本で問題になっていることが、遠いアンデスの地でも
同様に問題であることに驚くとともに、
それぞれの世代で感じることは、国境を越えてどこか
通じる部分があるのかもしれないと思いました。
最後に、リマさんより来場される皆様へ向けて
メッセージをいただきました。
「絵を通してアイマラの文化を知ってほしいです。
また、描いている風景を見てほしいと思います」
厳しい高地で、何千年もかけて織物を織るように
作られてきた暮らしの形。
そこには、目に見えない神々や音楽も、目に見える
ものと変わることなく等しく織り込まれています。
人が自然と生きることでしか生まれることのない
豊かさの形を、ぜひ会場でご覧になってください。

(1月20日(火)・1月27日(火)は休館日です)
 毎日寒いですね~。
毎日寒いですね~。朝起きると外が銀世界ということもしばしば。
今年の冬は暖冬という予報だったんじゃ・・・?
そしてインフルエンザが本格的に流行中とのこと。
みなさん温かくて美味しいものをたっぷり食べて
ウイルスを撃退しましょうね!
さて、わたむきホール虹の美術ギャラリーは今
鮮やかなアンデスの色彩に彩られています。
南米ボリビア出身で、先住民族「アイマラ族」の
血を引くアーティスト、そして教育家でもある
ミゲル・リマさんの絵画展が開催中なのです。
ミゲル・リマ絵画展
~チチカカ湖の色彩~
1月16日(金)~2月1日(日)

リマさんは2013年に初めて日本の土を踏み
2014年にあらためて来日、
現在、日野町で暮らされています。

日野町ではすっかり有名人のリマさん。
日本語は勉強中とのことですが、穏やかな人柄と、
奥様の浦田広美さんの通訳で自然に地域に溶け込み
様々なイベントや催しに引っ張りだこの日々を
送っていらっしゃいます。
そんなリマさんが昨年から描き始めたのが
自らのルーツ、アイマラ族の暮らしや神話を描いた
色鮮やかな色鉛筆画。
神秘的で愛らしい、不思議な魅力を持つリマさんの絵は
今、静かに様々な人の心をとらえています。
また今回は絵の他に、アイマラ文化を伝えるいくつかの
ものを同時に出展していただきました。
今回の展示について、リマさんと浦田さんに伺ったお話
をお楽しみ下さい!
会場に入ると、
最初にどうしても目についてしまうものが…。
動物の頭のよう。かなりのインパクトです。

(浦田さん)「アンデスの神話の動物のお面です。
アンデスの神話を伝えるため、日本で劇をした時に
作ったものです。
風船を膨らませ、新聞紙やキッチンペーパーを上に
貼って、乾いたら風船を取り除きます。
スペイン語ではパペルマシェ(Papelmashe)といいます」

(神話のタイトルは「キツネと娘」…昔あるところに娘がいた。娘は鳥の王様コンドルに求婚されたが、「他にもっといい人がいるかもしれない」と断る。様々な求婚者を断り続けた娘はついに自分を幸せにしてくれそうなキツネと結婚するが、キツネは嘘つきで、だまされて大変に苦労の多い人生を送った…というお話)
(浦田さん)「またこれは、チチカカ湖の神話を紹介した
いということで、ミゲルがひらがなで字を書きました」

(神話はチチカカ湖の名前の由来にまつわるもの。「チチカカ」とはそういう意味だったのかとびっくりする内容です)
様々な神話が遍在する南米の大地。
そこに暮らす人々の世界には、神話と同様に
豊かな「色」が溢れているようです。
―やはり、違う国に育ってきた方の色使いですね。
日本人は鮮やかな色をたくさん組み合わせると
いうことがないので…。
どうしてもどこかに中間色が入ってしまいます。
(リマさん)「ああ、そうですね。日本人の作家の絵を見る
と、とても感覚が繊細だということを感じます」
(浦田さん)「向こうの人は、(周りの目を気にするよりも)
“自分がこの色を好きだから”という理由で色を選ん
で組み合わせるんですね。
ボリビアでは人々がよく織物をやるんですが、
とにかく色を使うのが楽しいようです。
特に最近は化学染料が使えるようになり、
糸が簡単に染められるのでより楽しいみたいです」

(展示物である南米の楽器の下に敷かれているのもボリビアの織物です。鮮やかな水色、モスグリーンにピンク…。日本人には大胆な色の配列ですが、派手でトゥーマッチな印象は受けないのが不思議。)
さて、話題はいよいよ絵に移っていきます。
リマさんの絵は、古くから民族に伝承される図案・絵柄と
リマさんが考えたオリジナルの絵のミックスだそうです。
下のキャプションは絵の中の神話の場面や、アイマラの
人々の生活や儀式の場面を説明しており、
これも伝承されている話を
リマさんの言葉で語りなおしています。
(浦田さん)「たとえば絵の中にいるコンドルは
ナスカの地上絵でも見られる古い図案です。
星(十字架のように見えるもの)も古い図案ですね。
同時に、絵にいろいろな遊び心もこめていて、
よく見ると絵の中にいろいろな動物が隠れているんです」

(髪の毛?の先が鳥のくちばしのよう。他にもたくさんの絵にいろんな動物が隠れています。探してみてください!)
(浦田さん)「あらゆる場所に動物が遍在するというのは、アイマラの人独特の世界観かなと私は思っているのですが」
(リマさん)「自分の描く山には精霊が宿っています。」

(山にも動物。わかりますか?単に動物が暮らすだけではなく精霊も宿っているという意味で、パズルのピースのように動物を描きこまれているのでしょうか)
ここまでずっとお二人のお話を伺ってきて、
ひとつの疑問が浮かびました。
自然と暮らし何千年もかけて培ってきた美しい世界観と
独特の生活様式を持つアンデスの人々。
しかし美しくてもそれはあくまで
「あたりまえの日常」のはずです。
地球半周分も離れた地の外国人=私達日本人に
「自分たちの文化」を伝えようとされる理由は
いったい何なのでしょうか?
(浦田さん)「あたりまえ?うーん…。」
―“あたりまえ”ではないのですか?
「ここに描かれている絵は確かにアイマラの原風景です。
しかしミゲルはここで育ったわけではないんです。
彼はもちろんアイマラ族ですが、彼のお父さんも、おじいさんも、町に出て生活をしていました。ミゲルは町で育ったんですね。
そして大きくなってから、自分のルーツを知りたくて
アイマラ族の住む場所に通ったんです」

「もちろん子どもの頃から楽器を演奏するなど
お家にアイマラとしての習慣はあったので、
彼にはアイマラ族のアイデンティティがあるんです。
でもアイマラ族のいろいろな人の話を聞いたり、
アイマラの音楽を勉強したりしたのは
日本にアイマラ文化を紹介するのがきっかけでした。
彼はずっと音楽をやっていましたが、
前は外国の音楽に興味を持っていて、
自分のルーツとなる音楽をやりだしたのは
最近のことなんです。」
―リマさんは30代後半でいらっしゃいますね。
生まれ育った背景は全く違いますが、
同世代として、その感覚がよくわかる気がします。
自分たちの世代から、日本でも昔から受け継がれて
きたものが、ぷつんと途切れてしまっている感じが
あるのです。
(浦田さん)「そうですね。同じだと思います。
今回はアイマラに伝わる楽器も展示していますが、
この楽器を使った音楽も、若い世代に受け継がれる
ことが少なくなり、演奏できるのは高齢の人たち
ばかりになっていますので、
世代的に危機感を感じていると思います」

日本で問題になっていることが、遠いアンデスの地でも
同様に問題であることに驚くとともに、
それぞれの世代で感じることは、国境を越えてどこか
通じる部分があるのかもしれないと思いました。
最後に、リマさんより来場される皆様へ向けて
メッセージをいただきました。
「絵を通してアイマラの文化を知ってほしいです。
また、描いている風景を見てほしいと思います」
厳しい高地で、何千年もかけて織物を織るように
作られてきた暮らしの形。
そこには、目に見えない神々や音楽も、目に見える
ものと変わることなく等しく織り込まれています。
人が自然と生きることでしか生まれることのない
豊かさの形を、ぜひ会場でご覧になってください。

(1月20日(火)・1月27日(火)は休館日です)
2014年12月12日
【開催中】中島陽子 書道展 墨を彩る~あるがままに~
みなさん、こんにちは
前回の更新からかなり日が空いてしまい、
どことなく後ろめたい気持ちでこの文章を綴っています
それにしても、この寒さ!
みなさんインフルエンザには気を付けてくださいね。
さて、ブログを更新しなかった間のわたむきホール虹は
停止していたわけではありません。
ひとつのステージが終わると、また次のステージへ。
文化ホールである限り終わることのないサイクルを
今年もずっと続けてきました。
そんなわたむきホール虹、そして、
一年間立ち止まることなく頑張り続けてきた
すべての皆様にぴったりの展示が
美術ギャラリーにて開催中です。
中島陽子 書道展
墨を彩る~あるがままに~
12月11日(木)~12月28日(日)

東近江市在住の書道家として活躍される
中島陽子さんの展覧会です。
書道家として、地域に溶け込んだ活動をされてきた中島さん。
有名な八日市の百畳の大凧(!)を
中島さんの書が飾ったこともあります。
中島さんのお写真はこちら。

ブログ担当スタッフの私は、地域の書道家の方として
以前から中島陽子さんのお名前を知っていましたが、
お会いするのははじめてです。
どんな方だろう・・・と思ってお話を伺ったそのお人柄は
こう表現して差支えなければ、大変にチャーミングでした。
ご自身の作品を説明されるその合間に、何度も
「ああ、変なことを言ってしまったかも。
書かないでくださいね~」
とおっしゃるところなど・・・。
(※念のため、何も変なことは言われていませんでした)
まず、その中島陽子さんのチャーミングなお人柄を
思っていただきながら、
以下のレポートをお読みいただければ嬉しいです。
では、さっそくどうぞ!
展示会場に入ると、最初に目を引くのが
この大作です。

(中島さん)「これは『一陽来復(いちようらいふく)』と書いてあります。
悪いことがあっても、今度は良いことがありますようにという、陰と陽の考えかたですね。赤と黒で陰陽を表してみました。
新年に向けて、リセットしましょうという気持ちで」
リセット。いいですね。
下を向いていた心も前を向くことを思い出しそうです。
新年を前に、これこそまさに「言祝ぎ(ことほぎ)」。
言葉での祝福が私たちを出迎えてくれるような作品です。
中島さんは今回の展示に、
新たな年を迎えようとする今の時期にふさわしい
作品を選んでくださいました。

『早春の海に船を出して、鯛を見た』
茨木のり子さんの“鯛”という詩が書かれた作品です。
書を見るだけで、
何かいいことがありそうな気持ちになります。
そして作品全体から、紛れもない春の海の気配を
感じることができるのが不思議です。

こちらの写真、中央の作品は、
中国の漢詩を書にしたもの。
作者が“宮殿の景色”を見て感銘を受け
その様子を
「宮殿や楼閣は建物が複雑にめぐり
草や木が盛んに生い茂っているので
高く険しい山や深い谷のよう。
その勢いは五色の雉(きじ)が
飛んでいるように驚く」
と表現している詩なのだそうです。
これもユニークで華やかで、新年を祝うのには
ふさわしい作品ですね。
さて、ここまで中島さんの作品を見てきて
気づいたことがひとつ。
作品によって、書体や表現方法が
ひとつひとつ違うのです。
“書”とは、こんなに自在で豊かな表現手段なのかと
驚きを覚えます。

(ここ日野町が“蒲生野”であることにちなみ、額田王の有名な「あかねさす…」の歌を出展してくださいました。
先ほどの「宮殿」の書とは表情がまったく違う、女性の手で綴られた恋文にふさわしい書体)
―書体が作品ごとに違いますね。
「そうですね。作品展をするときには
そのほうがいいかな、と。
ひとつひとつは稚拙なものなのですが、
それでも、見ていただく方にとっては
色々あったほうが楽しんでいただけるのでは
ないかと思いまして」
中島さんが言われるとおり、
私のように、普段ほぼまったくと言えるほど
書に接することがない者にとっては、
ギャラリーが本当に新鮮で楽しい空間に
感じられます。
「あと…作品展としてお見せするかぎりは
並べて見て心地いいレイアウトのバランス、
全体にまとまってるかな、ごちゃごちゃして
ないかな、とか、そういうことは考えますね」

こちらの作品は、『雪月花』。
「“雪月花”という言葉はオールシーズン使えるので…。
これは、屛風屋さんに『何か書いて』と言われて
書いたんですよ。
今は旅館の玄関に置いてもらったりしています」
―この屛風で迎えられたら、外国人の方なんか
喜ばれるのではないですか?
「そうですね。外国の方に喜んでもらってるみたいです。
“書”って、海外の方には意味はわからなくても
何か美しいとかかっこいいとか思ってもらえる
みたいですね」
中島さんとお話ししていると、
“書”というものが急に自分と親しくなったような
(まったく心得はないのに)、そんな気持ちになります。
「いろいろな人に喜んでもらえる書でありたい。
だからあんまり難しい意味をこめたりしない」
そうおっしゃる中島さんの書の世界は、
それを見る全ての人に優しく開かれているようです。

(手前は金子みすずさんの詩、奥は草野心平さんの詩だそうです)
書に向かいはじめて30年という中島さん。
書の魅力とは中島さんにとって何なのでしょうか。
「うーん…。気が付けば30年という感じなんですよ。
書をやっていることで、色々なご縁をいただいて、
書がいつの間にか自分の中のツールに
なっていたんですね。
自分の人生が何もしていないよりは広がったし、
地域貢献のようなこともさせていただいています」
なかなか展覧会に出しても、
賞をいただいたりすることはできないんですけど・・・
と、中島さんは笑われますが、
“地域の書道家”として町に美しい書を届け、
様々な人の目を喜ばせる中島さんの在り方は、
芸術家として、確かな幸福の形を築いていらっしゃる
ように思えます。
“書を通じて自然に人や町とつながること”
それは、無理やり手に入れようとしても、
決して手に入らない
貴重な幸福の形なのではと感じました。

書の魅力について、最後に中島さんは
大切なことを語ってくださいました。
「今回の展示のタイトルは
“墨を彩る~あるがままに~”としていますが
“彩る”ということ、これが、
私が書で目指していることなんです。
墨なのに、“彩る”という、
この意味合いを、感じてもらえるかな?
感じてもらえるといいな、と思って
作品を制作しました。
これは、いくら言葉で説明しようとしても
核心に迫るほど伝えたいことから離れてしまう
ことなんです。
だから、会場に来て、様々な書を
実際に見ていただければと思っています」
ほんの200年ほど前まで、
日本では、言葉はほとんどすべて
筆と墨を用いて書かれていました。
現在では遠い感覚になってしまったようですが、
呼吸を整え、筆で文字を書くとき、
その字には詩や歌や色彩のようなものが
書き手の意図をこえ、宿ってしまうことが
当たりまえだったのかもしれません。
そんな書の魅力を、ぜひ会場にて
たっぷりと感じていただきたいと思います。
(12月16日(火)、24日(水)25日(木)は休館日です)
―お詫び―
2014年11月1日発行の当ホール情報誌
「虹のたよりvol.148」におきまして
「ギャラリーインフォメーション」欄で紹介した
中島陽子さんのお名前の表記が「中島よう子」と
なっておりました。
お詫びして訂正いたします。

前回の更新からかなり日が空いてしまい、
どことなく後ろめたい気持ちでこの文章を綴っています

それにしても、この寒さ!
みなさんインフルエンザには気を付けてくださいね。
さて、ブログを更新しなかった間のわたむきホール虹は
停止していたわけではありません。
ひとつのステージが終わると、また次のステージへ。
文化ホールである限り終わることのないサイクルを
今年もずっと続けてきました。
そんなわたむきホール虹、そして、
一年間立ち止まることなく頑張り続けてきた
すべての皆様にぴったりの展示が
美術ギャラリーにて開催中です。
中島陽子 書道展
墨を彩る~あるがままに~
12月11日(木)~12月28日(日)

東近江市在住の書道家として活躍される
中島陽子さんの展覧会です。
書道家として、地域に溶け込んだ活動をされてきた中島さん。
有名な八日市の百畳の大凧(!)を
中島さんの書が飾ったこともあります。
中島さんのお写真はこちら。

ブログ担当スタッフの私は、地域の書道家の方として
以前から中島陽子さんのお名前を知っていましたが、
お会いするのははじめてです。
どんな方だろう・・・と思ってお話を伺ったそのお人柄は
こう表現して差支えなければ、大変にチャーミングでした。
ご自身の作品を説明されるその合間に、何度も
「ああ、変なことを言ってしまったかも。
書かないでくださいね~」
とおっしゃるところなど・・・。
(※念のため、何も変なことは言われていませんでした)
まず、その中島陽子さんのチャーミングなお人柄を
思っていただきながら、
以下のレポートをお読みいただければ嬉しいです。
では、さっそくどうぞ!
展示会場に入ると、最初に目を引くのが
この大作です。

(中島さん)「これは『一陽来復(いちようらいふく)』と書いてあります。
悪いことがあっても、今度は良いことがありますようにという、陰と陽の考えかたですね。赤と黒で陰陽を表してみました。
新年に向けて、リセットしましょうという気持ちで」
リセット。いいですね。
下を向いていた心も前を向くことを思い出しそうです。
新年を前に、これこそまさに「言祝ぎ(ことほぎ)」。
言葉での祝福が私たちを出迎えてくれるような作品です。
中島さんは今回の展示に、
新たな年を迎えようとする今の時期にふさわしい
作品を選んでくださいました。

『早春の海に船を出して、鯛を見た』
茨木のり子さんの“鯛”という詩が書かれた作品です。
書を見るだけで、
何かいいことがありそうな気持ちになります。
そして作品全体から、紛れもない春の海の気配を
感じることができるのが不思議です。

こちらの写真、中央の作品は、
中国の漢詩を書にしたもの。
作者が“宮殿の景色”を見て感銘を受け
その様子を
「宮殿や楼閣は建物が複雑にめぐり
草や木が盛んに生い茂っているので
高く険しい山や深い谷のよう。
その勢いは五色の雉(きじ)が
飛んでいるように驚く」
と表現している詩なのだそうです。
これもユニークで華やかで、新年を祝うのには
ふさわしい作品ですね。
さて、ここまで中島さんの作品を見てきて
気づいたことがひとつ。
作品によって、書体や表現方法が
ひとつひとつ違うのです。
“書”とは、こんなに自在で豊かな表現手段なのかと
驚きを覚えます。

(ここ日野町が“蒲生野”であることにちなみ、額田王の有名な「あかねさす…」の歌を出展してくださいました。
先ほどの「宮殿」の書とは表情がまったく違う、女性の手で綴られた恋文にふさわしい書体)
―書体が作品ごとに違いますね。
「そうですね。作品展をするときには
そのほうがいいかな、と。
ひとつひとつは稚拙なものなのですが、
それでも、見ていただく方にとっては
色々あったほうが楽しんでいただけるのでは
ないかと思いまして」
中島さんが言われるとおり、
私のように、普段ほぼまったくと言えるほど
書に接することがない者にとっては、
ギャラリーが本当に新鮮で楽しい空間に
感じられます。
「あと…作品展としてお見せするかぎりは
並べて見て心地いいレイアウトのバランス、
全体にまとまってるかな、ごちゃごちゃして
ないかな、とか、そういうことは考えますね」

こちらの作品は、『雪月花』。
「“雪月花”という言葉はオールシーズン使えるので…。
これは、屛風屋さんに『何か書いて』と言われて
書いたんですよ。
今は旅館の玄関に置いてもらったりしています」
―この屛風で迎えられたら、外国人の方なんか
喜ばれるのではないですか?
「そうですね。外国の方に喜んでもらってるみたいです。
“書”って、海外の方には意味はわからなくても
何か美しいとかかっこいいとか思ってもらえる
みたいですね」
中島さんとお話ししていると、
“書”というものが急に自分と親しくなったような
(まったく心得はないのに)、そんな気持ちになります。
「いろいろな人に喜んでもらえる書でありたい。
だからあんまり難しい意味をこめたりしない」
そうおっしゃる中島さんの書の世界は、
それを見る全ての人に優しく開かれているようです。

(手前は金子みすずさんの詩、奥は草野心平さんの詩だそうです)
書に向かいはじめて30年という中島さん。
書の魅力とは中島さんにとって何なのでしょうか。
「うーん…。気が付けば30年という感じなんですよ。
書をやっていることで、色々なご縁をいただいて、
書がいつの間にか自分の中のツールに
なっていたんですね。
自分の人生が何もしていないよりは広がったし、
地域貢献のようなこともさせていただいています」
なかなか展覧会に出しても、
賞をいただいたりすることはできないんですけど・・・
と、中島さんは笑われますが、
“地域の書道家”として町に美しい書を届け、
様々な人の目を喜ばせる中島さんの在り方は、
芸術家として、確かな幸福の形を築いていらっしゃる
ように思えます。
“書を通じて自然に人や町とつながること”
それは、無理やり手に入れようとしても、
決して手に入らない
貴重な幸福の形なのではと感じました。

書の魅力について、最後に中島さんは
大切なことを語ってくださいました。
「今回の展示のタイトルは
“墨を彩る~あるがままに~”としていますが
“彩る”ということ、これが、
私が書で目指していることなんです。
墨なのに、“彩る”という、
この意味合いを、感じてもらえるかな?
感じてもらえるといいな、と思って
作品を制作しました。
これは、いくら言葉で説明しようとしても
核心に迫るほど伝えたいことから離れてしまう
ことなんです。
だから、会場に来て、様々な書を
実際に見ていただければと思っています」
ほんの200年ほど前まで、
日本では、言葉はほとんどすべて
筆と墨を用いて書かれていました。
現在では遠い感覚になってしまったようですが、
呼吸を整え、筆で文字を書くとき、
その字には詩や歌や色彩のようなものが
書き手の意図をこえ、宿ってしまうことが
当たりまえだったのかもしれません。
そんな書の魅力を、ぜひ会場にて
たっぷりと感じていただきたいと思います。
(12月16日(火)、24日(水)25日(木)は休館日です)
―お詫び―
2014年11月1日発行の当ホール情報誌
「虹のたよりvol.148」におきまして
「ギャラリーインフォメーション」欄で紹介した
中島陽子さんのお名前の表記が「中島よう子」と
なっておりました。
お詫びして訂正いたします。
2014年10月02日
【開催中】杉野 由佳 細密画展
みなさん、こんにちは
アジア大会、ご覧になられていますか?
滋賀出身のフェンシング太田選手、
シンクロ乾選手の活躍もとても嬉しかったのですが、
個人的には男女ともに日本選手が銅メダルを獲得した
「トランポリン」に魅せられてしまいました
空中での的確で美しい身体の動き、素敵ですよね。
今後注目していきたい競技になりました!
さて、秋のわたむき美術ギャラリー、
新しい展示がはじまりました。
杉野 由佳 細密画展
~身近な自然と
出会える瞬間~
9月26日(金)~10月13日(月・祝)

高校卒業後、京都の専門学校で自然環境について学び、
野山でのフィールドワークの際、植物や生物の絵を描き
はじめたことから細密画を手がけるようになった、
杉野由佳さんの展覧会です。
現在はWWF(世界自然保護基金)ジャパンの会報に
絵を描くお仕事もされています。
杉野由佳さんはこの方です。

現在、小学校6年生になる息子さんのお母様でもある
杉野さん。
しかし、植物や小さな生き物の話になると、
好奇心に満ちた探検家のような、活き活きとした
表情になられるのがとても印象的でした。
そして杉野さんからお聞きする自然のお話が、
とにかく面白いのです。
私たちの足元に広がる「小さな世界」の不思議。
さっそくお届けしたいと思います!

まずは、「自然を写実的に描く」ということについて。
春に開催した、バラのボタニカルアート展の作家、
須田久仁子さんにお伺いしたことですが、
カメラのない時代には、植物や生物の絵が、
自然を研究するうえで、非常に重要だったそうです。
(杉野さん)「そうです。有名な話ではイギリスのキュー
ガーデンに、お抱えの絵師がいたというのがあります。
日本では、シーボルトが日本の絵師に、写実的な技法を伝えたといわれています。
植物の研究・観察のために描く絵としては、
“生態的”に描く方法と“標本的”に描く方法があります。
どちらにしても大切なことは
“嘘を描かない”ことなんですね」
“嘘を描かない”とは、
目の前にある対象そのものを忠実に描くということ、
と、杉野さんはひとまず定義されます。

(“ツユクサ”花の部分を抜き出して拡大してあります。雄しべと雌しべの長さがこんなに違うことに、今まで気づきませんでした。)
「でも、自然のものって個体差に幅があるんですよ。
普通、花びらが6枚の花なのに7枚ついているものと
遭遇してしまったら、
自分にその花の知識がないと、そのまま描いてしまう。
嘘をつかないとはいっても、絵にするときは、
その対象の“典型的な”形を描かないといけないので。
だから、絵を描く前にはあらかじめ対象について
調べておくんです」
特にWWFの連載では、会報発行時の季節の植物を
描くため、
制作している時点ではその植物が「季節に合わない」
ことがほとんどなのだそうです。
そこで、折を見てはさまざまな植物の姿を
いつもスケッチブックにストックされているのだとか。
「あの、写真ではわからないことが多いんですよ。
“がく”や“苞(ほう)”がどうなっているかとか、
雄しべや雌しべの“付け根”の部分がどうなってるか、
“軸”が巻いてるか、巻いてないかとか・・・。
描きとめておくと、あやふやな部分がなくなります」

(“シロツメクサ”。「“付け根”の部分。ここがどういう状態がしっかり描けていることが重要なんです」(杉野さん)」
記録のための道具として、
通常、私たちが信頼をおいているカメラ。
しかし、植物や小さな生物の細部をすみずみまで記録するには、ある部分に焦点を絞ることで、他の部分がぼやけてしまうのが難点なのだそうです。
また研究上“見たいもの”が、写真に写っていない
ことも多く、総合すると、
「人の目で見て絵に描かれたもの」の役割は
やはり大きいとのこと。
お話を伺っていると、私たちの“目”や“手”とは
非常に高性能の道具だったのだと気づかされます。

(「透明水彩で、白い絵の具を使わずに描く」というボタニカルアート。「上手い下手があるというより、最後は根気の世界だと思います。どこまで途中でいやにならずに描けるか、という」)
身近な植物や生き物を細部まで忠実に描いた
杉野さんの細密画。
今回の展示では、その数々の絵に加えて、
様々な昆虫の標本も展示されています。
こちらももちろん杉野さんが自ら作られたもの。
絵と同様“細部をじっと見たくなる”美しい仕上がりです。

(見事な昆虫コレクション。全部はお見せできませんが一部だけご覧ください。
標本も細密画の制作に欠かせないもの。
「生きている虫はやはり動くので…羽根や脚がどうなっているかなど標本で見ます」)
-あの、よく質問されることだと思うのですが、
女性で標本を作られることを珍しいと言われたり
しませんか…?-
「いや、女性どころか…主婦で珍しいと(笑)
息子がいるんですけど、あんまり虫に興味がなくて、
ちょっと引かれてます(笑)
私はイモムシなんかでも、毒のあるものとないものの区別がつくので、毒のないものを何気なく持って、息子に
『はい』って手渡そうとすると、
『もうお母さんやめて』って(笑)」
普通、男の子が虫を家に持ち込んで、
お母さんが嫌がる状況というのはよくありますが
杉野さんのお宅では逆の構図なのですね。
イモムシを素手でさわれるお母さん。
何というか…かっこいいです!本当に。

(子どもが家に持って来る虫の代表格、“ダンゴムシ”。
細密画だとちょっと怖いようですが、小さな体の見事に完成された構造を、絵を通して知ることができます。
「今の時代って、何でも危ないって言うでしょう。
蜂だとか、危なくない蜂もいるんですよ。
ドロバチなんかは、あえて巣を荒らしにいくとか、
よっぽどのことをしないかぎり攻撃してこない」
確かに蜂は種類によって、また攻撃性を刺激してしまった時などは危険ですが、
巣作りの時期など、近くを飛んでいても
忙しいから人間のことなんて構っていなさそうな
気配の蜂もしばしば見かけます。
「あと、虫にはつかみ方がありますよね。
つかみ方が悪いと噛まれたりするわけです。
トンボとか、頭から持ったらそれは噛みつかれます(笑)
羽根を指の間にこう挟んで持つやり方とかね。
カマキリでもバッタでも、それぞれつかみ方があって」
“怖い”と思って避けることは、逆に自然がこちらにくれる
様々な情報をシャットアウトしてしまうこと。
そこで発される自然からのシグナルに鈍感になると、
人はどんどん自然の中でそぐわない行動をとるように
なり、結果、危険な目に遭ってしまうのではないか…。
杉野さんのお話を聞きながら、そんなことを考えました。

(杉野さんが魅せられた虫“オトシブミ”。葉に卵を産み付け、その自分より何倍も大きな葉を巻き手紙のようにくるくると丸める習性からこの名がついたとか。
「葉を丸める様子が面白くて、何時間でも観察していました」)
杉野さんのお話はどこまでも面白く、時間を忘れて
いつまでも聞いていたくなるのですが、
最後に、会場にいらっしゃる方へのメッセージを
お伺いしました。
「そうですね。会場にある作品を見て、
身近な生き物に興味を持ってもらいたいですね。
実際の生き物が、絵に描かれてあるようになって
いるか、見てほしいなと思います。
私の絵に描かれてあるものは珍しいものでは
ないので、すぐに見つかるはずですから」
子どもの頃は誰でも背が低くて視線が地面に近く、
目に入る草花と虫の世界はまさに細密画そのもの
だった。
そのことを、杉野さんの作品は鮮やかに思い出させて
くれます。
一枚の葉に広がる葉脈が驚くほど精緻であることや、
昆虫の細い脚やうすい羽が、すごい運動能力を秘めて
いることをじっと観察しながら、
私たちは「世界は本当によくできている」ことを
学んで大人になってきたのではなかったでしょうか。
なんだか気持ちが忙しく疲れた時に、すぐ足元にある
小さな世界をじっと眺めてみると、
そこには思いがけず、
豊かで濃密な世界が広がっているのかもしれません。
(10月3日(金)・10月7日(土)は休館日です)

アジア大会、ご覧になられていますか?
滋賀出身のフェンシング太田選手、
シンクロ乾選手の活躍もとても嬉しかったのですが、
個人的には男女ともに日本選手が銅メダルを獲得した
「トランポリン」に魅せられてしまいました

空中での的確で美しい身体の動き、素敵ですよね。
今後注目していきたい競技になりました!
さて、秋のわたむき美術ギャラリー、
新しい展示がはじまりました。
杉野 由佳 細密画展
~身近な自然と
出会える瞬間~
9月26日(金)~10月13日(月・祝)

高校卒業後、京都の専門学校で自然環境について学び、
野山でのフィールドワークの際、植物や生物の絵を描き
はじめたことから細密画を手がけるようになった、
杉野由佳さんの展覧会です。
現在はWWF(世界自然保護基金)ジャパンの会報に
絵を描くお仕事もされています。
杉野由佳さんはこの方です。

現在、小学校6年生になる息子さんのお母様でもある
杉野さん。
しかし、植物や小さな生き物の話になると、
好奇心に満ちた探検家のような、活き活きとした
表情になられるのがとても印象的でした。
そして杉野さんからお聞きする自然のお話が、
とにかく面白いのです。
私たちの足元に広がる「小さな世界」の不思議。
さっそくお届けしたいと思います!

まずは、「自然を写実的に描く」ということについて。
春に開催した、バラのボタニカルアート展の作家、
須田久仁子さんにお伺いしたことですが、
カメラのない時代には、植物や生物の絵が、
自然を研究するうえで、非常に重要だったそうです。
(杉野さん)「そうです。有名な話ではイギリスのキュー
ガーデンに、お抱えの絵師がいたというのがあります。
日本では、シーボルトが日本の絵師に、写実的な技法を伝えたといわれています。
植物の研究・観察のために描く絵としては、
“生態的”に描く方法と“標本的”に描く方法があります。
どちらにしても大切なことは
“嘘を描かない”ことなんですね」
“嘘を描かない”とは、
目の前にある対象そのものを忠実に描くということ、
と、杉野さんはひとまず定義されます。

(“ツユクサ”花の部分を抜き出して拡大してあります。雄しべと雌しべの長さがこんなに違うことに、今まで気づきませんでした。)
「でも、自然のものって個体差に幅があるんですよ。
普通、花びらが6枚の花なのに7枚ついているものと
遭遇してしまったら、
自分にその花の知識がないと、そのまま描いてしまう。
嘘をつかないとはいっても、絵にするときは、
その対象の“典型的な”形を描かないといけないので。
だから、絵を描く前にはあらかじめ対象について
調べておくんです」
特にWWFの連載では、会報発行時の季節の植物を
描くため、
制作している時点ではその植物が「季節に合わない」
ことがほとんどなのだそうです。
そこで、折を見てはさまざまな植物の姿を
いつもスケッチブックにストックされているのだとか。
「あの、写真ではわからないことが多いんですよ。
“がく”や“苞(ほう)”がどうなっているかとか、
雄しべや雌しべの“付け根”の部分がどうなってるか、
“軸”が巻いてるか、巻いてないかとか・・・。
描きとめておくと、あやふやな部分がなくなります」

(“シロツメクサ”。「“付け根”の部分。ここがどういう状態がしっかり描けていることが重要なんです」(杉野さん)」
記録のための道具として、
通常、私たちが信頼をおいているカメラ。
しかし、植物や小さな生物の細部をすみずみまで記録するには、ある部分に焦点を絞ることで、他の部分がぼやけてしまうのが難点なのだそうです。
また研究上“見たいもの”が、写真に写っていない
ことも多く、総合すると、
「人の目で見て絵に描かれたもの」の役割は
やはり大きいとのこと。
お話を伺っていると、私たちの“目”や“手”とは
非常に高性能の道具だったのだと気づかされます。

(「透明水彩で、白い絵の具を使わずに描く」というボタニカルアート。「上手い下手があるというより、最後は根気の世界だと思います。どこまで途中でいやにならずに描けるか、という」)
身近な植物や生き物を細部まで忠実に描いた
杉野さんの細密画。
今回の展示では、その数々の絵に加えて、
様々な昆虫の標本も展示されています。
こちらももちろん杉野さんが自ら作られたもの。
絵と同様“細部をじっと見たくなる”美しい仕上がりです。

(見事な昆虫コレクション。全部はお見せできませんが一部だけご覧ください。
標本も細密画の制作に欠かせないもの。
「生きている虫はやはり動くので…羽根や脚がどうなっているかなど標本で見ます」)
-あの、よく質問されることだと思うのですが、
女性で標本を作られることを珍しいと言われたり
しませんか…?-
「いや、女性どころか…主婦で珍しいと(笑)
息子がいるんですけど、あんまり虫に興味がなくて、
ちょっと引かれてます(笑)
私はイモムシなんかでも、毒のあるものとないものの区別がつくので、毒のないものを何気なく持って、息子に
『はい』って手渡そうとすると、
『もうお母さんやめて』って(笑)」
普通、男の子が虫を家に持ち込んで、
お母さんが嫌がる状況というのはよくありますが
杉野さんのお宅では逆の構図なのですね。
イモムシを素手でさわれるお母さん。
何というか…かっこいいです!本当に。

(子どもが家に持って来る虫の代表格、“ダンゴムシ”。
細密画だとちょっと怖いようですが、小さな体の見事に完成された構造を、絵を通して知ることができます。
「今の時代って、何でも危ないって言うでしょう。
蜂だとか、危なくない蜂もいるんですよ。
ドロバチなんかは、あえて巣を荒らしにいくとか、
よっぽどのことをしないかぎり攻撃してこない」
確かに蜂は種類によって、また攻撃性を刺激してしまった時などは危険ですが、
巣作りの時期など、近くを飛んでいても
忙しいから人間のことなんて構っていなさそうな
気配の蜂もしばしば見かけます。
「あと、虫にはつかみ方がありますよね。
つかみ方が悪いと噛まれたりするわけです。
トンボとか、頭から持ったらそれは噛みつかれます(笑)
羽根を指の間にこう挟んで持つやり方とかね。
カマキリでもバッタでも、それぞれつかみ方があって」
“怖い”と思って避けることは、逆に自然がこちらにくれる
様々な情報をシャットアウトしてしまうこと。
そこで発される自然からのシグナルに鈍感になると、
人はどんどん自然の中でそぐわない行動をとるように
なり、結果、危険な目に遭ってしまうのではないか…。
杉野さんのお話を聞きながら、そんなことを考えました。

(杉野さんが魅せられた虫“オトシブミ”。葉に卵を産み付け、その自分より何倍も大きな葉を巻き手紙のようにくるくると丸める習性からこの名がついたとか。
「葉を丸める様子が面白くて、何時間でも観察していました」)
杉野さんのお話はどこまでも面白く、時間を忘れて
いつまでも聞いていたくなるのですが、
最後に、会場にいらっしゃる方へのメッセージを
お伺いしました。
「そうですね。会場にある作品を見て、
身近な生き物に興味を持ってもらいたいですね。
実際の生き物が、絵に描かれてあるようになって
いるか、見てほしいなと思います。
私の絵に描かれてあるものは珍しいものでは
ないので、すぐに見つかるはずですから」
子どもの頃は誰でも背が低くて視線が地面に近く、
目に入る草花と虫の世界はまさに細密画そのもの
だった。
そのことを、杉野さんの作品は鮮やかに思い出させて
くれます。
一枚の葉に広がる葉脈が驚くほど精緻であることや、
昆虫の細い脚やうすい羽が、すごい運動能力を秘めて
いることをじっと観察しながら、
私たちは「世界は本当によくできている」ことを
学んで大人になってきたのではなかったでしょうか。
なんだか気持ちが忙しく疲れた時に、すぐ足元にある
小さな世界をじっと眺めてみると、
そこには思いがけず、
豊かで濃密な世界が広がっているのかもしれません。
(10月3日(金)・10月7日(土)は休館日です)